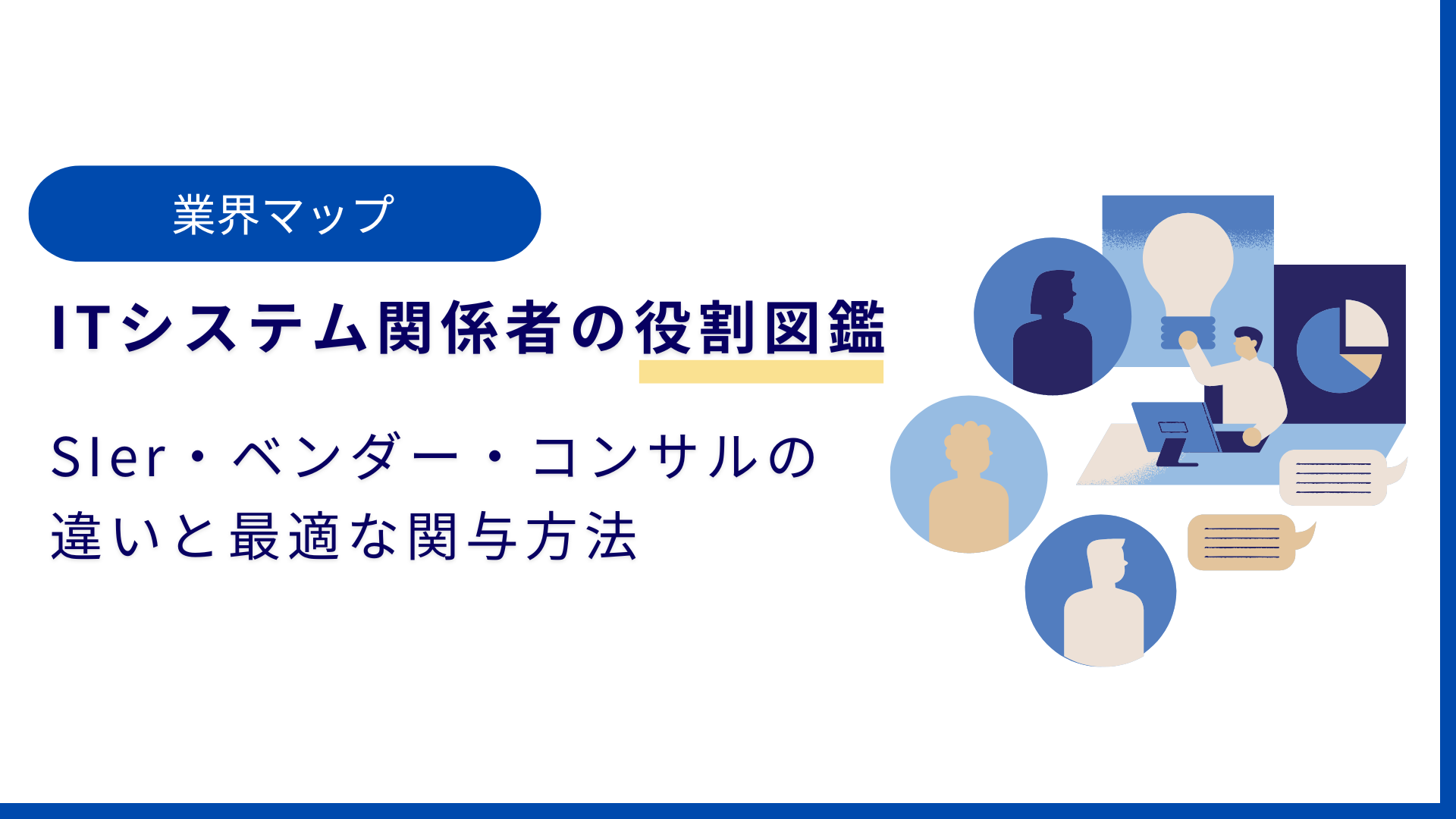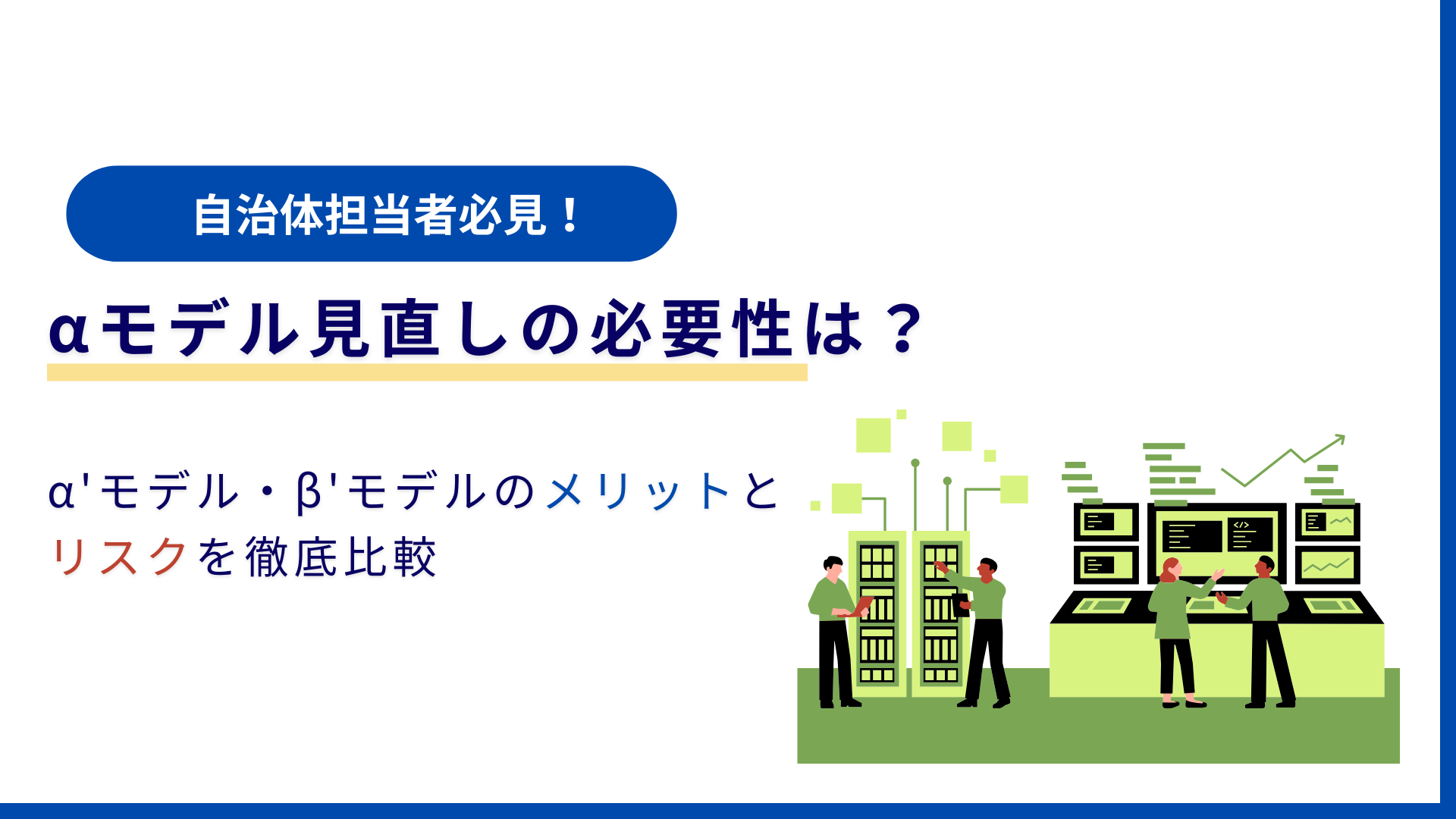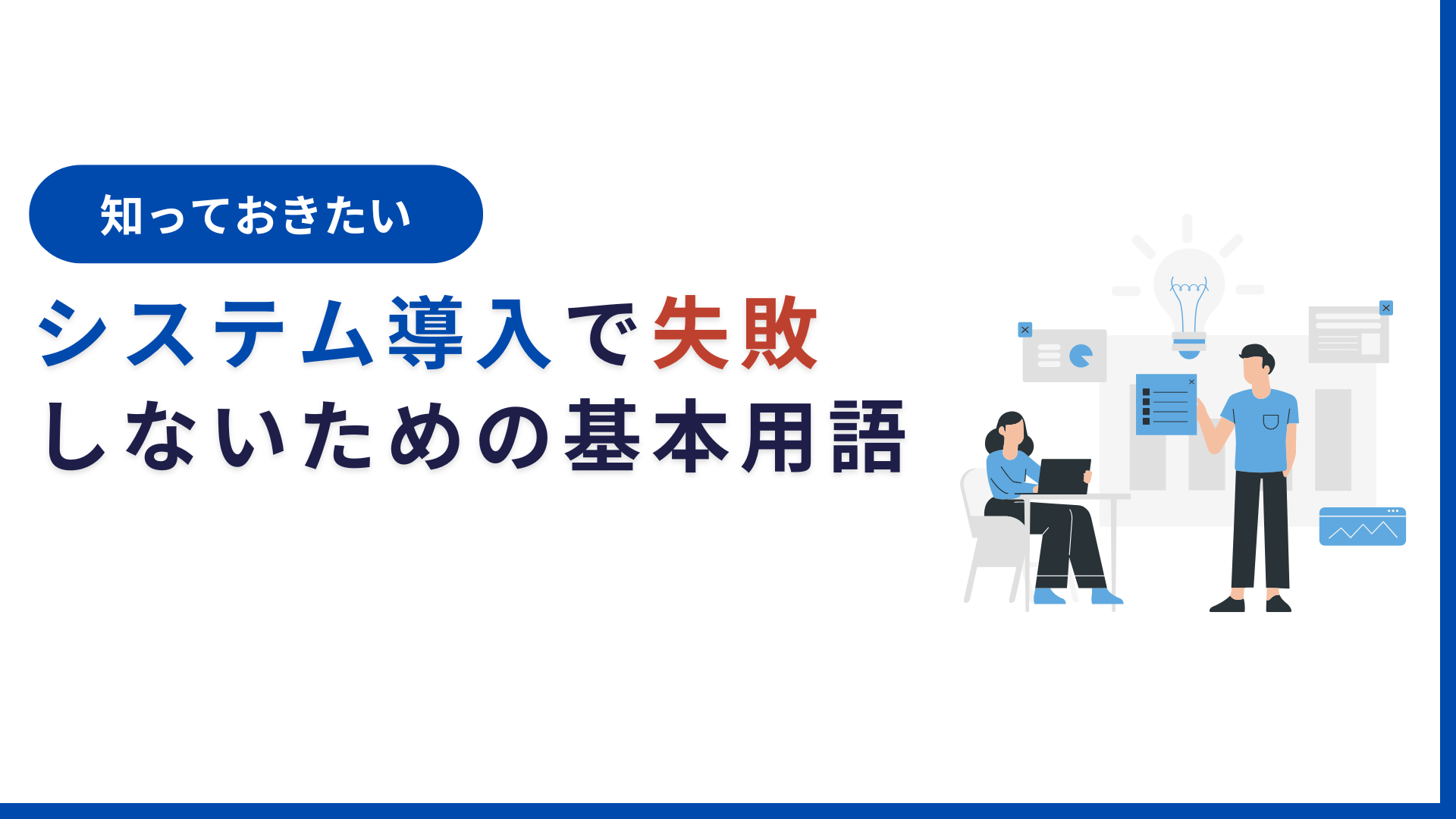
システム導入で失敗しないために導入前に知っておきたい基本用語26選
「新しいシステムを導入することになったけど、専門用語が多すぎてよくわからない・・・」
「システム導入プロジェクトはどうすれば円滑に進めることができるんだろう・・・」
システム導入は組織において重要なプロジェクトであり、専門性が高いかつ業務負荷も大きくなるので、担当する方にとってはプレッシャーを感じる場面があるかと思います。
また、システム導入は頻繁に行うものではないので、組織内に有用なナレッジが蓄積しにくいのも悩ましいポイントです。
例えば、前回導入プロジェクトを行ったのは5年以上前でありその時の知見をもったメンバーが存在せず前回のプロジェクトの詳細な経過がわからないので、どうプロジェクトを進めていけばよいかわからない状況に陥ってしまうことがあります。
本記事は、新しいシステムを導入する、または既存システムを刷新するプロジェクトを進める前に、あらかじめ知っておいた方が良い基本的な用語の意味や実際に使われる場面などについて、わかりやすく解説する記事です。
本記事を読むことで、システム導入を進める前に必要な基礎知識を身につけることができますので、プロジェクトを進める前にぜひご一読ください!
目次
システム導入の企画段階や契約に関する用語
まず初めに、システム導入プロジェクトの企画段階において頻出する用語や、契約に関する用語をご説明します。
RFI
RFIは、Request For Information(情報提供依頼書)の略称です。
どんなシステムが自組織にとって良いものなのか見定めるために、発注先のシステム開発会社・パッケージ製品の選定や調達などに向けた情報収集を行うために発注先候補の会社に対して、会社の基本情報・技術情報・パッケージ製品の情報などの情報提供を依頼する文書を発出します。
この情報提供を依頼する文書のことを、RFIといいます。
RFIを発出して発注先候補の会社に回答を依頼することで、一般に公開されているウェブサイトやパンフレットでは得られない情報提供を受けることができる点がメリットといえます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
また、RFIを作成するときの具体的な進め方については、下記リンクの記事が参考になります。
【項目サンプルあり】RFI(情報提供依頼書)とは?目的やメリット、RFPとの違いを分かりやすく解説! – IT調達ナビ
RFP
RFPは、Request For Proposal(提案依頼書)の略称です。
発注先の候補となっているシステム開発会社に対して、システムの具体的な提案を依頼するために文書を発出します。
このシステムの具体的な提案を依頼するための文書のことを、RFPといいます。
RFPは、候補会社に提案書を提出してもらい、発注先のシステム開発会社を評価・決定するために実施します。
また、RFPで発注者側の要望を明文化して候補会社に伝えることで、システムに求める要件について発注者側と開発者側の相互理解が深まることもメリットの1つです。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
また、RFPを作成するときの具体的な進め方については、下記リンクの記事が参考になります。
【初心者編】RFPとは?RFP作成のメリットや注意点、RFIやRFQなど分かりやすく解説! – IT調達ナビ
As-Is(アズイズ)・To-Be(トゥービー)
それぞれ英熟語としては、As-Is(アズイズ)は「現状」、To-Be(トゥービー)は「理想像」という意味があります。
IT分野では、現在の業務フローや現行システムの「現状の姿」のことをAs-Is、新システム導入後の業務フローや新システムの「あるべき姿」のことをTo-Beと呼びます。
実際のシステム導入を検討する場面では、現状のことを示す際に「As-Is○○」、システム導入後のことを示す際に「To-Be○○」のように使うことがあります。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
As-Is(アズイズ)・To-Be(トゥービー) – IT調達ナビ
BPR
BPRとは、ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(Business Process Re-engineering)の略称で、企業の業務プロセスを抜本的に見直し、最適化するための手法です。
システム導入の際に併せて業務プロセスそのものを見直すことにより、業務効率が向上します。
大まかな流れとしては、現在の業務プロセスの現状分析を行い、既存の問題点を解消した業務プロセスの再設計と実施を行います。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
請負契約
請負契約は、受注側が決められた成果物を作成し、期限内に納品することを約束するために締結する契約の形態です。
システム導入の請負契約における成果物の例としては、導入されるシステムそのもの(ソフトウェア)や、システムの仕様書/設計書、テスト計画書などが挙げられます。
具体的に何を成果物として定義するかについては、契約の都度決めることになります。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
準委任契約
準委任契約は、決められた業務を遂行することを目的とした契約の形態です。
システム導入のプロセスにおいては、要件定義、受入テストのサポート、システム利用のトレーニングなどに適用されます。
請負契約は受注側が決められた成果物を作成し期限内に納品することを約束する性質の契約ですが、順委任契約は役務提供を目的とした契約であるため、契約の目的に応じてどちらの契約形態が適しているか判断する必要があります。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
システム類型に関する用語
次に、システム類型に関する用語をご説明します。
ERP
ERPは「エンタープライズ・リソース・プランニング (enterprise resource planning)」の略称です。
企業における各部門の人的資源や情報等のリソースを統合的に管理することによって、企業の経営や業務全般の最適化・効率化を図る考え方、またはそれを実現するシステムのことを指します。
統合的に管理する業務機能の単位としては、「会計業務」「人事業務」「生産業務」「物流業務」「販売業務」などがあります。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
ポストモダンERP
ポストモダンERPとは「次世代型のERP」のことです。
具体的には、ERPで実現する機能を主要な業務に絞り、不足する機能はSaaSなどのクラウドサービスを活用して、複数のアプリケーションを連携させて実現する方式のことです。
現在日本に普及している多くのERPのシステムはすべての業務やデータを管理する統合型のERP(モノリシック型ERP)と呼ばれるものですが、最近はポストモダンERPの考え方に基づく製品も多く出てきている状況です。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
また、ポストモダンERPのメリットや導入実現に向けたポイントについては、下記リンクの記事をご覧ください。
ポストモダンERPとは?現状の課題やメリットや実現に向けたポイントを解説! – IT調達ナビ
SFA
SFAは、Sales Force Automationの略で、「営業支援システム」のことを指します。
システムの機能としては、営業活動を可視化することで、時間とリソースを最大限有効活用し、営業活動の効率化や利益拡大することを目的とするものがあります。
SFAの活用により、営業活動の効率化、データ管理の一元化、営業戦略の最適化などのメリットを得られます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
SaaS
SaaSは「Software as a Service(ソフトウェア・アズ・ア・サービス)」の略で「サース」と呼び、インターネットを通じてソフトウェアを提供する方式のことを指します。
いわゆるクラウドサービスの一つです。
Saasを利用することによるメリットとしては、ソフトウェアの導入や維持管理のための定期的な点検の手間が減ること、インターネット接続があればどこからでも利用できること、利用量や利用者数に応じてサービス内容を変更できることなどが挙げられます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
CRM(顧客管理システム)
CRMとはカスタマー・リレーションシップ・マネジメント(Customer Relationship Management)の略称で、企業が顧客との関係を構築・維持・強化するための経営戦略や手法のことを指します。
そこから転じて、上記のためのシステムをCRM(顧客管理システム)と呼称するようになってきています。
CRMを導入するメリットとしては、顧客理解の深化、業務効率の向上、顧客満足度の向上、売上・利益の増加、データドリブンな経営判断が可能となる、などが挙げられます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
販売管理システム
販売管理システムは、企業の販売プロセス全般を統合的に管理する機能を持ったシステムです。
販売管理システムの導入により、商談から受注、出荷、売上までのワークフローを一元化することができ、下記のようなメリットを得ることができます。
- 意思決定の迅速化
- コスト削減と収益性の向上
- 顧客満足度の向上
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
POSシステム
POSシステムのPOSはPoint of Sale Systemの略で、日本語では販売時点情報管理といいます。
商品販売の際、支払いがされる時点での商品情報や販売数量、金額、日時などの情報を即座に収集・記録し、それに基づいた売上や在庫を管理するためのシステムです。
POSシステムの導入により、下記のようなメリットを得ることができます。
- 正確な販売データのリアルタイム収集
- 効率的な在庫管理
- 迅速な経営判断のサポート
- レジ業務の効率化と待ち時間短縮
- 顧客情報の収集と分析による顧客サービスの向上
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
パッケージ
IT分野におけるパッケージとは、一定の機能を備えた上で既に製品化されているソフトウェア、システムのことを指します。
パッケージのメリットは、「初期費用を抑えられる」「短期間で導入できる」ことです。
パッケージの導入を検討する上で注意したいポイントは、「自社特有の業務には対応できない可能性がある」ことです。
パッケージは特定の領域に絞った業務かつ汎用的な標準機能を有することが多いため、独自性の高い業務の場合には適合しない可能性があります。
上記の場合の対応策などについて、より詳しく知りたい方は下記リンクの記事をご覧ください。
システム要件の種類と定義プロセスに関する用語
続けて、システム要件の種類と定義プロセスに関する用語をご説明します。
業務要件
業務要件とは、あるサービスや業務が達成すべき目的と、その達成に必要な機能や条件を具体的に記述したものです。
この業務要件を記述した文書は、システムの刷新や導入において、業務ユーザーの視点からシステムの要求仕様を明確にするためにはとても重要なものです。
業務要件の定義においては、発注者側が主体的に実施することが望ましいため、外部委託を行う場合においても事業者に丸投げにせず、発注者が積極的に関わる必要があります。
また、デジタル庁の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」では、以下の8種類を業務要件と定義しています。
- 業務実施手順
- 規模
- 時期・時間
- 場所など
- 管理すべき指標
- システム化の範囲
- 業務の継続の方針など
- 情報セキュリティ
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
機能要件
機能要件とは、導入するシステムが最終的に満たすべき機能のことです。
機能要件の種類について、デジタル庁の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」では、以下の5種類を機能要件と定義しています。
- 機能
- 画面
- 帳票
- データ
- 外部インターフェース
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
非機能要件
非機能要件とは、システム開発で定義するもののうち、機能要件以外の要件のことです。
「情報システムの非機能要件」は、処理の実行速度などの「性能」や、システムの「セキュリティ」などを指します。
「プロジェクトの進め方に関する非機能要件」は、「移行」や「運用・保守」などを指します。
また、非機能要件は範囲が非常に広く、発注側での定義が難しい項目であるため、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」や「非機能要求グレード」などのガイドラインを活用して定義します。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
要求定義
要求定義とは、新システムの導入や既存システムの刷新の検討の際、発注者側としてシステムに求める仕様(システムで実現したいこと) を具体化することです。
要求定義を実施する主な目的は、「自分たちが求めている新システム像」を発注先の候補となるシステム開発会社に齟齬なく伝えることです。
このフェーズを疎かにしてしまうと、システム開発会社との認識相違に起因する手戻り等により想定以上の費用や工数が発生するリスクが増大するため、丁寧に実施することがとても重要です。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
要件定義
要件定義とは、システムで実現する業務や機能などを定義することです。
要件定義を実施する主な目的は、システム開発を依頼する開発会社側に、抜け漏れなく要望を伝え、システム開発作業を効率よく実施してもらうためです。
要件定義では、「業務要件」「機能要件」「非機能要件」の3種類を定義します。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
システム要件
システム要件とは、システム開発における要件定義のフェーズで、特定の業務要件を達成するためにシステムに求める要件のことを指します。
システムが具体的に何を達成すべきで、どのように動作すべきかを明確にする基準となるのがシステム要件です。
システム要件は、機能要件と非機能要件の二つに分類されます。
機能要件と非機能要件の両方が適切に満たされたシステムを利用し、自身の業務を適切に行うことができれば、システム利用者のニーズを満たすことができます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
Fit&Gap(フィット&ギャップ)
Fit&Gap(フィット&ギャップ)とは、パッケージを導入する際に、「パッケージの持つ機能」と「システム利用者の業務プロセスや求めるシステムの機能」を比較して突合し、 どれだけ適合(Fit)し、どれだけズレ(Gap)があるかを明らかする分析手法のことです。
パッケージと発注者側の求める要件の適合度合いとGapのある部分を確認することで、有力な製品を絞り込むことができ、さらに詳細なFit&Gapを実施することで見積もりのベースとなる要件や契約内容を固めることができます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
また、Fit&Gapの具体的な実施方法や、重要なポイントについては、下記リンクの記事が参考になります。
パッケージ導入時の要件定義に必要な「Fit&Gap」とは?実施方法やポイントを解説 – IT調達ナビ
システムの開発手法に関する用語
ここからはシステムの開発手法に関する用語について、ご説明します。
スクラッチ開発
スクラッチ開発とは、発注者側企業にとって最適化されたシステムをオーダーメイドでゼロから構築する開発手法のことを言います。
※先ほどご説明した「パッケージ」とは正反対の概念です。
メリットとしては、自社の業務に合わせて最適化された機能を実現できること、一般的にシステムの寿命が長くなることが挙げられます。
反対にデメリットとしては、独自機能を盛り込みすぎてシステムが複雑化し運用保守が難しくなる、パッケージと比較して導入コストが膨らんでしまいがちな点が挙げられます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
ウォータフォール型開発
ウォータフォール型開発とは、システムやソフトウェアの伝統的な開発方式であり、水が上から下に流れるイメージから「ウォーターフォール」と呼ばれています。
「要件定義(計画)」「外部設計」「内部設計」「プログラム設計」「プログラミング」「テスト」の工程に分け、一つの工程が終わったら次の工程に進んでいきます。
この開発方式では、原則的に前の工程に戻らないのが特徴です。
人的リソースが多く必要な大規模な開発プロジェクトや、要件が状況によって変化しない基幹系システムの開発に適しています。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
アジャイル型開発
アジャイル型開発は、近年注目が高まっている開発方式です。
ビジネス環境の変化に即時に適応できるよう、短い期間でイテレーション(※1)を繰り返す一連の開発手法を指します。
(※1)イテレーションとは、反復される短い期間の単位を指します。一般的に1つのイテレーション(反復)では、「設計」「開発」「テスト」の工程を行います。
システムの機能ごとに開発を行い、逐一リリースしていくようなイメージです。
ウォーターフォール型開発と比較して、仕様変更に柔軟に対応できること、仕様変更があっても大きな手戻りが発生しづらいことが特徴と言えます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
ノーコード、ローコード開発
ノーコード開発とは、プログラミングを一切行わずにアプリケーションやWebサービスなどを開発する手法です。
ローコード開発とは、ごく少量のプログラミングにより、同様にアプリケーションやWebサービスを開発する手法を指します。
どちらの開発ツールもプログラミング言語に関する知識を習得していなくても、システム開発が行えるよう設計されていることが特徴です。
様々な製品があるため、使用する開発ツールにより開発できるものも異なってきます。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
アドオン開発
アドオン開発とは、パッケージの標準機能で不足している機能を追加で開発することです。
パッケージは対象業務に対する標準的な機能が実装されており、発注側企業特有の業務やニーズに適合しない可能性があります。
そのため、適合しない部分について発注側企業独自の機能を追加するためにこのアドオン開発が用いられる場合があります。
また、アドオン開発の実施可否の検討においては、事前にFit&Gap(フィット&ギャップ)を行い、パッケージの機能と自社のニーズの適合度を整理する必要があります。
より詳しく知りたい方は、下記リンクの記事をご覧ください。
また、アドオン開発を行う際の留意点や具体的な実例の解説については、下記リンクの記事が参考になります。
パッケージ導入の鍵を握る「アドオン」と「カスタマイズ」それぞれの違いと留意点を解説! – IT調達ナビ
まとめ
新しいシステムを導入する、または既存システムを刷新するプロジェクトを進める前に、あらかじめ知っておいた方が良い基本的な用語の意味や実際に使われる場面などについて解説しましたが、理解は深まりましたでしょうか。
システム導入は組織において重要なプロジェクトであり、専門性が高いかつ業務負荷も大きくなるので苦労される場面も多いと思います。
また、自社のリソースだけでプロジェクトを成功させることが難しい場合、外部リソースを活用することも選択肢の一つです。
なお、当社は「この国の、システム発注の常識を変える。」を経営理念として、システム導入における発注者支援のサービス提供を行っています。
発注者側の知見不足に起因したシステム導入における様々な課題は、当社のサービスを活用することで解決できますので、お困りの方はぜひお気軽にお問い合わせください!
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!