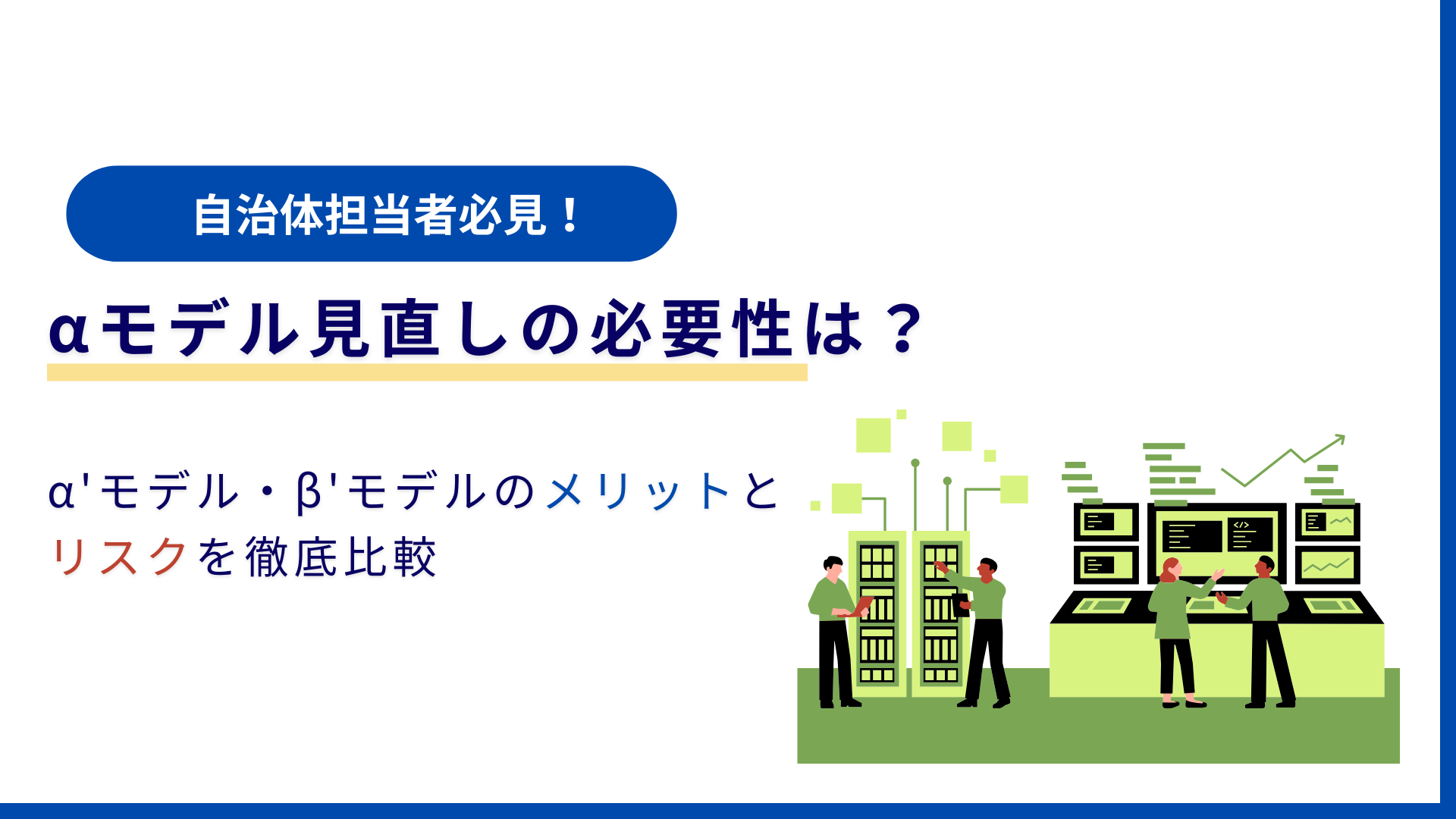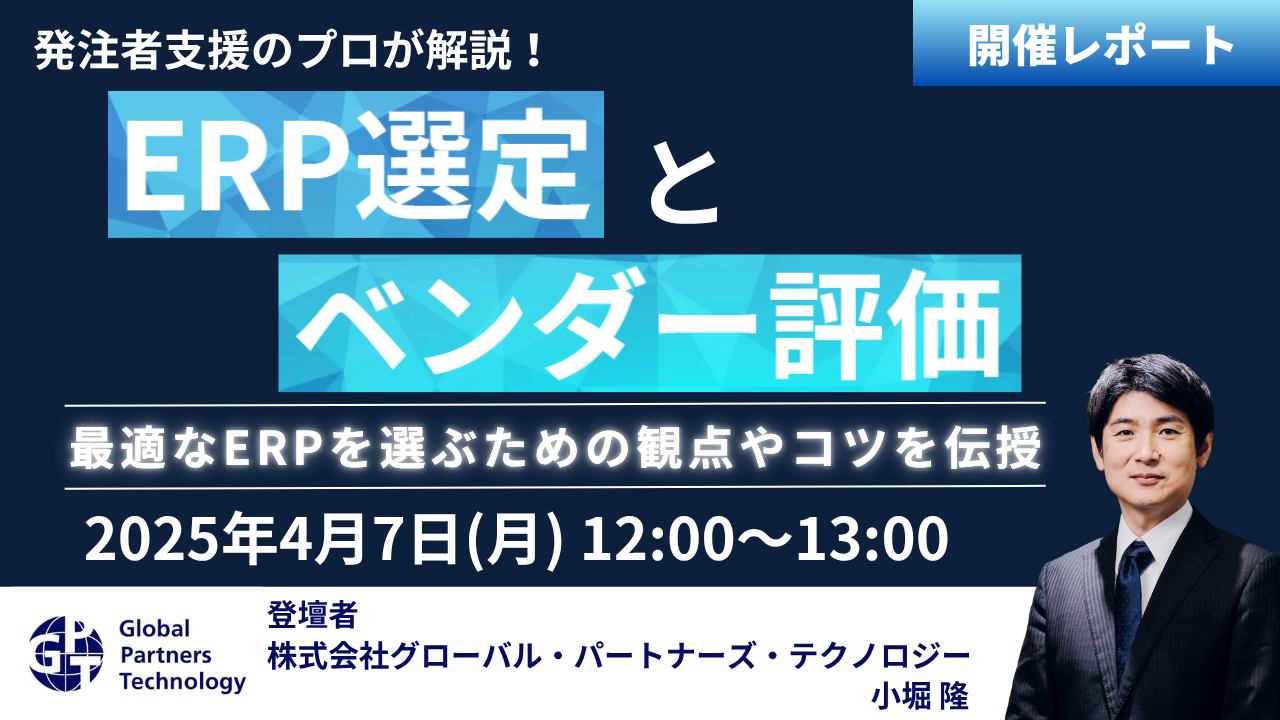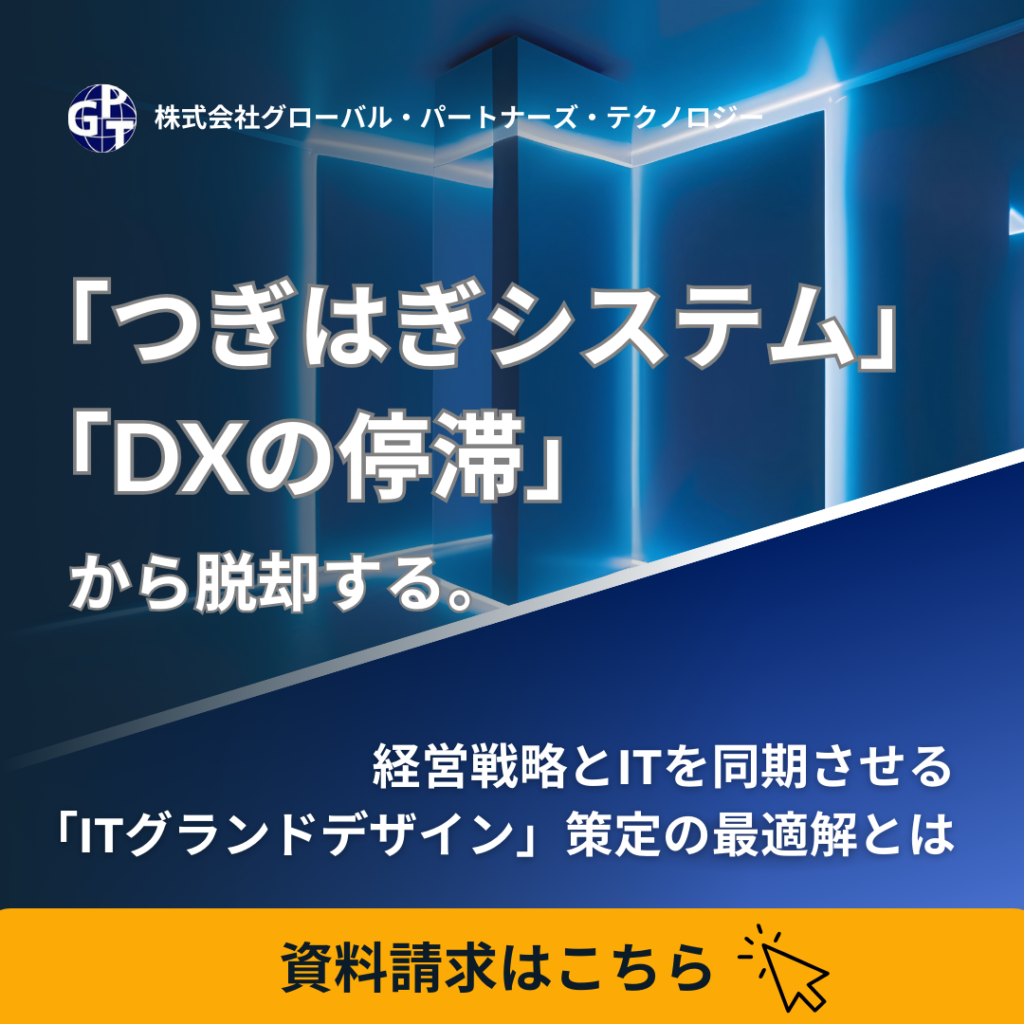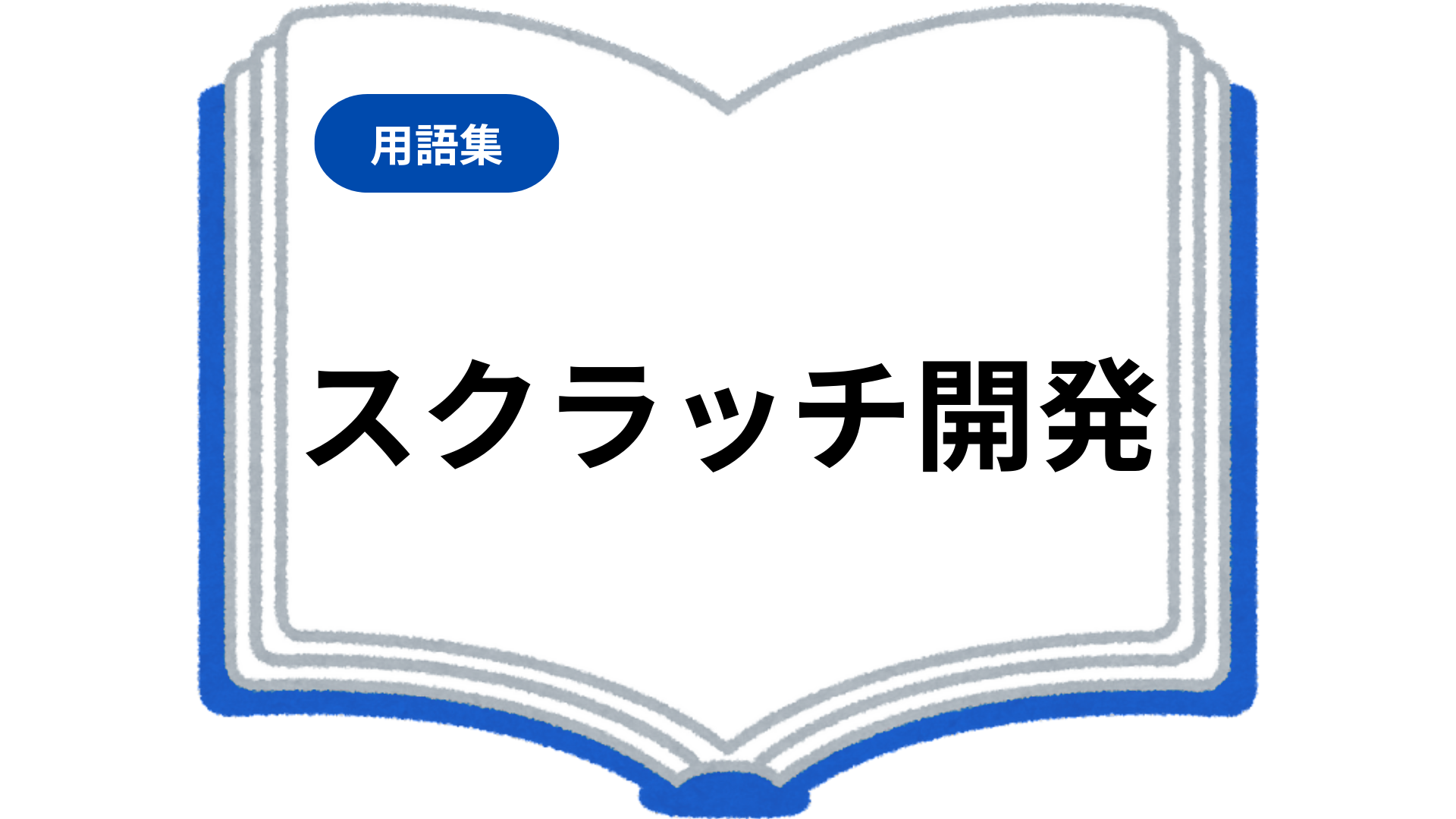
スクラッチ開発とは?メリット・デメリットや採用シーンについて解説
スクラッチ開発とは、発注者側企業にとって最適化されたシステムをオーダーメイドでゼロから構築することを言います。
スクラッチ開発では、要求定義をもとにして自社独自のシステムを構築することができます。
メリットは「競争優位の実現をシステムがサポートできる」「(一般的に)システムの寿命が長い」ことです。
デメリットは自社の業務に合わせたシステムを構築するため、「業務改善の意識が弱くなる傾向になる」「独自機能を盛り込みすぎてシステムが複雑化し、運用/保守が難しくなる」ことです。
スクラッチ開発では「ウォーターフォール型」や「アジャイル型」(またはその混合型)の開発手法が多く使われます。
その理由は「競争優位が必要な業務領域のシステムは、他社との差別化を実現するために、要求定義の段階から独自性が必要」なためです。
したがって「要求定義」の段階では、「要求定義とビジネス戦略がしっかりとかみ合っていること」を確認しながら進めることが重要です。
要求定義があいまいだったり、ビジネス戦略とずれていたりすると、要求定義自体に変更が発生してしまい、要求定義の後に続く要件定義、システム設計、プログラム作成など、いくつものシステム開発プロセスに手戻りが発生し、それが、システム開発期間の延長や開発予算の増加、システムの品質低下に繋がります。
また、「スクラッチ開発で作られたシステムは開発担当者への依存度が大きい」ことも特徴のひとつです。
そのため、システムが実際に稼働する際に必要な「運用設計ドキュメント」を整備して、開発担当者と運用担当者の間でシステムについての知識共有、知識移転を行う必要があります。
なお、スクラッチ開発とは違い、自社独自のシステムを開発するのではなく、既に製品化されているソフトウェアやシステムを「パッケージ」と呼びます。
システムが対象とする業務が一般的なものであり、他社との差別化要因とはならない場合は、パッケージの導入を行うことが推奨されます。
目次
よくある質問
スクラッチ開発を採用すべき適切なシーンや条件は何ですか?
スクラッチ開発は、自社固有の業務要件や特殊な機能が必要で、市販のパッケージソフトで対応できない場合にのみ採用すべきです。
また、高度なカスタマイズ性や拡張性を求める場合にも適しています。
スクラッチ開発を採用すべき主なシーン・条件
1. 独自性の高い業務要件がある場合
既存のパッケージソフトでは対応困難な独自の業務プロセスや機能が求められる場合に有効です。
2. 将来的な拡張や変更を見据えた柔軟性が必要な場合
長期的に業務変化に対応しやすい柔軟なシステム構築が求められるケースに適しています。
3. 競争優位性の確保が重要な場合
他社との差別化を図るために独自機能を実装し、ビジネス戦略に直結するシステムが必要な場合。
4. 既存システムとの連携が複雑な場合
複数のシステムと高度に連携する必要があり、標準的なソフトウェアでは対応が難しい場合。
5. セキュリティやコンプライアンスの要件が厳しい場合
特定のセキュリティ要件や法令遵守が求められ、市販製品の適用が困難な場合。
これらの条件に該当する場合、スクラッチ開発を検討することで、業務に最適化されたシステムの構築が可能となります。
ただし、コストや期間が一般的に長くなるため、慎重な判断が必要です。
スクラッチ開発とパッケージソフト導入の比較ポイントは?
スクラッチ開発とパッケージソフト導入は、それぞれ特性や適用条件が異なるため、発注者は要件適合性やコスト、導入期間、拡張性、運用負荷などの観点から比較検討することが望ましいでしょう。
比較すべき主なポイント
1. 要件適合性
・スクラッチ開発は自社独自の業務要件に合わせて柔軟に設計できる場合が多いです。
・パッケージは既成の機能を利用するため、要件に完全に合わないこともあり、カスタマイズが必要になるケースがあります。
2. 導入コストと期間
・スクラッチ開発は設計・開発に時間やコストがかかる傾向があります。
・パッケージは比較的短期間かつ低コストで導入できる場合が多いです。
3. 拡張性・柔軟性
・スクラッチ開発は将来的な機能追加や業務変更に対して柔軟に対応しやすいことがあります。
・パッケージは拡張性に制限がある場合があり、カスタマイズに制約が生じることがあります。
4. 運用・保守負荷
・スクラッチ開発は保守や運用に関して自社または開発元の体制が必要となり、負荷が増すこともあります。
・パッケージはベンダーの保守サービスを利用できるため、運用負荷が比較的軽減されるケースが多いです。
5. リスク管理
・スクラッチ開発は開発リスクが高く、要件変更や遅延の影響を受けやすいことがあります。
・パッケージは検証済みの機能を活用できるため、相対的にリスクが低い傾向があります。
これらのポイントを踏まえ、発注者は自社の業務内容や予算、スケジュール、リスク許容度に応じて適切な選択を検討することが重要と考えられます。
スクラッチ開発で発注者が特に注意すべきリスクは何ですか?
スクラッチ開発においては、要件の不確実性や開発遅延、コスト超過、品質管理の難しさなど複数のリスクが存在し、発注者はこれらを事前に把握し適切に対応することが重要とされています。
発注者が注意すべき主なリスク
1. 要件定義の不十分さ
要件が不明確または変更が頻発すると、開発の方向性がぶれ、手戻りや再設計が多発する可能性があります。
2. 開発スケジュールの遅延
独自開発のため、技術的課題や仕様調整に時間がかかり、予定通りの納期が難しくなることがあります。
3. コストの増大
開発規模の拡大や変更対応により、当初の見積もりを超過するリスクがあります。
4. 品質確保の困難さ
独自仕様のためテストが複雑化し、不具合の検出・修正に時間とコストがかかる場合があります。
5. 技術的依存とノウハウの偏在
開発ベンダーや特定技術に依存しすぎると、保守・運用段階で問題が生じやすくなります。
これらのリスクに対して、発注者は要件定義の徹底、進捗管理の強化、品質保証体制の確立などを通じて、プロジェクトの安定推進を図ることが求められます。
スクラッチ開発における品質確保のための発注者の役割は?
スクラッチ開発において発注者は、品質確保のために要件定義の明確化、テスト計画の承認、進捗および品質の監督、ベンダーとのコミュニケーション強化など多面的に関与することが求められます。
発注者の主な役割
1. 要件定義の明確化と合意形成
システム要件を具体的かつ詳細に定義し、ベンダーと十分に合意を形成することで、開発品質の基盤を築きます。
2. テスト計画および品質基準の確認・承認
ベンダーが策定するテスト計画や品質基準を確認し、実務要件に適合しているかを承認します。
3. 進捗と品質状況の定期的な監督
開発およびテストの進捗報告を受け、品質関連の課題やリスクを早期に把握し適切に対処します。
4. ベンダーとの継続的なコミュニケーション
問題点や疑問点を迅速に共有し、改善策の検討・実施を促進するための密な連携を維持します。
5. ユーザー受入れテストの実施支援
実際の利用部門と協力し、受入れテストの実施や評価を支援し、実運用に耐えうる品質を確認します。
発注者がこれらの役割を積極的に担うことで、スクラッチ開発の品質確保に大きく寄与し、プロジェクト成功の可能性を高めることが期待されます。
________________________________________
あわせてこの用語と記事をチェック
・要求定義とは
・ウォーターフォール型開発とは
・アジャイル型開発とは
・パッケージとは