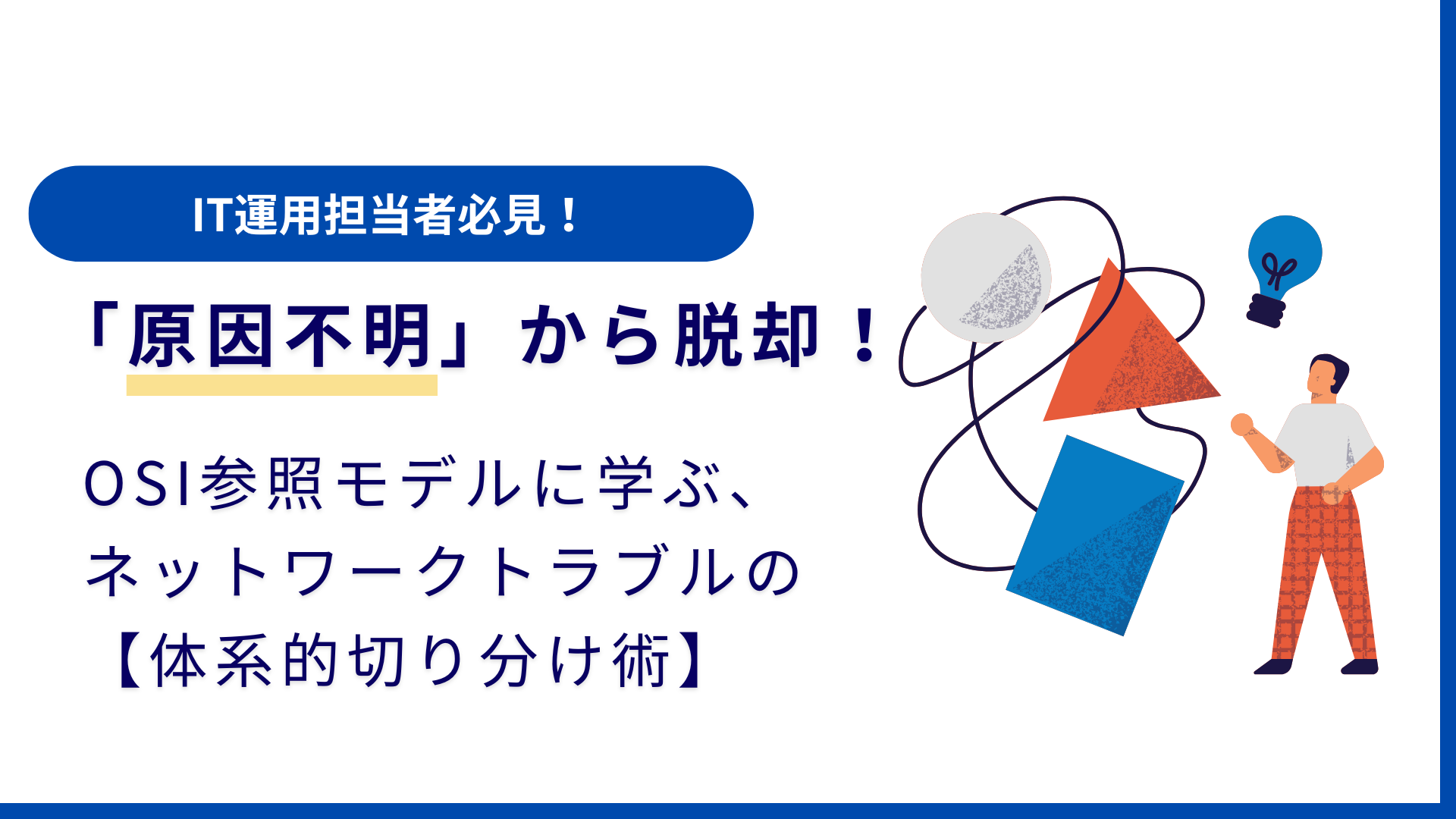RPAとは?業務の効率化を実現する最先端のテクノロジーについて解説
RPAとは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、人間がパソコン上で行っている事務作業を、ソフトウェアロボットによって自動化する技術を指します。
RPAは、手順が定型化された反復作業に適しており、大量のデータ整理や入力作業などを効率的に自動化することが可能です。
RPAによって代替できる作業の例は、以下の通りです。
- データの整理・登録
- 複数データの数値照合
- 定型書類の作成・発行
- 情報収集・分析
このように、RPAは人員不足の解消に貢献する技術として、様々な業界で活用されています。
特に自治体においては、以下のような業務への活用が広がっており、行政職員が本来注力すべき業務に専念できる環境づくりが進められています。
- 請求書の会計処理
- AI-OCRと組み合わせて大量の紙申請書類のシステム登録作業
その他のRPAの活用事例については、以下の記事をご参照ください。
参考リンク:https://gptech.jp/articles/it-strat-gov-bpr-3steps-9perspectives/
なお、RPAを導入する際には、業務の再構築(BPR:Business Process Reengineering)を前提とした検討が不可欠です。
業務フローの見直しや様式の標準化などに取り組まなければ、RPAの効果を十分に引き出すことができません。
また、RPAはあらかじめ定義された処理を正確に実行するのは得意ですが、「判断」を伴う作業はできません。
そのため、例外処理や確認作業などは人間が対応する必要があり、それらを踏まえた業務設計と効果測定が求められます。
BPRの進め方や導入時の留意点については、以下の記事もぜひご参照ください。
目次
よくある質問
RPAとAIの違いは何ですか?
RPAは、人がPC上で行う作業を「記録・再生」して自動化する技術で、決まったルールに従う定型業務に向いています。
ここでいう「ロボット」は、実際の機械ではなく「ソフトウェア上の仮想的なロボット」を指します。
一方AIは、データから学習・判断・予測ができる技術で、人の「考える力」を再現することを目指しています。
画像認識や会話の理解など、柔軟な処理が必要な業務に使われます。
RPAが「人の代わりに作業を行う」もの、AIは「考える力を補う」もの、と覚えるとわかりやすいでしょう。
RPAと従来の自動化(マクロやスクリプトなど)は何が違うのですか?
マクロやスクリプトは、使いこなせばブラウザ操作やファイル連携なども可能で、RPAと同様の処理を実現することもできます。
ただし、これらは一般的にプログラミングの知識や開発経験を必要とするため、専門的なスキルを持つ人でないと扱いが難しい場合があります。
一方、RPAはこうした技術的なハードルを下げることを目的として設計されており、ノーコードやローコードで操作可能なツールが多く、業務部門の担当者でも直感的な操作で自動化のシナリオ(処理手順)を作成できるのが特徴です。
また、RPAは複数のアプリケーションや画面をまたいで動作することが前提となっており、業務プロセス全体を横断的に自動化しやすいという利点があります。
そのため、「技術力がある人が使いこなす」マクロやスクリプトに対し、RPAは「現場の業務担当者でも扱いやすい」ツールとして、より幅広い人が業務自動化に関われる環境を提供していると言えます。
ただし、RPAはツール導入やライセンスにコストがかかることもあるため、業務の内容や複雑さ、利用者のスキルレベルを踏まえて、最適な手段を選ぶことが重要です。
RPAを導入することでどれくらいの時間やコストが削減できますか?
RPAを導入することで、定型業務にかかる作業時間や人件費を大幅に削減することが可能です。
国内の導入事例では、月間で数百時間、年間では数千時間以上の削減につながったケースも複数報告されています。
コスト面でも、年間数百万円〜数千万円規模の削減効果が得られた例があります。
たとえば、事務処理や請求業務、レセプト処理などの分野でRPAを導入した結果、業務時間の大幅な短縮と同時に、処理スピードや精度の向上を実現できた事例もあります。
ただし、効果の大きさは業務内容や導入範囲によって異なるため、事前の業務分析と費用対効果のシミュレーションが重要です。
中小企業でもRPAを導入できますか?導入形態によるコストの違いや選び方を教えてください。
中小企業でもRPAの導入は十分に可能です。
近年は、小規模な業務から始められる軽量なRPAツールが増えており、専門的なIT知識がなくても導入・運用できる環境が整ってきています。
日々の定型業務を自動化することで、業務効率化や人手不足への対応ができ、少人数体制の企業にとっても高い効果を発揮します。
RPAの費用感や導入ハードルは、運用形態によって異なります。
以下に代表的な3つのタイプを紹介します。
◉デスクトップ型RPA(コスト小/導入しやすい)
・一般的なPC上で動作し、1台の端末内で業務を完結させるタイプ。
・比較的低コストで導入でき、小規模な業務からスモールスタートが可能。
・操作も簡単で、現場担当者が自身で使い始めやすい点が特長です。
◉ クラウド型RPA(コスト中/柔軟性・拡張性あり)
・インターネット経由で利用するタイプで、複数端末や在宅環境にも対応。
・シナリオの共有や一元管理がしやすく、複数人での運用にも適しています。
◉ サーバー型RPA(コスト大/統合管理に強み)
・サーバー上で複数のロボットを集中管理・実行できる本格運用向けのタイプ。
・特徴は「管理機能」にあり、シナリオの統合管理、実行スケジューリング、ログ取得、運用監視などに優れているため、全社的な業務自動化に適しています。
まずは、自社内でどの業務が自動化に向いているかを見極めた上で、予算・運用体制・拡張性などを考慮しながら、自社に合った形式を選定することが重要です。