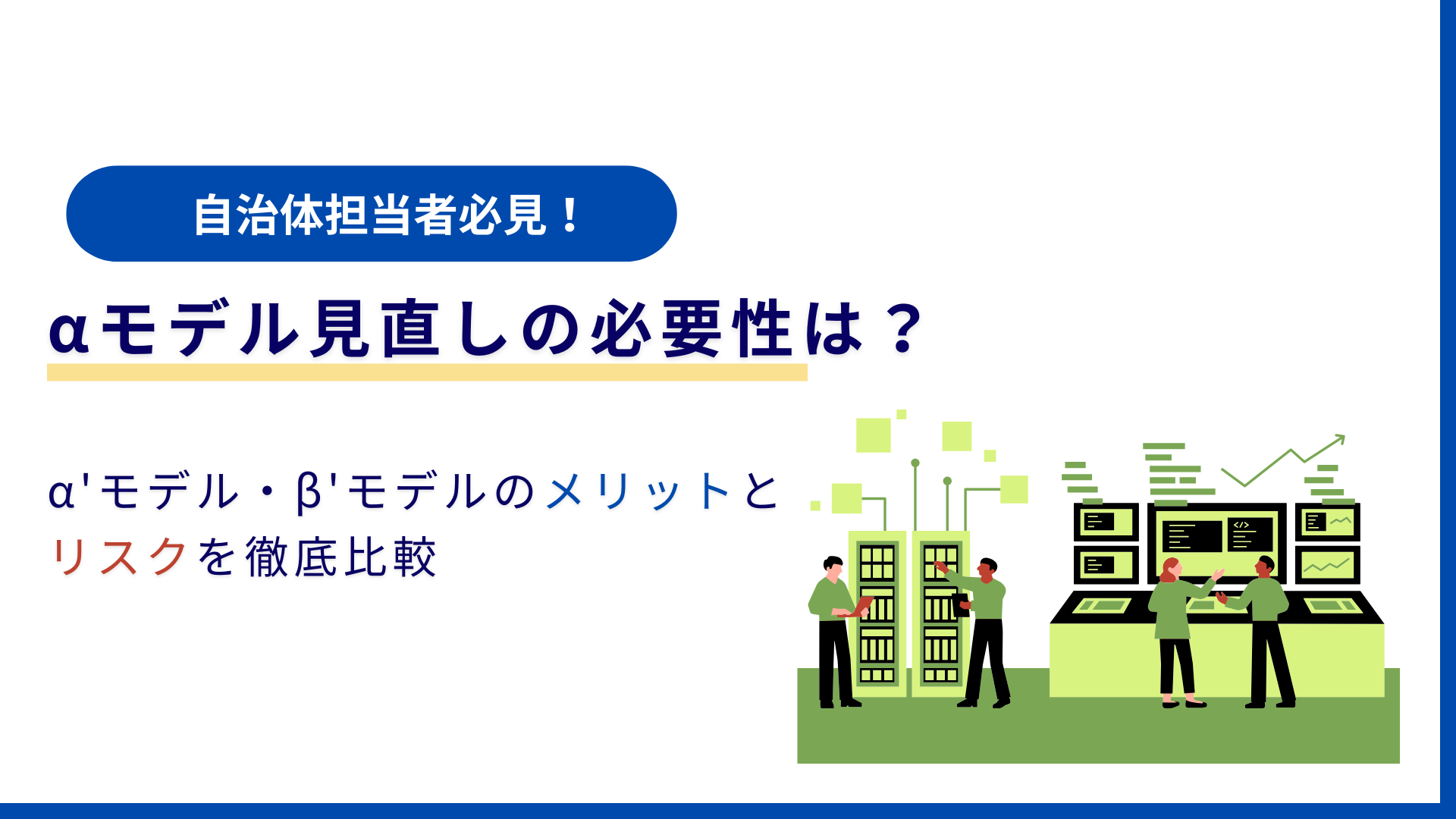RFIとは?システム調達前の情報収集に欠かせない文書について解説
RFIとは、Request For Information(情報提供依頼書)の略称です。
発注先のシステム開発会社・パッケージ製品の選定や調達などに向けた情報収集を目的とし、発注先候補の会社に対して、会社の基本情報・技術情報・パッケージ製品の情報などの情報提供を依頼する文書のことです。
RFIは、主に以下のようなケースで作成・発出されます。
- システム導入・刷新のための候補企業・製品の選定するとき
- 市場調査として、各ベンダーの技術力や製品特性を把握したいとき
RFIを活用することで、Webサイトやカタログだけではわからない、より詳細で実務的な情報を得ることが可能になります。
また、提供される情報が機密情報に当たる場合もあるため必要に応じてNDAを締結した上でRFIを発出します。
RFIを発出する主な目的は、「製品・サービスの選定や入札、調達などに向けた情報収集のため」です。
一般的に、RFIには以下のような項目を記載します。
- RFIを発出する側のプロジェクトの概要(プロジェクトの目的や自社情報の概要など)
- 情報提供依頼事項(相手会社の基本情報、技術情報、製品情報など)
- 手続要領(提出期限、連絡方法など)
- 回答様式(指定のExcelフォーマットなど)
なお、RFP(Request For Proposal:提案依頼書)は、システム開発やパッケージの導入を発注したいと考えている候補の会社に対して、発注者側からシステム開発の提案を依頼するために発出する文書のことです。
RFIを発出して必要な情報を収集した後、候補として有力な会社を絞り込み、最終的に発注先の会社を決定するための提案をもらうために発出するものです。
よくある質問
RFIはなぜ必要なのですか?どのような場面で使われますか?
RFIは、「自社に最適な選択肢を見極めること」を目的として、検討中のシステムやベンダーに関する情報を効率的に収集するために用いられます。
主に調達プロセスの初期段階で活用され、以下のようなケースで特に有効です。
候補となる製品やベンダーの情報が少ない場合:カタログやウェブサイトだけでは把握できない、技術力・実績・将来性などを知るため。
選定プロセスの土台づくり:市場にどのような選択肢があるかを把握し、自社にとっての要件や優先順位を明確にするため。
複数ベンダーから同条件で情報を収集したい場合:公平性・透明性を保ちながら、機能・価格・開発体制などの比較検討を行うため。
公共機関・自治体などでの導入時:ベンダーとの癒着防止やプロセスの正当性を証明するためにもRFIが活用されるケースがあります。
RFIで得られた情報を基に、自社の要件を整理し、次のステップであるRFP(提案依頼書)へとつなげていくことが、より納得度の高いシステム選定につながります。
RFIを出すときのポイントや注意点はありますか?
RFIを効果的に活用するためには、以下のポイントを意識することが重要です。
1.依頼の背景と目的を明確にする
なぜこのRFIを出すのか、何を達成したいのかを明確に記述します。ベンダーがニーズを正確に理解できるようにすることで、回答の質が向上します。
2.項目を細かくしすぎない
RFIはあくまで市場調査を目的とした文書です。詳細な要件を詰めすぎると、ベンダー側の負担も大きくなり、回答を得るまでに時間がかかってしまいます。必要な情報に絞ることが大切です。
3.求める回答内容は具体的に示す
「ライセンス費用」「初期導入費用」「保守費用」「クラウド対応の有無」など、知りたい項目を具体的に記載しておくことで、比較検討がスムーズになります。
4.秘密保持契約(NDA)を検討する
技術的な詳細や未公開の機能などを回答してもらう場合、ベンダーから「NDA締結」を求められるケースがあります。事前に想定し、必要に応じて明記しておくと安心です。
RFIは単なる問い合わせ文書ではなく、調達活動の方向性を決める重要な一手です。
ベンダーとの信頼関係構築にもつながるため、丁寧かつ戦略的に作成・運用することが求められます。
RFIを送ったあとのベンダーからの回答はどのように活用すればよいですか?
RFIを通じて得られたベンダーの回答は、単なる情報収集にとどまらず、要件定義やベンダー選定の精度を高めるための材料となります。
効果的な活用には、以下のようなステップが重要です。
1.回答内容を可視化し、整理する
各ベンダーの回答をExcelや一覧表に落とし込み、共通フォーマットで「機能要件への対応状況」「実績・ノウハウ」「費用感」などを整理します。「比較しやすい形にする」ことで、ベンダーごとの特徴や強み・弱みが明確になります。
2.比較検討の基礎情報として活用する
回答から得られた情報を基に、市場全体の傾向や技術トレンド、費用の相場感などを把握できます。これにより、「想定していた要件やコスト感が現実的か」を確認し、自社の方針や要件を調整する材料になります。
3.RFP作成に向けた要求事項のブラッシュアップ
RFIで収集した情報は、次のステップであるRFP(提案依頼書)作成の基礎となります。RFPに盛り込むべき要件や評価軸、優先順位を明確化し、ベンダーに具体的かつ現実的な提案を求められるようになります。
RFIは単なる「情報収集のための調査票」ではなく、調達の成功確率を高める重要なステップです。
得られた情報を丁寧に扱い、選定・提案依頼・契約の土台づくりに活かしていくことが求められます。
あわせてこの用語と記事をチェック