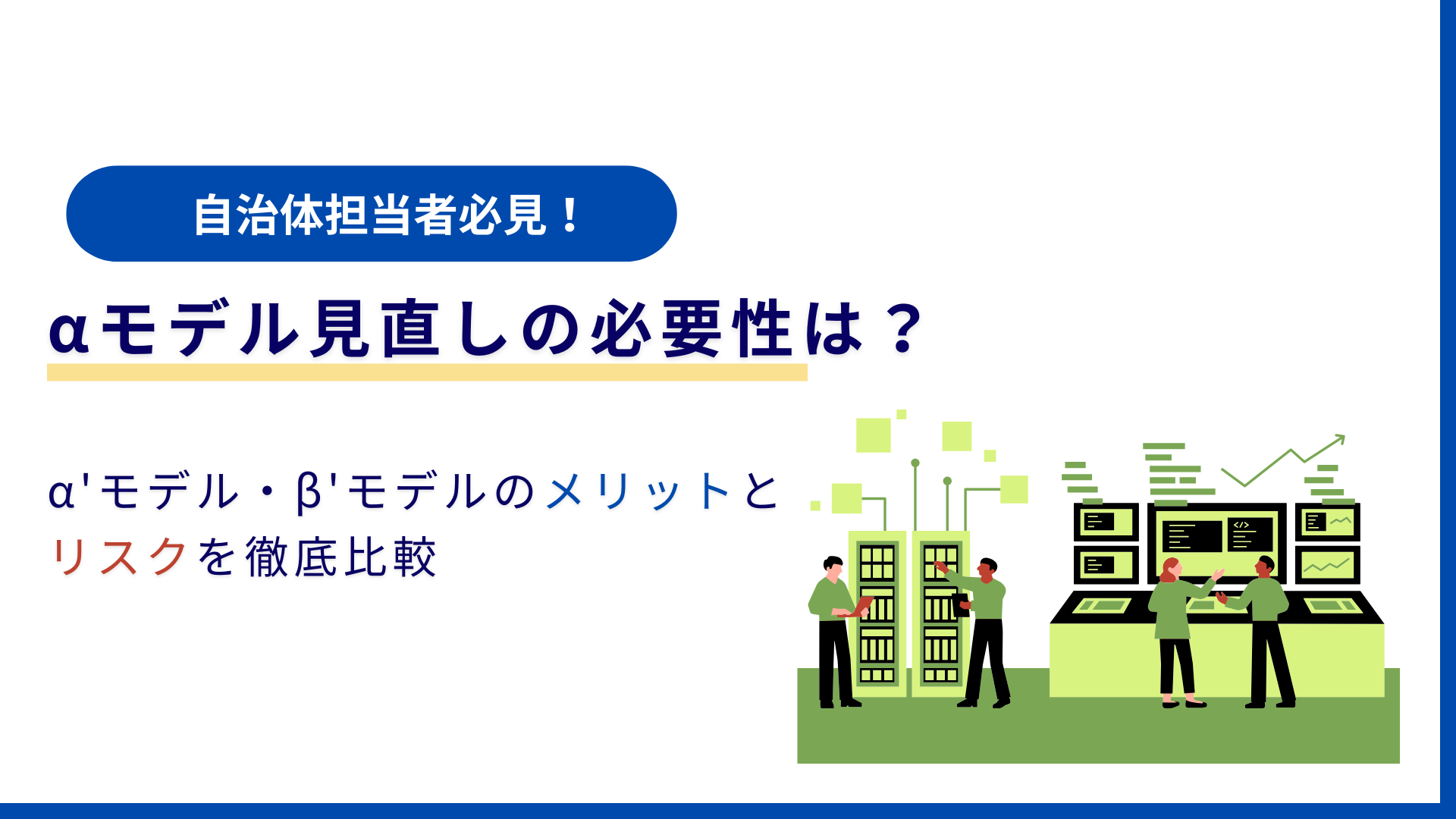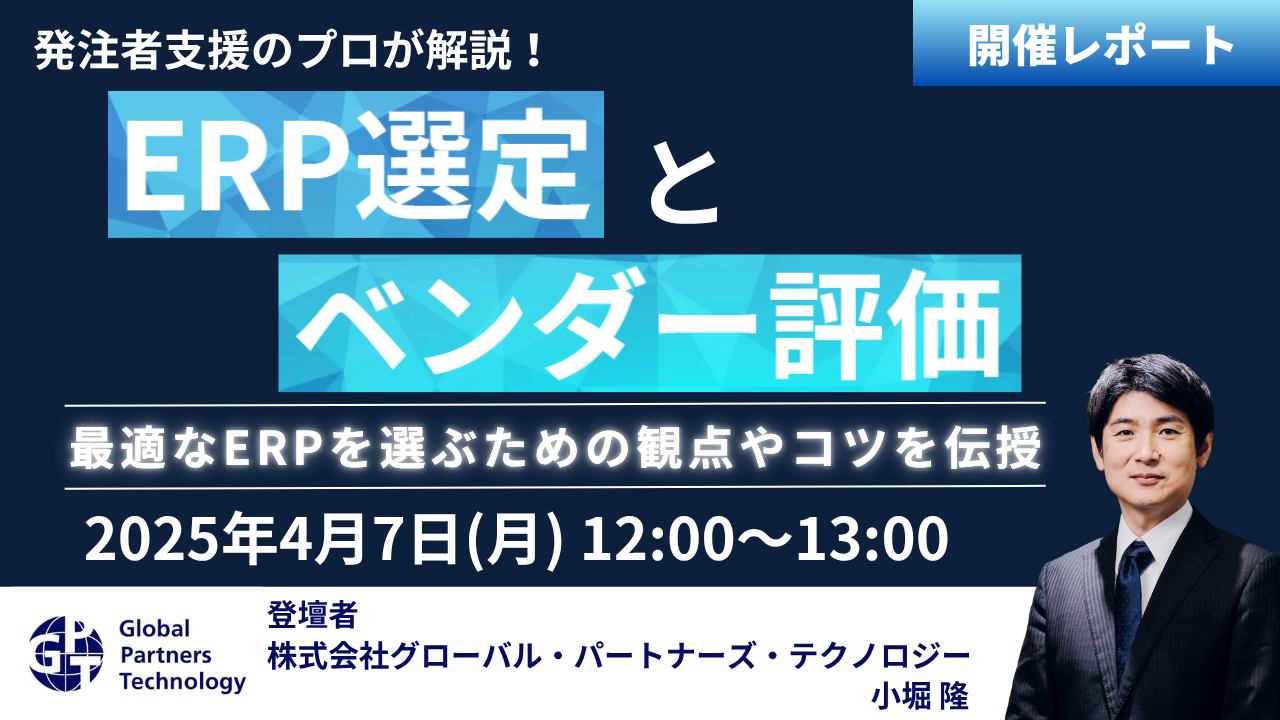RFP
RFPとは、Request For Proposal(提案依頼書)の略称です。発注先の候補となっているシステム開発会社に対して、システムの具体的な提案を依頼するために発出する文書のことです。
RFPを発出する主な目的は、「候補会社に提案書を提出してもらい、発注先のシステム開発会社を評価・決定するため」です。
RFPで発注者側の要望を明文化して候補会社に伝えることで、「システムに求める要件について発注者側と開発者側の相互理解を深める」ことも目的の1つです。
RFPに記載する事項としては、発注側の会社・事業の概要や、システム開発を発注する背景・方針(現状の業務・システムの課題、システムの導入/刷新方針、想定スケジュール)、提案してほしい事項(現状の課題を解決するためのシステム概要、開発体制・スケジュール、見積もり項目)、提案要綱(提案書のファイル形式、提案書の提出締め切り日、プレゼン実施日)などがあります。
特に候補会社が複数ある場合は、同じ内容のRFPを全候補会社に発出し、同じ様式で提出される提案書を各候補会社から受領することで、同じ基準で比較・評価がしやすくなります。
なお、RFI(Request For Information:情報提供依頼書)は、発注先候補の会社に対して会社情報や候補会社の持つ技術や製品に関する情報の提供を依頼するために発出する文書です。
RFPに基づいて提案書を出してもらいたい候補会社を絞り込むために、まずはRFIで情報収集をすることがあります。
目次
よくある質問
予算・スケジュール・成果物の精度が不十分なRFPを発行すると、発注者にどのようなリスクが生じるでしょうか?
RFP(提案依頼書)の精度が不十分なまま発行されると、ベンダーからの提案内容がばらつき、発注者が適切に比較・選定できなくなるリスクがあります。
さらに、契約後の進行においても次のような問題を招きやすくなります。
1. コスト超過のリスク
要件が曖昧なために見積りが過小または過大になり、追加費用や不透明なコスト発生につながります。
2. 納期遅延のリスク
スケジュールの前提条件が不明確だと、事前に想定していた条件と異なることにより、導入フェーズの各工程についてスケジュールや作業内容の再調整が生じる可能性が高まり、結果として納期遅延のリスクが大きくなります。
3. 品質低下のリスク
成果物の範囲や水準が定義されていない場合、期待していた成果と実際の成果が乖離し、ユーザー満足度の低下や再開発コストの発生につながります。
4. 契約交渉での不利
RFPに具体性が欠けると、契約書に反映できる条項が不十分となり、責任分担やリスク配分で発注者が不利になりやすくなります。
精度の低いRFPは「コスト超過」「納期遅延」「品質低下」「契約での不利」といったリスクを招きます。
発注者にとっては、契約前に十分な精度で要件を固めることが不可欠です。
複数の候補ベンダーからの提案を比較する際、公平かつ透明な評価基準をどう設けることが望ましいでしょうか?
ベンダー選定においては、恣意的な判断や不透明な評価が行われると、後々の契約トラブルや不信感につながります。
そのため、公平性と透明性を確保するために以下の観点で評価基準を設けることが望まれます。
1. 評価項目の明確化
機能要件・非機能要件・コスト・スケジュール・サポート体制など、評価対象とする観点を事前に明示します。
2. 重み付けの設定
各項目の重要度に応じて配点を設定します。たとえば基幹システムなら信頼性や保守性を重視するなど、業務特性に合致させることが重要です。
3. 定量評価と定性評価の併用
価格や納期は数値で比較し、提案の実現性や過去実績は評価委員による定性判断を組み合わせることでバランスを取ります。
4. 評価プロセスの可視化
評価委員会を設置し、評価結果や理由を記録に残すことで、後から説明可能な透明性を担保します。
ベンダー比較の公平性を確保するには、評価項目を明示し、重み付けを設定し、定量・定性を組み合わせて評価することが重要です。
評価プロセスを記録することで透明性も担保できます。
RFIやRFQとの使い分けをどうすれば発注プロセスの効率と品質が向上するでしょうか?
RFI・RFP・RFQはいずれも調達プロセスで用いられる文書ですが、目的が異なるため、状況に応じて選択的に活用することが重要です。
1. RFI(情報提供依頼書)の役割
市場にどのようなソリューションやベンダーが存在するかを調査する段階で活用します。
要件が固まっていない初期段階で利用することで、以降の検討を現実的かつ的確にできます。
2. RFP(提案依頼書)の役割
機能要件や非機能要件、導入目的を明確に示し、候補ベンダーに対して解決策と価格を含めた提案を求める段階で利用します。
特に公共調達ではRFPの時点で価格評価も行い、業者決定まで進むケースが一般的です。
3. RFQ(見積依頼書)の役割
仕様が固まり、価格や納期など定量条件の比較を重視する場合に用いられます。
RFPと併用するのではなく、調達方針に応じて「RFPかRFQか」を選択するイメージです。
4. 使い分けのポイント
提案内容の比較を重視するならRFP、定量条件の比較を重視するならRFQと、調達の目的に応じてどちらを用いるか判断することが効率性と品質の向上につながります。
RFIは情報収集、RFPは提案依頼、RFQは見積依頼と役割が異なります。
RFPとRFQは併用ではなく調達の目的に応じて選択するのが望ましく、使い分けが発注プロセスの効率と品質を高めます。
あわせてこの用語と記事をチェック
・【初心者編】RFPとは?RFP作成のメリットや注意点、RFIやRFQなど分かりやすく解説!