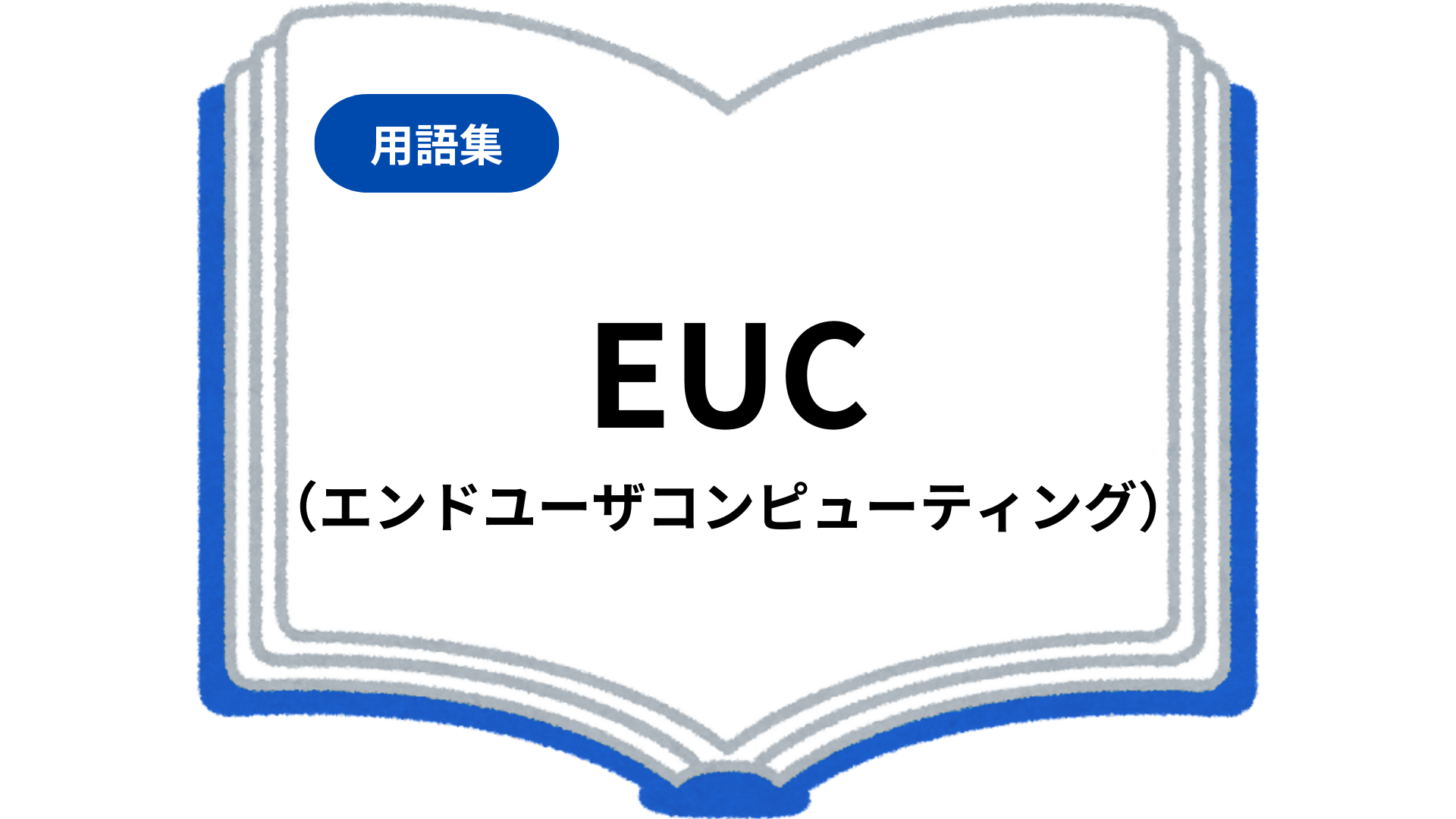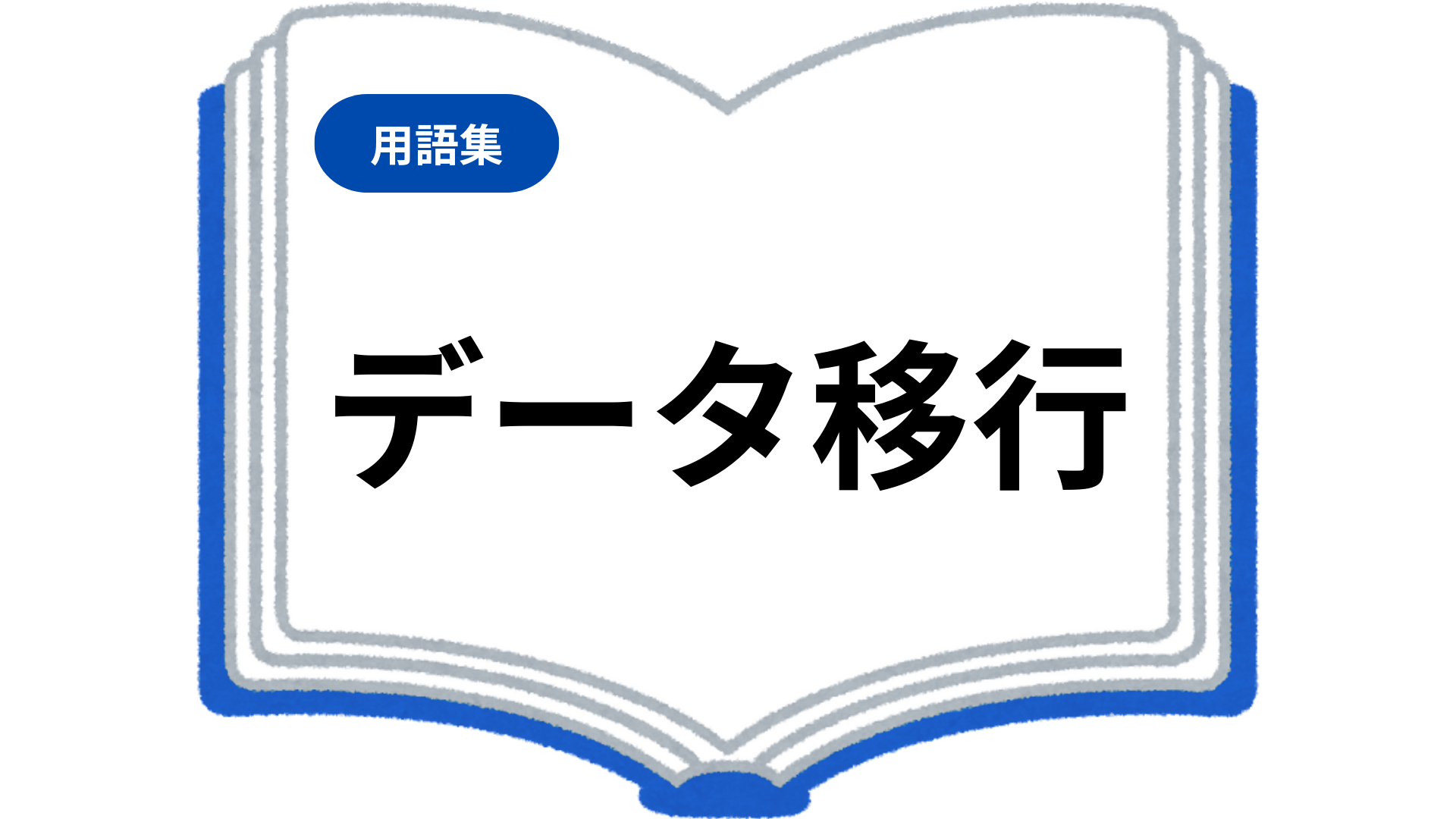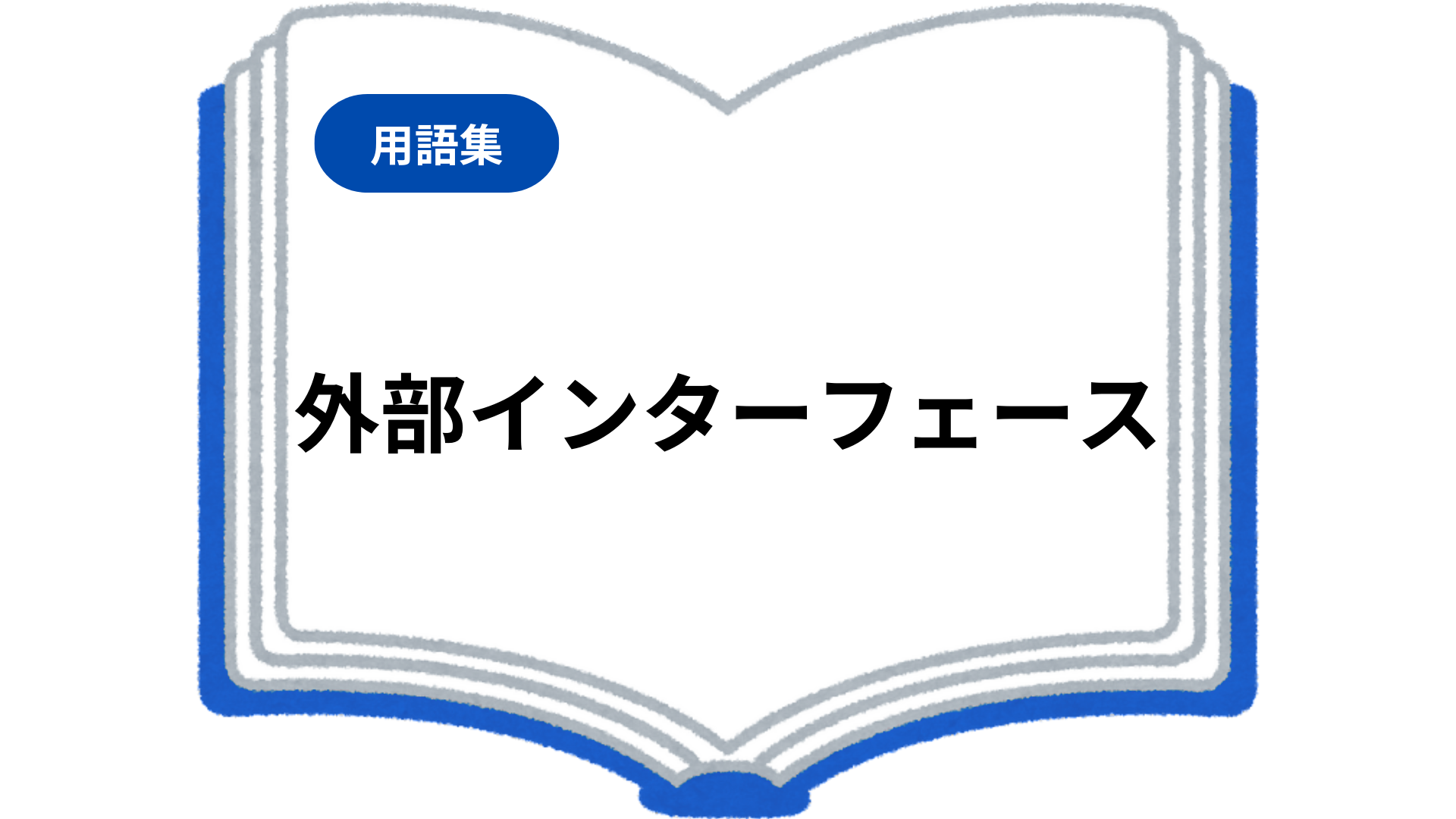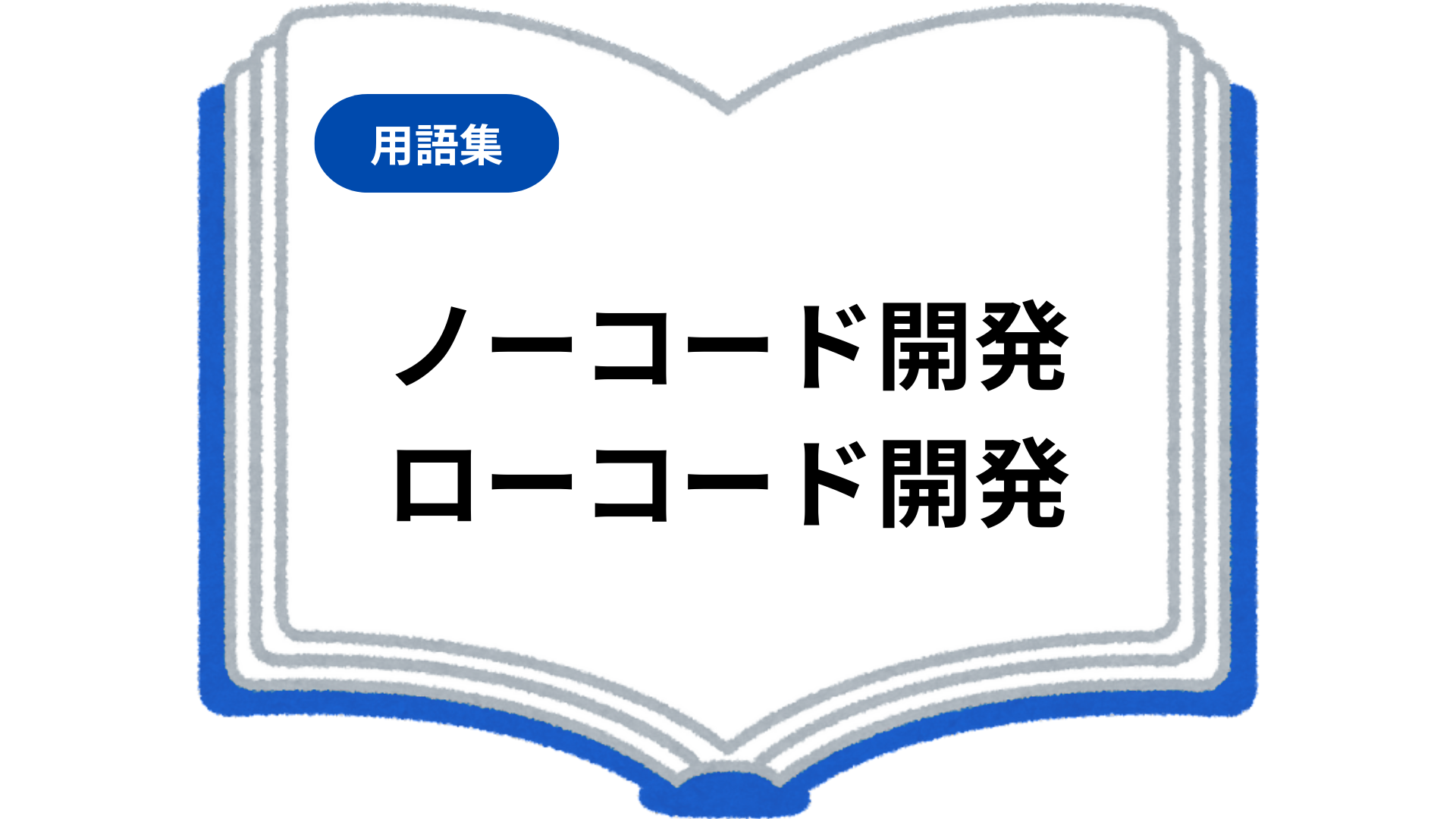
ノーコード開発、ローコード開発とは?特徴や代表的なツールについて解説
ノーコード開発とは、プログラミングを一切行わずにアプリケーションやWebサービスなどを開発する手法です。
ローコード開発とは、ごく少量のプログラミングにより、同様にアプリケーションやWebサービスを開発する手法を指します。
近年、DX推進やIT人材の不足を背景に、非エンジニアでもシステムやアプリケーションを開発できる環境のニーズが高まっています。
このような状況から、プログラミングを行わない、もしくは最小限に留める開発手法に注目が集まっています。
また、ノーコード開発やローコード開発を行うためには、特定のプラットフォームやツールを使用する必要があります。
これらのツールは、プログラミングの知識がなくても開発が可能になるよう設計されており、ノーコード製品やローコード製品と呼ばれています。
ノーコード製品やローコード製品の例は下記の通りです。
- ノーコードツール
Bubble、Glide、Adalo、STUDIOなど - ローコードツール
OutSystems、Microsoft Power Apps、Mendixなど
多くのノーコード、ローコード製品は、事前に用意されたコンポーネント(例えば、アイコンやテキストボックスなど)を組み合わせることで、ユーザーが望むアプリケーションを開発できるようになっています。
実際に開発できるものは、使用する製品によって大きく異なります。
Webアプリケーションやデータベース管理システムなど、開発できるシステムは多岐に渡ります。
ノーコード製品やローコード製品は多種多様に存在し、無償で利用できるものも多いため、実際にいくつかの製品を試してみると、これらの概念に対する理解が深まるかもしれません。
目次
よくある質問
ノーコード/ローコード開発を採用するメリットと制約は何か?
ノーコード/ローコード開発を採用することは、開発スピードやコスト効率の向上につながる一方で、拡張性やガバナンス面に制約があると言えます。
発注者はこのバランスを踏まえ、導入可否を判断することが重要です。
メリット
1.開発スピードの向上
・画面操作中心で開発できるため、短期間でプロトタイプや業務アプリを構築可能。
・変化の速い業務要件に即応しやすい。
2.コスト削減
・コーディング工数が大幅に削減されるため、開発コストが抑えられる傾向にある。
・外部エンジニアへの依存度を下げ、内製化促進にもつながる。
3.利用部門の主体的関与
・現場担当者が直接開発に関わることで、業務に即したシステムが実現しやすい。
・IT部門と業務部門の連携強化にも寄与。
制約
1. 拡張性・複雑な要件への対応
・標準機能の範囲に依存するため、大規模開発や特殊要件には適さない場合がある。
・拡張性が限定されていることから、機能追加が困難となる場合がある。
2. ベンダーロックインの可能性
・特定ツールに依存した場合、将来的な移行や統合に制約が生じる。
3. ガバナンス・セキュリティ管理
・利用部門主体の開発が拡大すると、セキュリティ要件や社内標準から逸脱する恐れがある。
・システム全体の品質保証や保守責任をどう担保するかが課題となる。
ノーコード/ローコード開発は、迅速なシステム構築とコスト効率の向上というメリットがある一方で、拡張性や統制面の課題を伴う可能性があります。
発注者は、対象業務やプロジェクト規模を踏まえて「どこまでをノーコード/ローコードで対応し、どこからは従来開発を行うか」を見極めることが重要です。
既存のパッケージやスクラッチ開発との比較で、どのような観点から選定すべきか?
ノーコード/ローコード開発を選定する際は、開発スピード・コスト・柔軟性・保守性といった観点を、パッケージ導入やスクラッチ開発と比較検討することが適切です。
発注者は自社の要件や将来の拡張性を踏まえて最適な方式を見極めることが求められます。
比較の観点
1. 開発スピードとコスト
・ノーコード/ローコードは迅速な開発とコスト削減が可能。
・パッケージは初期導入が比較的早いが、カスタマイズが増えるとコストが増大。
・スクラッチは要件に応じた自由度が高い一方で、開発期間・コストが大きくなる傾向。
2. 業務要件との適合度
・パッケージは標準機能の範囲で要件が合致すれば効率的。
・スクラッチは特殊要件や独自業務に柔軟に対応可能。
・ノーコード/ローコードは標準機能を前提に、比較的シンプルな業務に適する。
3. 拡張性と将来の対応力
・スクラッチは最も柔軟で拡張性が高い。
・パッケージはベンダーのロードマップに依存。
・ノーコード/ローコードはツールの機能拡張範囲に制約がある。
4. 運用・保守の容易さ
・パッケージはベンダーサポートに依存しやすい。
・スクラッチは自社やベンダーに知見が必要で、保守体制の確保が課題。
・ノーコード/ローコードは利用部門でも修正可能だが、ガバナンスが弱い場合リスクとなる。
比較の際は、「スピード・コストを優先するのか」「業務に合わせた柔軟性を重視するのか」「長期的な運用・保守を見据えるのか」という観点から評価することが重要です。
発注者はベンダー任せにせず、各方式の長短を踏まえて意思決定することが望ましいでしょう。
ベンダーや利用部門に開発を任せる場合、どのようなリスク管理が必要か?
ベンダーや利用部門にノーコード/ローコード開発を任せる場合には、品質保証・ガバナンス・セキュリティ確保の観点からリスク管理を徹底することが重要です。
発注者は「誰が」「どの範囲を」「どのルールで」開発するのかを明確化し、統制を維持することが求められます。
主なリスクと管理のポイント
1. 品質のばらつき
・主なリスク:利用部門主導では、標準化されていない独自仕様や属人的な設計が生じやすい。
・管理策:開発ガイドラインの策定、レビュー体制の構築、品質基準の明文化。
2. セキュリティ・コンプライアンス違反
・主なリスク:データ取扱いや認証機能が適切に実装されず、情報漏洩リスクが高まる。
・管理策:IT部門やCIOによるセキュリティチェック、アクセス権限管理の統制。
3. システム統合の難航
・主なリスク:部門単位で開発したシステムが全社アーキテクチャと整合せず、後の統合にコストが発生。
・管理策:全社的なシステム方針との整合性確認、共通APIやデータ基盤の活用。
4. ベンダーロックイン
・主なリスク:特定ベンダーやツールに依存し、将来の移行が困難となる可能性。
・管理策:契約段階でのデータ移行性の確認、オープン規格準拠の利用を優先。
ベンダーや利用部門に開発を委ねる場合でも、発注者が全体統制の責任を持ち、品質・セキュリティ・統合性を担保する枠組みを構築することが不可欠です。
リスクを未然に管理することで、スピードと柔軟性のメリットを享受しつつ、全社最適のシステム運用につなげることが可能となります。
ノーコード/ローコードで開発したシステムの運用や保守で注意すべき点は何か?
ノーコード/ローコードで開発したシステムの運用や保守では、属人化防止・セキュリティ管理・ツール依存リスクへの対応が重要です。
発注者は短期的な利便性だけでなく、中長期的な安定運用を見据えて統制を図ることが望ましいです。
注意すべき主なポイント
1. 属人化のリスク
・利用部門主導で開発したシステムは、担当者の異動や退職により保守が困難になる可能性がある。
・対応策:設計書や運用手順書の標準化、ナレッジ共有体制の確立。
2. セキュリティとガバナンス
・権限管理やデータ保護の統制が不十分なまま運用すると、情報漏洩や不正利用につながる。
・対応策:IT部門による定期的なセキュリティレビュー、アクセス権限の適切な設定。
3. ツール依存(ベンダーロックイン)
・特定のプラットフォームに依存すると、機能拡張や他システムとの連携に制約が生じる。
・対応策:導入時にエクスポート機能や移行性を確認、将来の代替手段を検討。
4. 運用・保守コストの予測困難性
・開発段階では低コストでも、運用開始後に利用料や追加機能の課金が増加するケースがある。
・対応策:ライセンス体系や将来の拡張費用を契約時点で明確に把握。
ノーコード/ローコード開発は迅速性や柔軟性に優れますが、運用・保守段階では「統制」「セキュリティ」「将来の拡張性」を発注者が主体的に管理することが不可欠です。
短期的な利便性と長期的な安定性の両立を意識することが望ましいです。
________________________________________
あわせてこの用語と記事をチェック