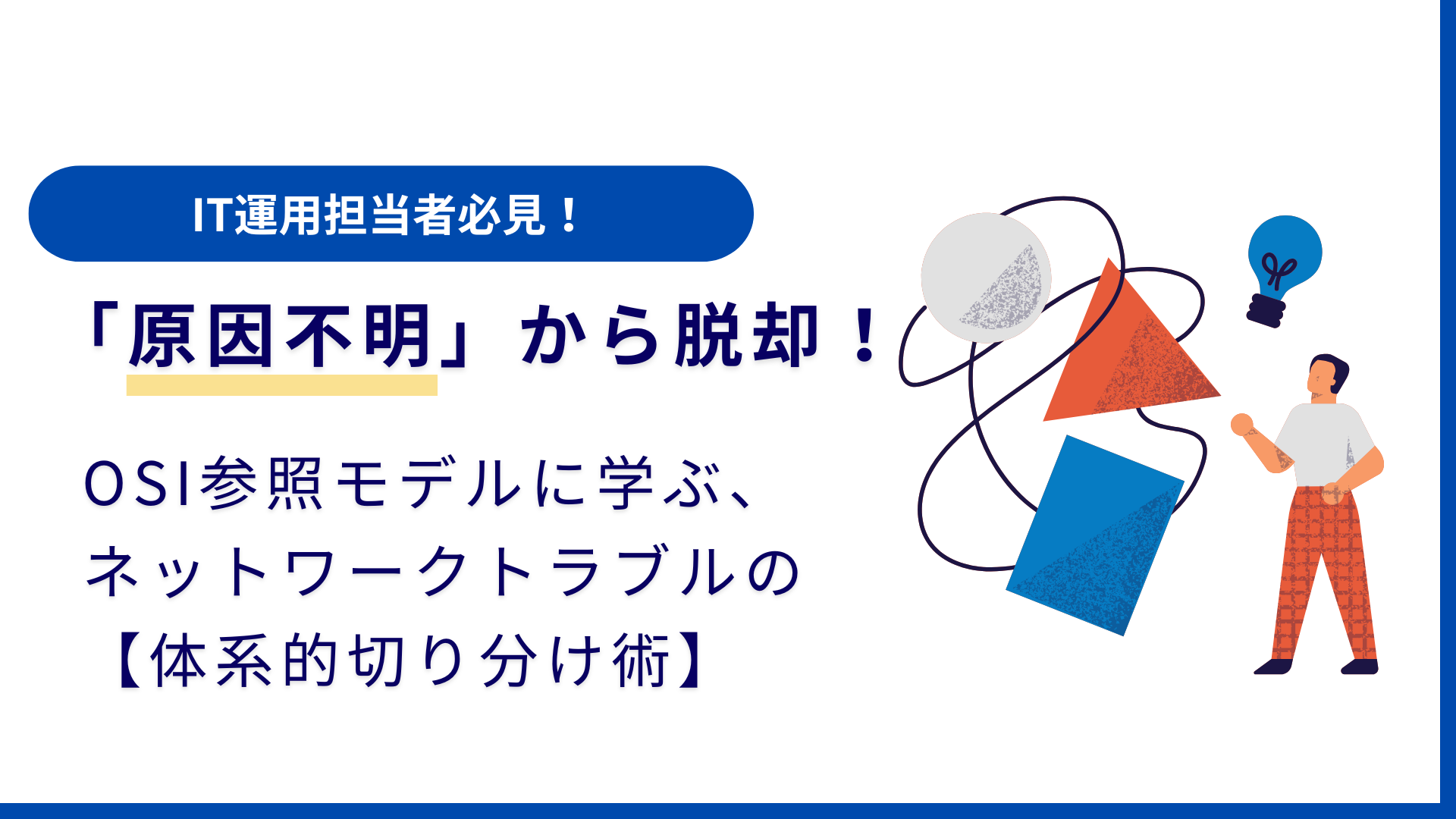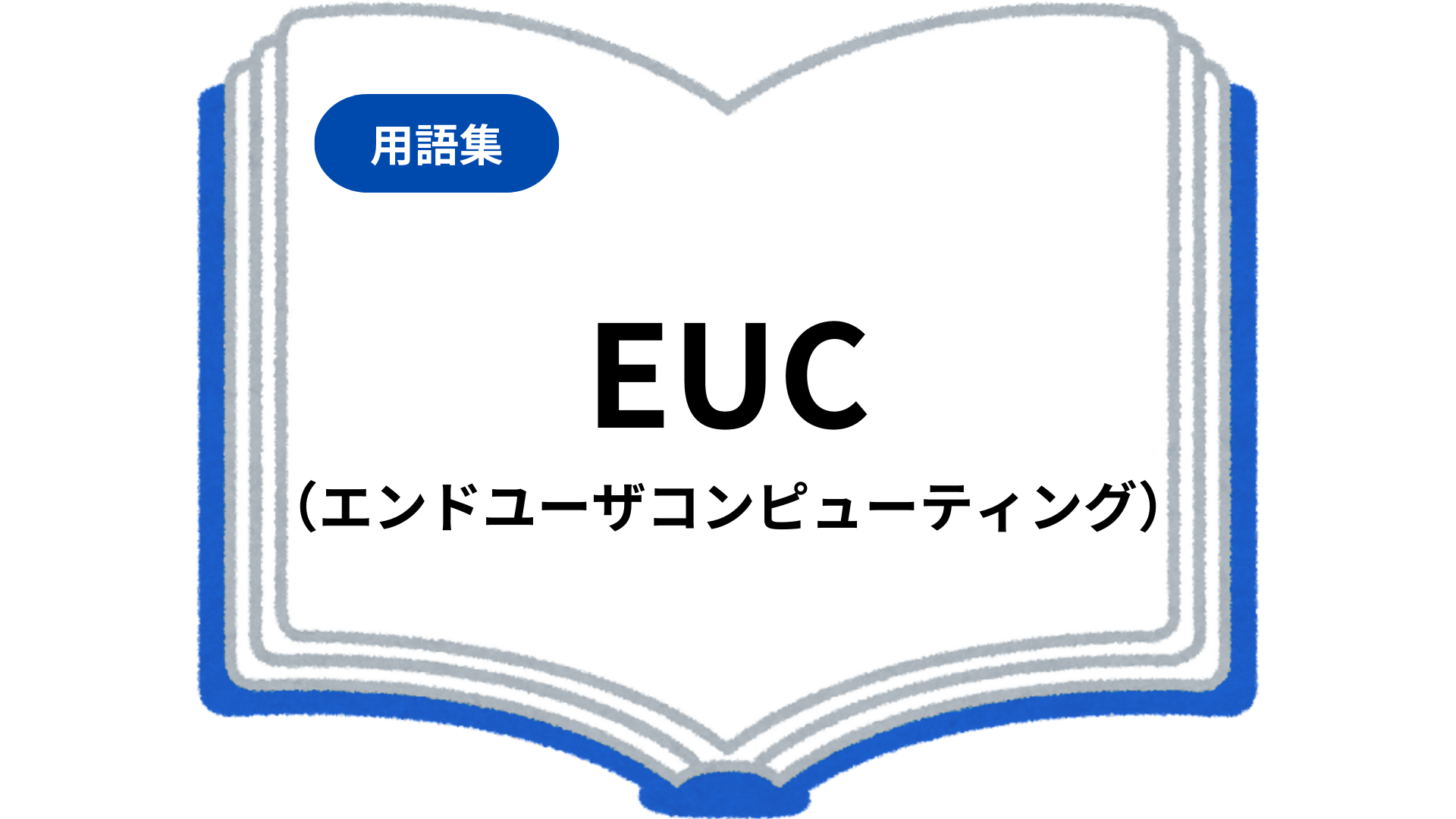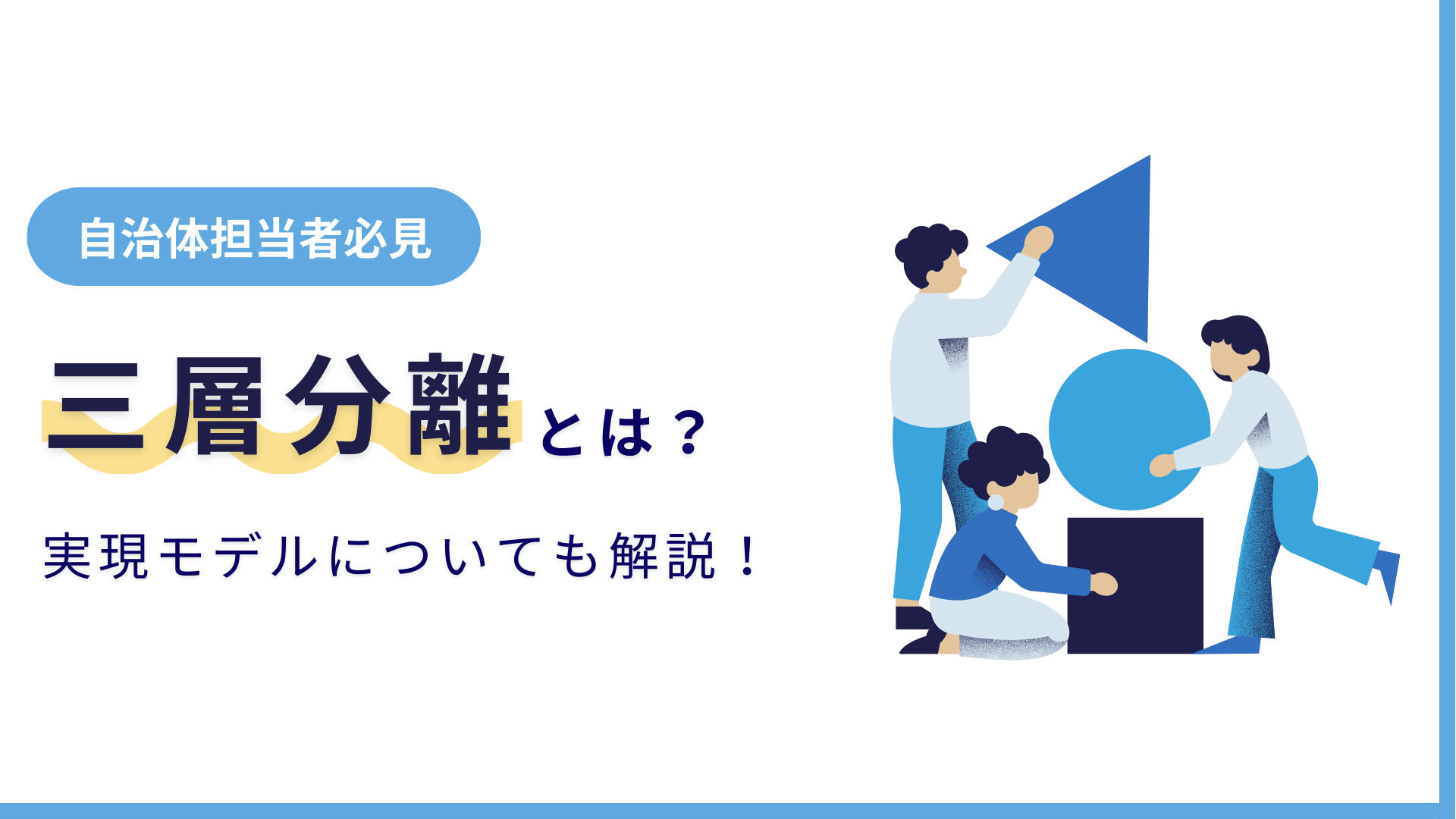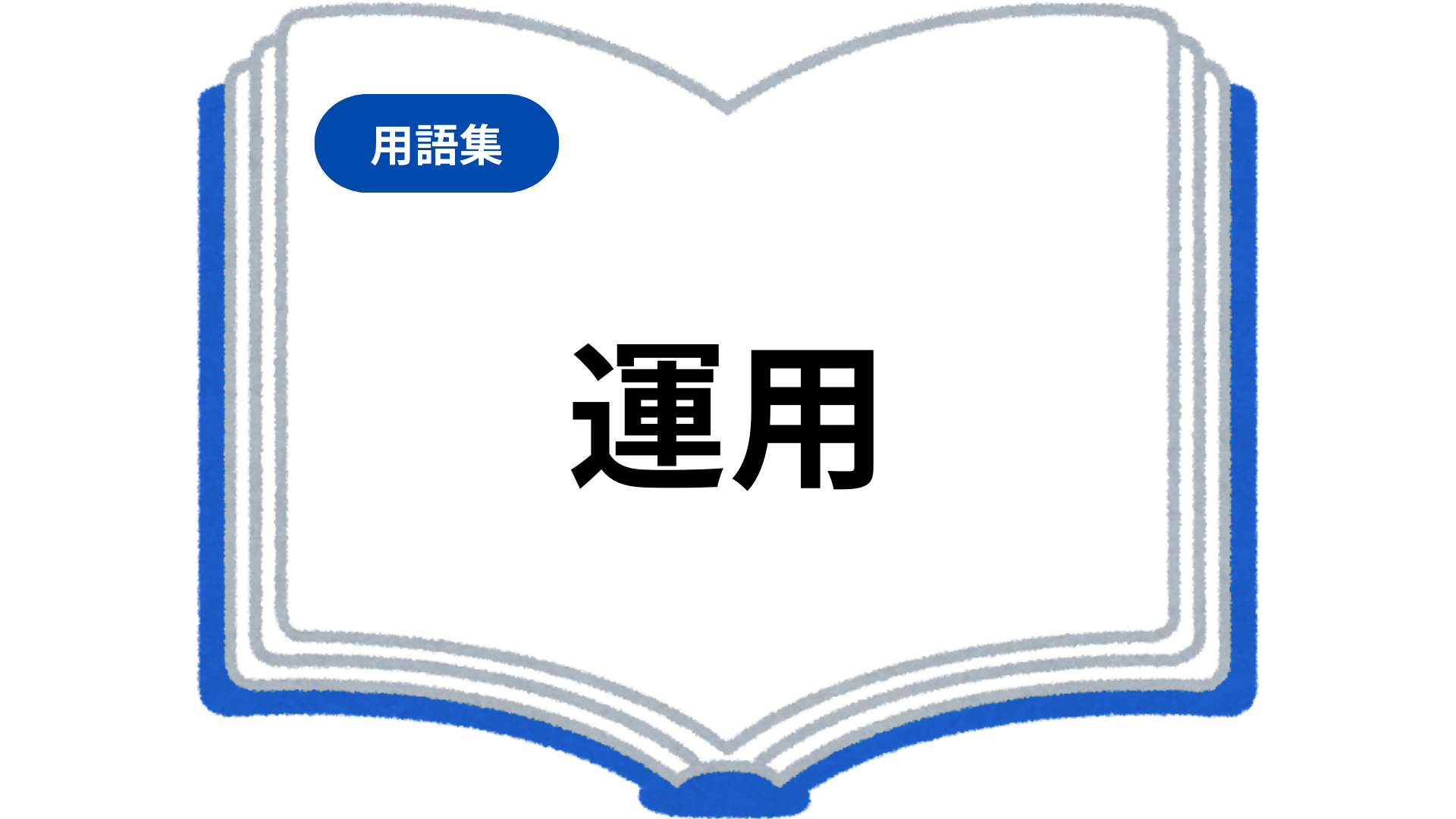
運用
運用とは、システムの運用とは完成したシステムを実際の業務に使うこと、そして、そのためにシステムの稼働状態を正常に維持することです。
「開発3割、運用7割」と言われるほど、システムの運用には「ヒト」と「カネ」と「時間」がかかりますが、運用しなければシステムからのベネフィットを得ることができません。
システム開発のプロジェクトが完了し、いよいよ本稼働という時から運用計画書に基づいた運用は始まります。運用計画については、次のような項目を検討します。
・監視業務:システムの稼働状況を監視する(稼働状況監視、性能監視、セキュリティ監視、データ監視など)
・システム稼働維持業務:システム計画通り稼働させる(バッチ処理の計画/実行、データバックアップ、システム停止/始動、ユーザー管理など)
・システム構成管理業務:システムを構成する要素を管理する(ネットワーク、ハードウェア、OS,ソフトウェア、データベースの型式、バージョン、ライセンスなど)
・ユーザーサポート業務:ユーザーが円滑にシステムを利用できるように支援する(ヘルプデスク、操作教育など)、等
システムの運用と混同しやすい用語に「保守」がありますが、「運用=システムに手を入れずに正常状況を維持すること」、「保守=システムに手を入れて異常状況を是正すること」という区別ができます。
また「業務運用」という言葉がありますが、これはシステムの運用を含めて業務をどう進めるかという視点に立ったものです。
なお、システムの運用が社内担当者では行えない場合、外部にその業務を委託することになります。その際、運用が適切に行われているかどうかを判断する考え方として「SLA(サービスレベル合意書)」があります。
また、運用を委託された受注者は「運用報告書」を作成し、それを発注者側に提出して定期報告会を開催します。これによって、発注者側はシステムの稼働状況が認識できるだけではなく、システムの改善計画や将来の導入計画、および、それに関する予算立案を進めることができるのです。
このように「運用」はシステム導入後の安定稼働に欠かせない業務と言えます。
よくある質問
システム運用における発注者の主な役割と責任は何ですか?
システム運用における発注者の主な役割と責任は、運用計画の策定支援、運用品質の監督、障害発生時の対応調整、及び関係者間の円滑なコミュニケーションの確保にあります。
発注者の主な役割と責任
1. 運用計画の承認と支援
運用体制や手順、監視項目などの計画策定に参画し、適切な内容となっているかを確認・承認します。
2. 運用品質の監督
運用状況の報告を定期的に受け、品質基準やSLAの遵守状況を監督し、必要に応じて改善指示を行います。
3. 障害対応の調整と管理
障害発生時には迅速な情報共有を促進し、ベンダーや運用担当者との連携を図って復旧活動を支援します。
4. 関係者間の連携促進
利用部門、ベンダー、運用チーム間のコミュニケーションを円滑にするための調整役を担います。
5. 継続的な運用改善の推進
運用データやインシデント分析を基に、運用プロセスの見直しや改善提案を推進します。
発注者はこれらの役割を果たすことで、システム運用の安定と効率化、さらには事業継続性の確保に貢献することが求められます。
運用フェーズで発注者が特に注意すべきリスクや課題は何ですか?
運用フェーズにおいて発注者が注意すべきリスクや課題は、システムの安定稼働維持に関わる障害対応の遅延、運用コストの増大、情報セキュリティの脆弱性、及び利用者の適切なサポート不足などが挙げられます。
注意すべき主なリスク・課題
1. 障害対応の遅延と影響拡大
障害発生時の初動対応や情報共有が遅れると、業務停止や信頼失墜のリスクが高まります。
2. 運用コストの管理不足
運用体制やツールの適切な見直しが行われない場合、不要なコスト増加や非効率な運用が継続される恐れがあります。
3. 情報セキュリティリスクの増大
アクセス管理の不備や脆弱性対応の遅れにより、情報漏洩や不正アクセスの危険性が高まります。
4. 利用者サポートの不備
利用者の問い合わせやトラブル対応が不十分だと、業務効率の低下やシステム利用の抵抗感が生じます。
5. 運用改善の停滞
運用状況の定期的な評価と改善活動が行われない場合、継続的な品質向上が困難になります。
これらのリスクや課題を認識し、発注者は運用体制の適切な監督と改善推進を通じて、システムの安定稼働と効率的な運用を確保する必要があります。
運用改善のために発注者が活用すべき指標や評価方法はありますか?
運用改善を効果的に進めるため、発注者はシステム稼働率や障害発生件数、対応時間、利用者満足度などの指標を定期的に評価し、課題抽出と改善策立案に活用すべきです。
活用すべき主な指標
1. システム稼働率(可用性)
システムが計画通り稼働している時間の割合を測定し、安定性を評価します。
2. 障害発生件数および影響度
発生した障害の頻度と業務への影響を把握し、問題点の重点的な改善に役立てます。
3. 障害対応時間(MTTR:平均復旧時間)
障害発生から復旧までの平均時間を計測し、対応体制の効率性を評価します。
4. 変更管理の成功率
運用中の変更や修正が計画通りに完了し、問題を引き起こしていないかを確認します。
5. 利用者満足度
利用部門からのフィードバックやアンケート結果を収集し、サービス品質の主観的評価を行います。
評価方法のポイント
・指標を定量的に収集し、定期的な報告とレビューの場で共有する。
・指標の傾向分析を通じて長期的な運用課題を把握し、改善活動の優先順位を設定する。
・利用者の声を重視し、定性的な評価と合わせて全体最適を目指す。
これらの指標と評価方法を活用し、発注者は運用品質の継続的な改善を推進し、安定的かつ効率的なシステム運用を実現することが求められます。
・保守とは