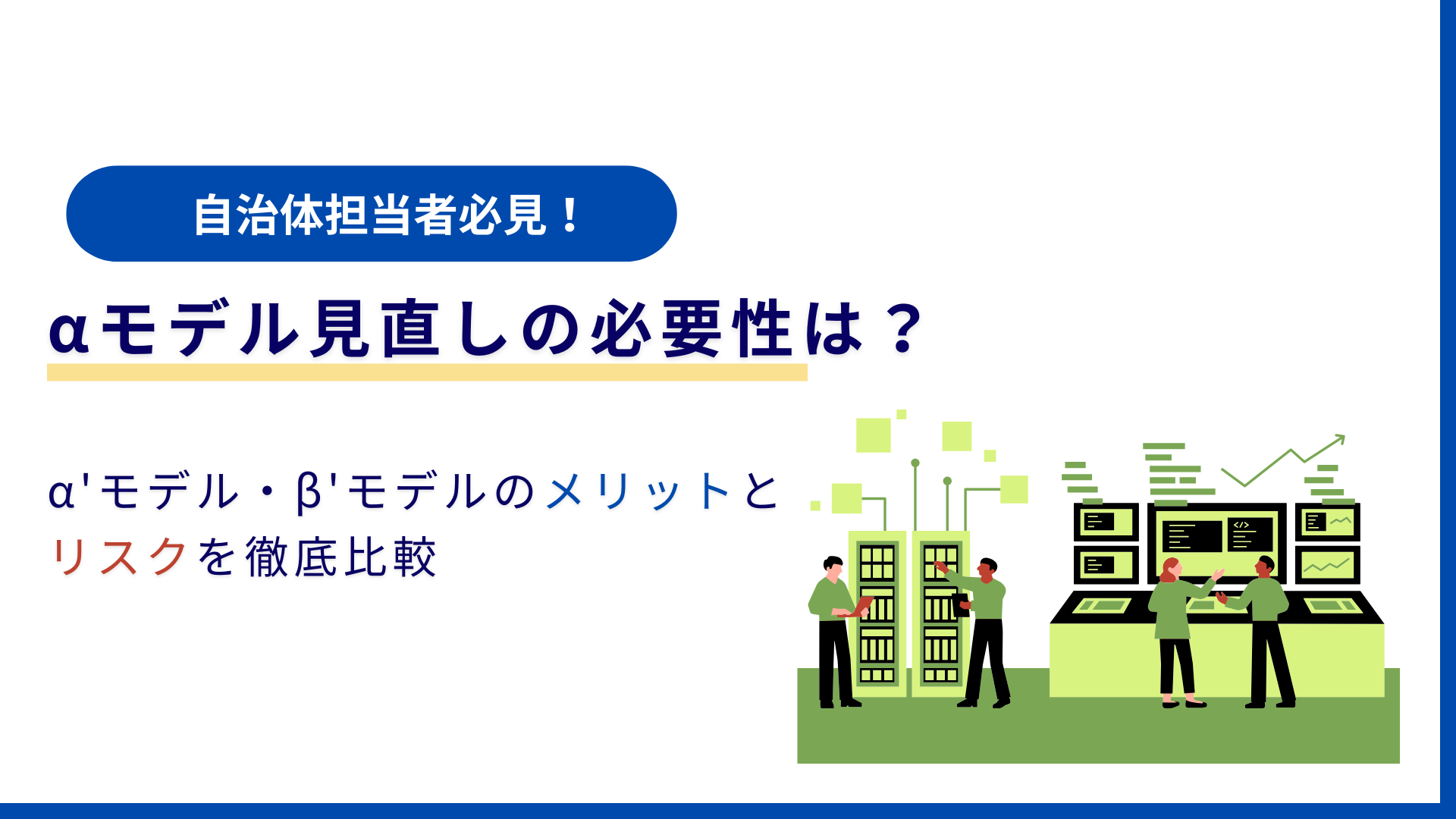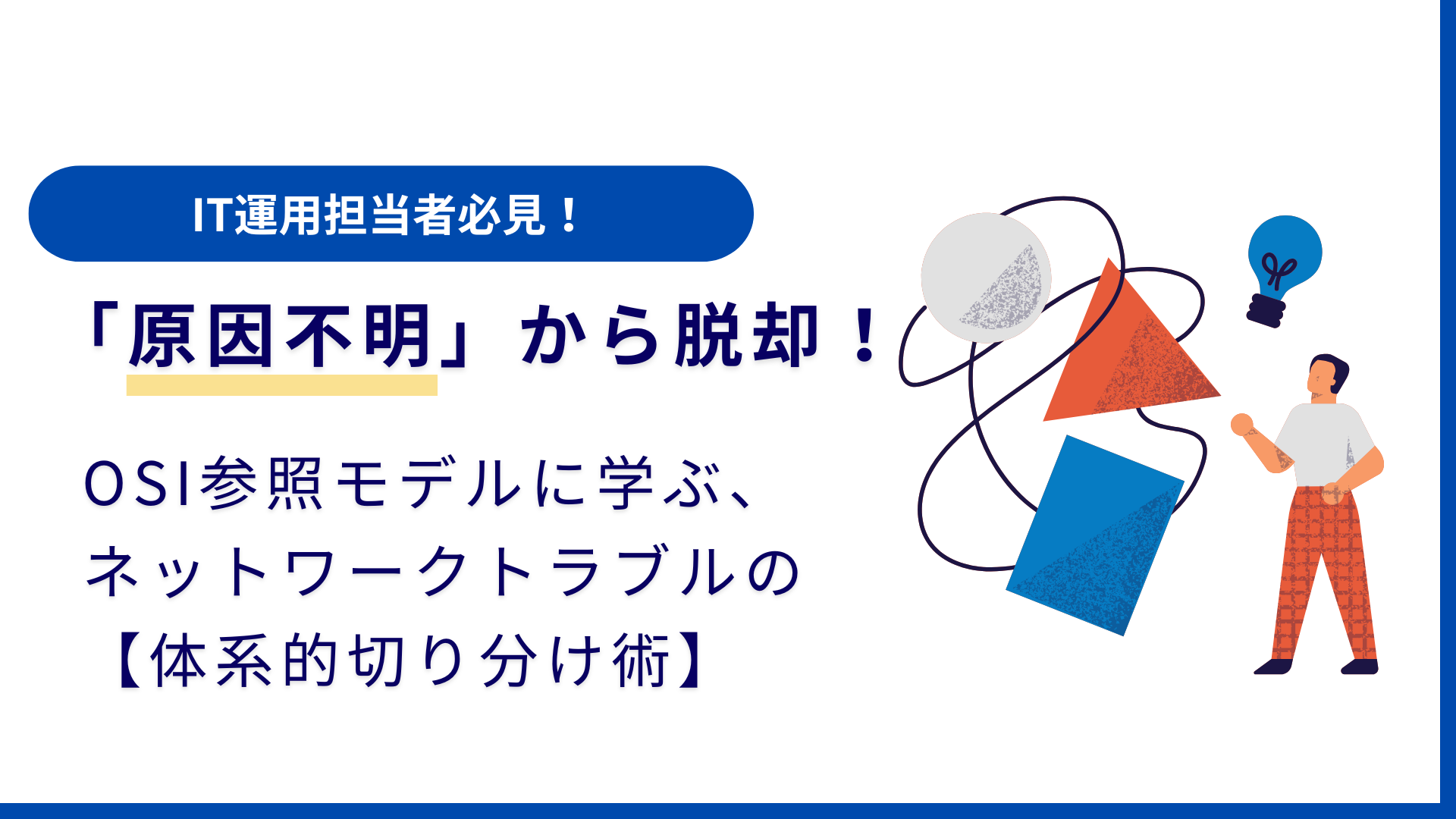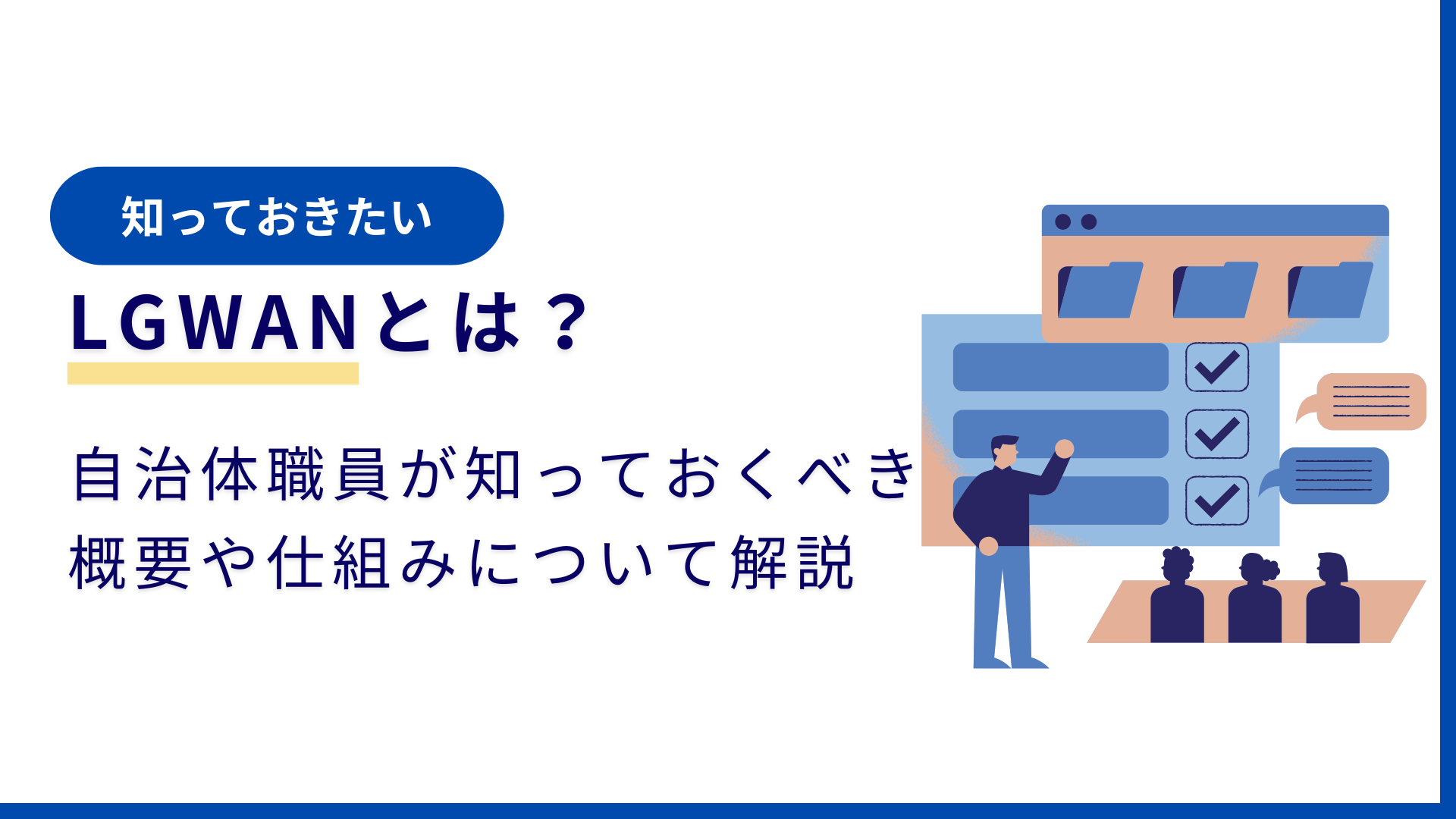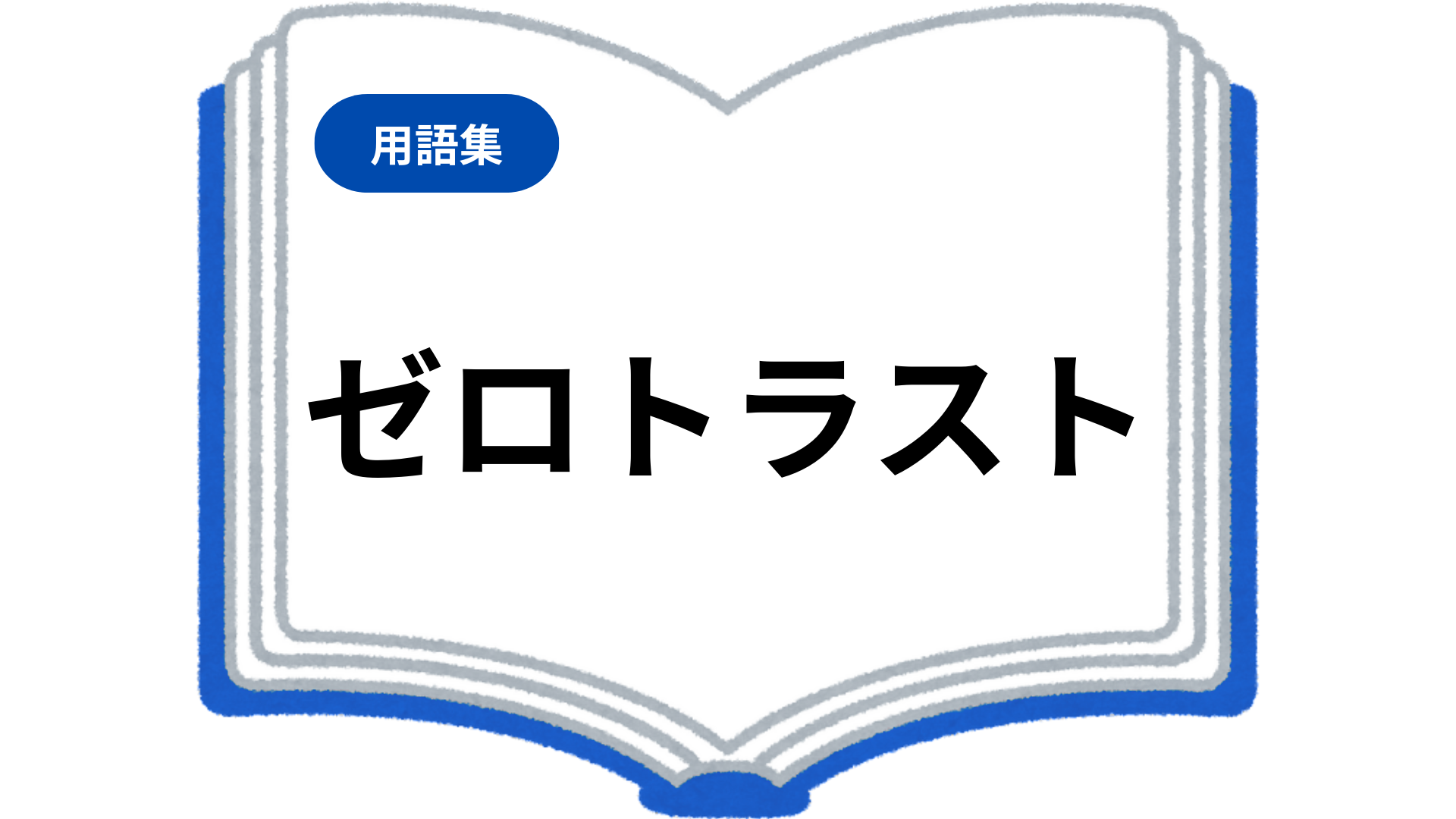
ゼロトラストとは?特徴や仕組み、境界型セキュリティとの違いについて解説
ゼロトラストとは、従来の内部ネットワークを安全とし、外部ネットワークを危険とする考えに基づいた「境界型セキュリティモデル」から、ネットワークの内部・外部に関わらず、すべてのアクセスを「信頼せず、常に検証する」という考え方に基づいたセキュリティモデルです。
従来の境界型セキュリティモデルは、ネットワークの内部と外部に明確な境界を設定し、外部からの攻撃を防ぐことに重点を置いていました。
しかし、クラウドサービスやリモートワークの普及に伴いネットワークの境界が曖昧になる環境が増えてきました。
サイバー攻撃の高度化や複雑化により内部への侵入を完全に防ぐことは難しく、こうした環境下においては、外部からの攻撃を防ぐだけでは十分な対策とはなりません。
仮に攻撃者が内部に侵入しても、その活動を制限し、被害を最小限に抑えるような、内部からの脅威にも対処する必要があります。
ゼロトラストは、一度内部に侵入されてしまうと攻撃者が自由に動き回れるという、従来の境界型セキュリティモデルが抱える脆弱性を克服し、企業や組織のネットワークにおいて高いセキュリティの維持を可能とします。
ゼロトラストを構成する主要な要素には、以下のようなものがあります。
- デバイスのセキュリティ
すべてのデバイスが信頼できることを保証するため、接続前にデバイスの状態を検証し、セキュリティが確保されたデバイスのみアクセスを許可します。これにより、不正デバイスからの攻撃を防ぎます。 - ネットワークのセグメンテーション
ネットワークを細かく分割し、必要最小限のアクセスのみを許可します。これにより、攻撃者に侵入された場合でも、攻撃が他のセグメントに広がるリスクを軽減します。 - IDとアクセス管理(IAM)
ユーザーやデバイスのIDを厳格に管理し、すべてのアクセスを検証します。多要素認証(MFA)を用いて、信頼性を高め、不正アクセスを防止します。 - データ保護
機密データへのアクセスを厳しく制限し、暗号化を実施します。これにより、データが不正に取得された場合でも、その内容が保護されます。 - 継続的な監視と分析
すべてのトラフィックとアクセスを常時監視し、異常な活動や潜在的な脅威をリアルタイムで検出します。これにより、迅速な対応が可能となり、セキュリティの強化につながります。
また、「ゼロトラスト」と似ている用語で「ゼロトラストアーキテクチャ」というものがあります。
2つの用語は密接に関連していますが、厳密には異なる概念となります。
- ゼロトラスト
「何も信頼せず、常に検証する」という基本的な考え方や原則を指します。 - ゼロトラストアーキテクチャ
ゼロトラストの考え方を企業や組織の中で実現するための、具体的な設計や実装方法を指します。
ゼロトラストは、現代の複雑なIT環境において非常に重要なセキュリティモデルです。
従来の境界型セキュリティでは対応しきれない内部脅威にも対処できるため、クラウドサービスやリモートワークの普及に伴い、ゼロトラストの重要性はますます高まっています。
ゼロトラストについては、しばしば「単一の製品や技術」として誤解されることがありますが、実際には複数の技術とポリシーを組み合わせた考え方です。
そのため、技術的な対策やツールの導入に加え、組織全体のセキュリティポリシーや文化として根付かせる必要があります。
よくある質問
ゼロトラストを導入する際に発注者が考慮すべきポイントは?
発注者がゼロトラスト戦略を検討する際は、自社の現状分析、段階的な実装計画、技術的適合性、組織体制の整備、そして継続的な運用評価を重点的に考慮することが重要です。
発注者が考慮すべき主なポイント
1.現状のセキュリティ環境と課題の把握
自社の既存インフラや運用状況、リスク要因を正確に評価し、ゼロトラストの導入効果を見極めます。
2.段階的かつ現実的な実装計画の策定
全面的な一括導入ではなく、重要度や優先度の高い領域から段階的に適用範囲を拡大する計画が望ましいです。
3.技術選定の適合性評価
多要素認証、アクセス制御、ネットワーク分離などの技術が既存システムや運用体制と適合するかを検証します。
4.組織・運用体制の整備
セキュリティポリシーの見直し、運用担当者の役割明確化、教育・啓発の実施を行い、運用基盤を強化します。
5.継続的な監視・評価体制の確立
導入後も効果を継続的に監視し、脅威環境の変化に対応できる柔軟な改善体制を整備します。
これらのポイントを踏まえ、発注者は自社に最適なゼロトラスト戦略を構築し、実効性の高いセキュリティ強化を目指すことが求められます。
ゼロトラスト導入の課題やリスク、発注者が注意すべき点は?
ゼロトラスト戦略の導入に際しては、技術的複雑性の高さ、既存環境との整合性、運用体制の変革、コスト増加などの課題やリスクが存在し、発注者はこれらに十分配慮する必要があります。
主な課題・リスク
1. 技術的複雑性と統合の難しさ
多様な認証・アクセス制御技術を組み合わせるため、既存システムとの連携や統合が困難となる場合があります。
2. 既存環境との互換性問題
古いシステムや非対応機器が存在すると、全面的な適用に障壁が生じることがあります。
3. 運用体制・文化の変革
従来の境界防御型からの移行により、運用プロセスや担当者の役割、社内意識の変化が求められます。
4. 導入および運用コストの増加
新たな技術導入や運用監視体制の整備により、初期費用およびランニングコストが増加することがあります。
5. 段階的な導入計画の必要性
全面的な一括導入はリスクが高いため、計画的かつ段階的な実施が望まれますが、それに伴うスケジュール管理も課題となります。
発注者が注意すべき点
・導入範囲や優先順位の明確化
・ベンダー選定時の技術・運用支援能力の評価
・組織内教育や変革支援の推進
・導入効果とコストのバランス検討
・継続的な評価・改善体制の確立
これらを踏まえ、発注者はゼロトラスト導入におけるリスク管理と効果的な推進体制の構築に注力することが求められます。
ゼロトラストを実現するためのベンダー選定や運用管理で重視すべき観点は?
ゼロトラスト実現に向けたベンダー選定および運用管理では、技術的な適合性、運用支援体制の充実、セキュリティポリシーの柔軟性、そして継続的な改善能力を重視することが重要です。
ベンダー選定で重視すべき観点
1.技術的対応力と製品の適合性
多要素認証、アクセス制御、マイクロセグメンテーションなど、ゼロトラストの主要技術を提供し、自社環境に適合できるかを確認します。
2.運用支援体制の充実
導入後の運用支援や障害対応、トレーニング提供が十分かを評価し、長期的なパートナーシップを見据えます。
3.セキュリティポリシーの柔軟性
自社のセキュリティ要件や規制に対応可能で、ポリシー変更に柔軟に対応できる製品・サービスかを検討します。
4.実績と信頼性
同業種や類似規模の企業での導入実績、ベンダーの信頼性や評価を参考に選定します。
運用管理で重視すべき観点
1.ポリシー管理と自動化
アクセス制御や認証ポリシーの一元管理と自動適用により、運用負荷の軽減とセキュリティの均一化を図ります。
2.継続的な監視と評価
セキュリティイベントやアクセスログを継続的に監視し、異常検知や改善点の抽出を行います。
3.運用体制の明確化と教育
運用担当者の役割分担や対応フローを明確化し、定期的な教育・訓練を実施することが必要です。
4.ベンダーとの連携強化
トラブル時の迅速な対応やアップデート情報の共有など、密なコミュニケーション体制を構築します。
これらの観点を踏まえ、発注者はベンダー選定から運用まで一貫した品質と信頼性を確保し、ゼロトラストの効果的な実現を目指すことが重要です。
あわせてこの用語と記事をチェック