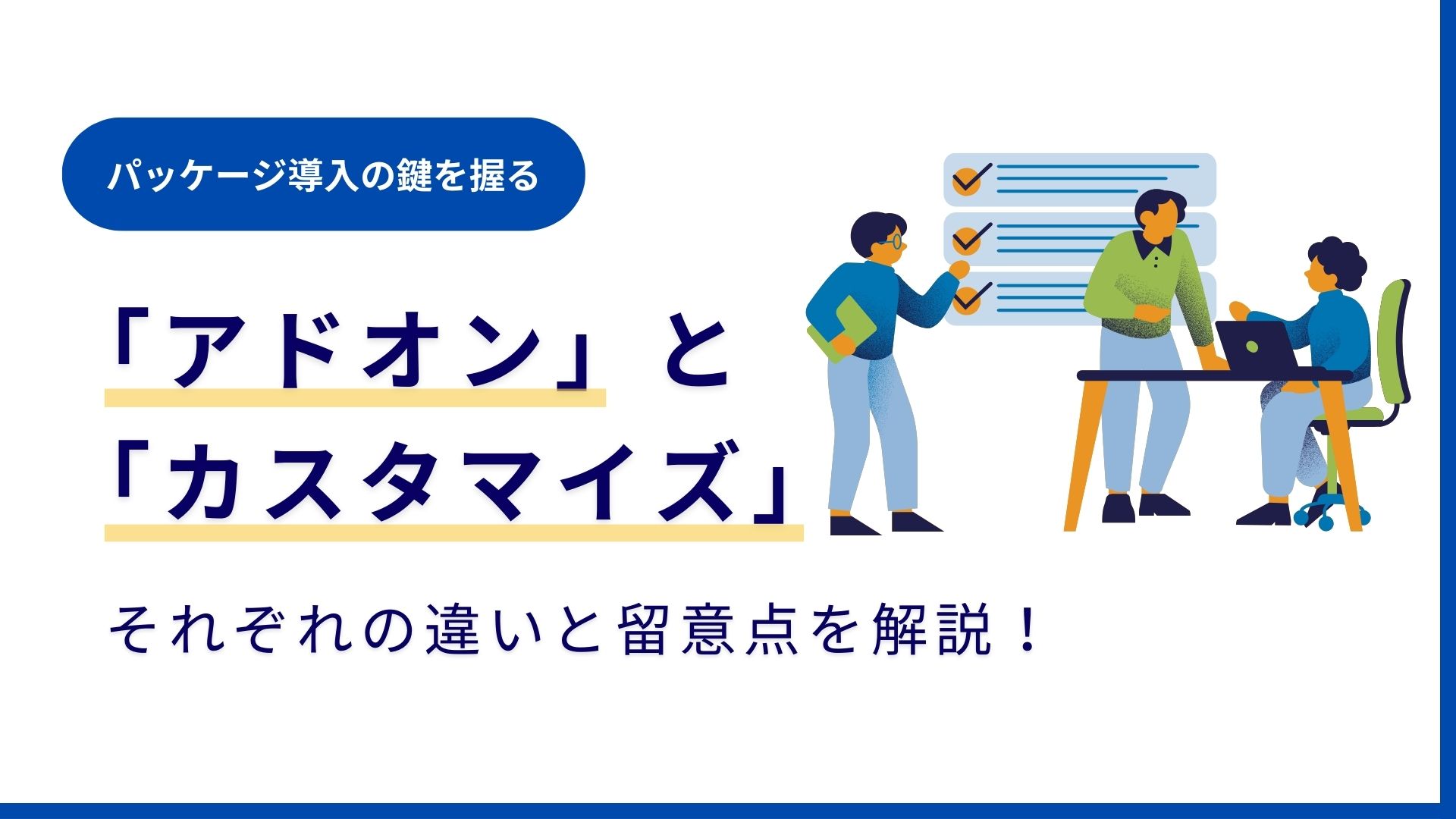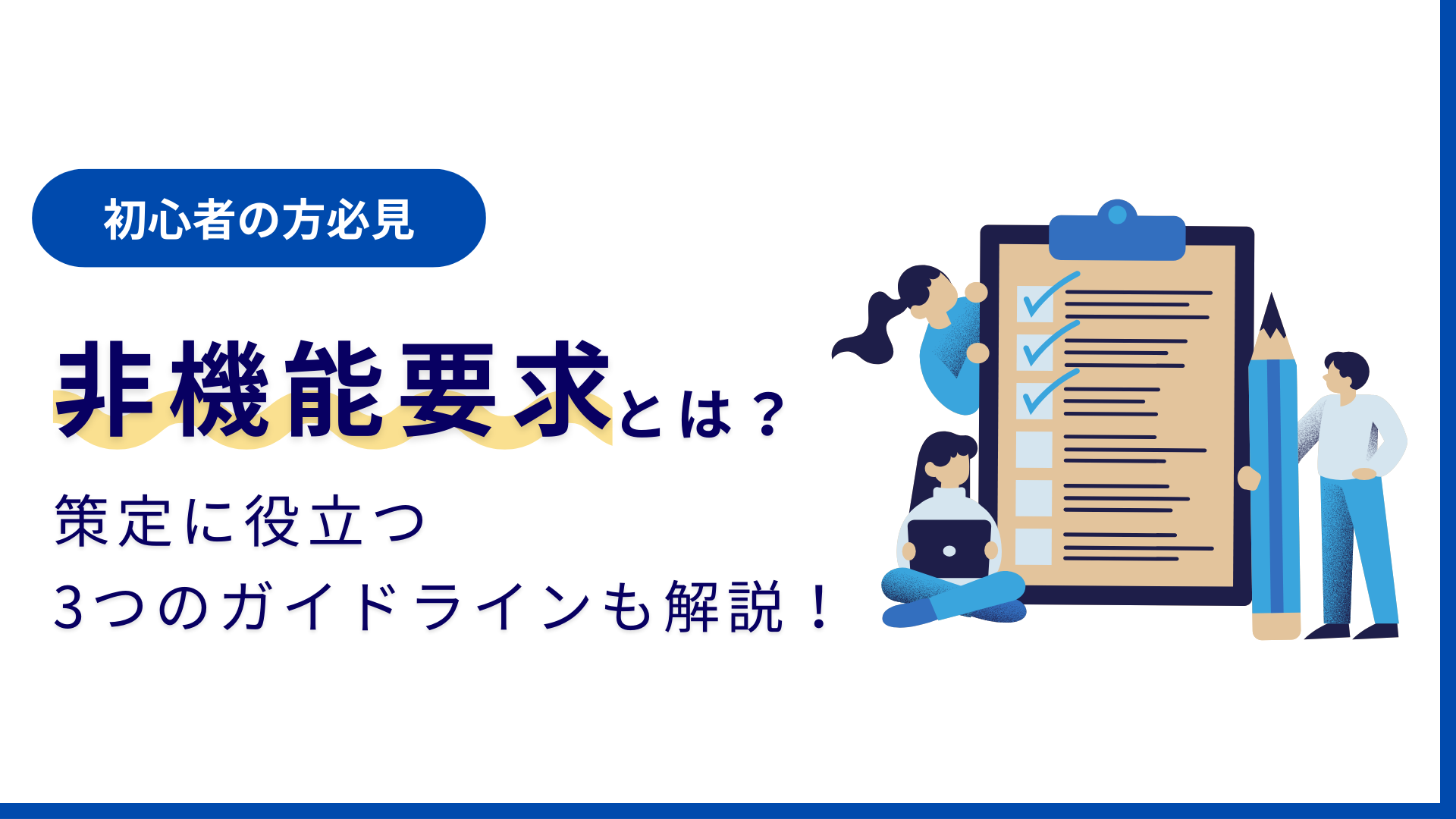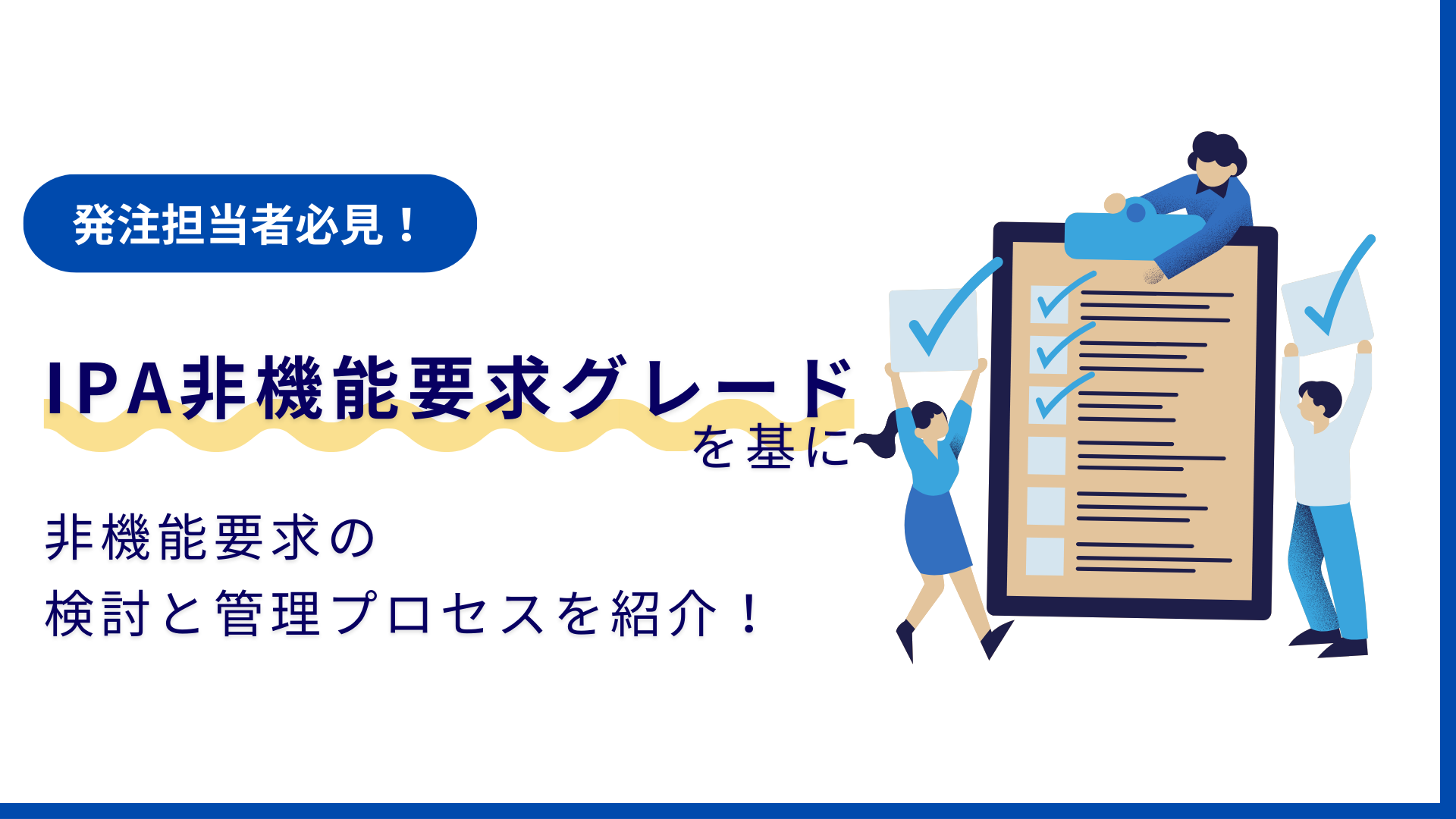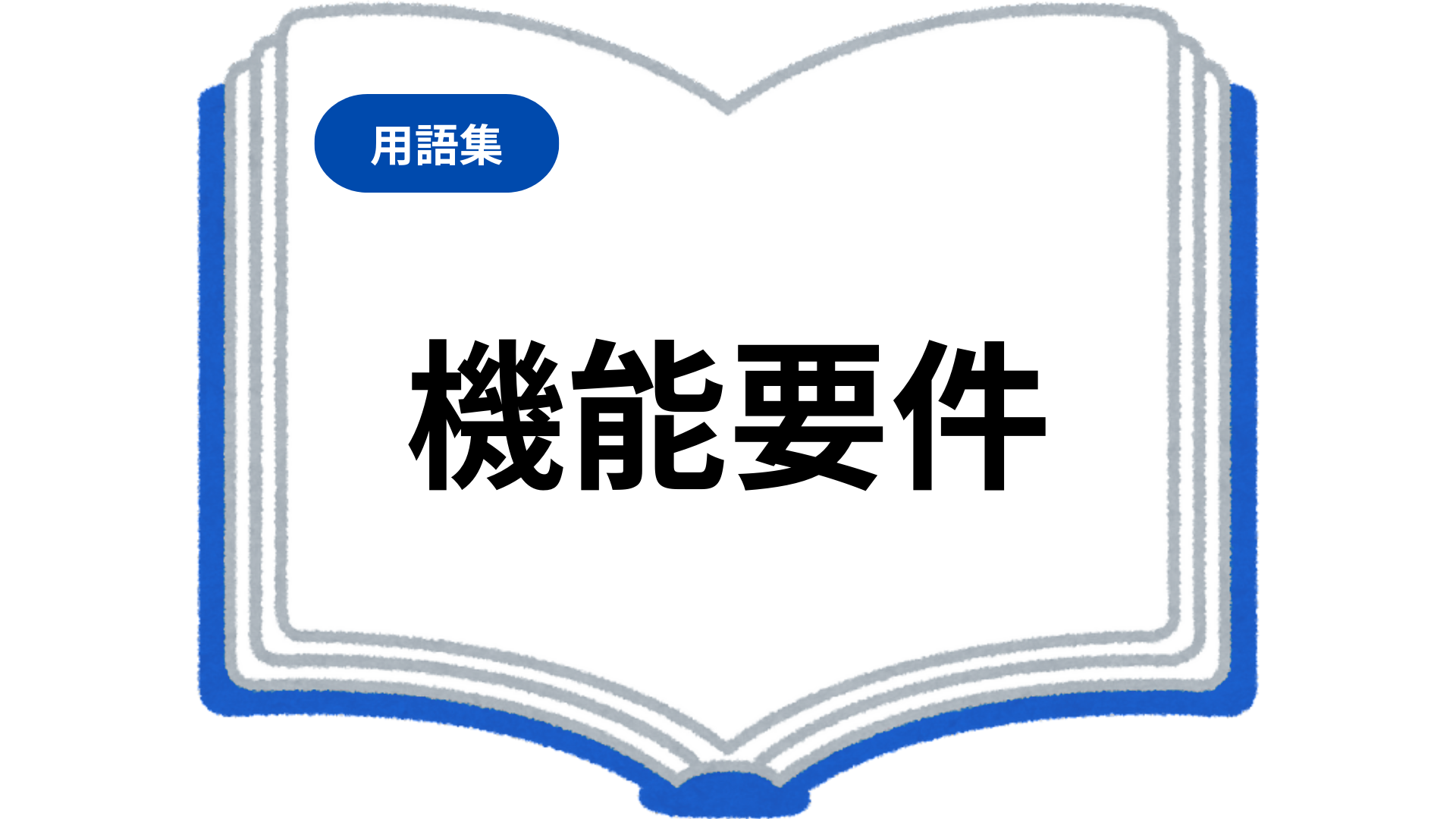
機能要件とは?デジタル庁で定められている機能要件の定義について解説
機能要件とは、導入するシステムが最終的に満たすべき機能のことです。
発注者はまず、自身の業務やニーズに基づいて機能要件の元となる要求を整理し、開発者と調整しながら具体的な機能要件を定義していきます。
機能要件の種類について、デジタル庁の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」では、以下の5種類を機能要件と定義しています。
・機能:処理内容や入出力情報など、システムが備えるべき機能に関わる要件
・画面:画面のイメージや遷移方法など、システムで表示される画面に関わる要件
・帳票:帳票のイメージや入出力方法など、システムで出力する帳票に関わる要件
・データ:データ項目やデータ標準化など、システムで扱われるデータに関わる要件
・外部インターフェース:他のシステムとのデータ送受信など、システム連携に関わる要件
また、機能要件を具体的に定義することを機能要件定義といいます。
機能要件定義とは、発注側の業務ニーズをもとに、どのような機能をシステムに実装するかを明確に文書化する作業です。
この定義作業によって、発注者と開発者の間で期待される機能への認識を一致させ、システム開発の方向性を共有できます。
定義が曖昧なまま開発が進むと、後工程で手戻りやトラブルが発生するリスクが高まるため、機能要件定義は非常に重要です。
なお、機能要件以外の要件として、「非機能要件」と「業務要件」があります。
「非機能要件」は、導入するシステムの性能やセキュリティなど、システム開発で定義するもののうち、機能以外の要件を指します。
「業務要件」は、システムを導入した後の業務実施手順や、システムで対応する業務の範囲などを指します。
目次
よくある質問
機能要件が曖昧だと、システム選定や発注にどんな影響がありますか?
機能要件が曖昧なままでは、製品選定の精度が低下し、契約後の認識ズレや追加対応の発生につながる恐れがあります。
想定される主な影響
1. 製品選定時の比較・評価が困難になる
必要な機能が具体化されていないと、複数製品の比較が機能面でなく「価格」や「ベンダー実績」などに偏りがちになります。その結果、自社業務に適さない製品を選定するリスクが高まります。
2. 要件と提案内容の齟齬
発注者の期待とベンダーの理解が一致しないまま契約に至ると、「実装されると思っていた機能が含まれていない」「画面や操作が想定と異なる」といったトラブルにつながりかねません。
3. カスタマイズや仕様変更によるコスト増
契約後に機能不足が判明すると、追加開発・仕様変更が必要になり、コスト増や納期遅延の要因となります。特に公共調達では契約変更の制約もあるため注意が必要です。
4. 品質管理や導入後評価の基準が曖昧に
機能要件は受入試験や検収の判断基準となるため、要件が不明確だと、完成基準が曖昧となり、品質担保が難しくなります。
機能要件は、システム調達における「期待値の明文化」であり、ベンダーとの共通認識の土台です。
不備や曖昧さがあると、選定ミスや契約後のトラブルを招きかねません。
業務要件をもとに、実装すべき機能を具体的かつ整理された形で記述することが、適切な発注と品質確保につながります。
パッケージ製品導入時における機能要件の扱い方にはどのような要点がありますか?
パッケージ製品導入時も、機能要件は明確に定義する必要があります。
特に「自社業務との適合性」を見極める観点が重要です。
主なポイント
1. Fit&Gap分析の前提資料になる
パッケージ製品には既定の標準機能が備わっているため、自社の業務要件とどこが一致し、どこに差異があるかを見極める必要があります。機能要件を明文化することで、「標準で対応可能な範囲」と「追加開発や運用変更が必要な領域」を明確に切り分けることができます。
2. カスタマイズ要否の判断基準になる
「どの業務機能を残すか」「パッケージに合わせて業務を変えるか」「追加開発が必要か」といった判断は、機能要件が明確であることを前提とします。曖昧なままでは、不要なカスタマイズや仕様変更による費用増加を招く可能性があります。
3. ベンダーとの認識すり合わせに不可欠
発注側の期待とベンダーの提案内容に齟齬が生じないよう、機能要件を基にした具体的な要件確認が必要です。要件が明確であれば、提案書や見積もりの内容も適切に評価しやすくなります。
4. 受入試験や契約の根拠として活用
導入後の受入試験や品質確認の基準としても、機能要件は重要です。「満たすべき要件」が合意されていれば、納品時のチェックや契約検収が円滑に行えます。
パッケージ製品導入時も、機能要件の定義は必要不可欠です。
標準機能とのFit & Gap分析、カスタマイズ有無の判断、ベンダー提案の精査、検収基準の明確化といったあらゆる局面で、機能要件がプロジェクトの指針となります。
単に製品に合わせるのではなく、自社業務と製品の整合性を検証するために、丁寧な要件整理が求められます。
機能要件と非機能要件(性能・セキュリティ要件等)の記述範囲はどこまで明確にすべきですか?
機能要件・非機能要件ともに、システムの受入れ基準や運用安定性を担保できるよう、可能な限り具体的かつ定量的に記述することが重要です。
明確化すべきポイント
1. 機能要件の記述例
・実現すべき具体的な機能や操作
・対象ユーザーや業務プロセスに対応する範囲
・入出力や画面項目の仕様
2. 非機能要件の記述例
性能要件:処理速度、応答時間、同時アクセス数の上限など
可用性・信頼性:稼働率目標や障害復旧時間の規定
セキュリティ:アクセス制御、ログ管理、暗号化基準など
拡張性・保守性:将来の機能追加や運用変更に対応できる設計
法令遵守・ガイドライン適合:個人情報保護や業界標準への準拠
システム要件は、「何ができるか」だけでなく、「どの程度の品質・性能で動作するか」まで含めて明確に示すことが必要です。
特に非機能要件は、曖昧なままだと運用トラブルやパフォーマンス低下を招きやすく、受入検査時の争点にもなり得ます。
機能・非機能要件ともに、関係者間で具体的に共有できるレベルでの定義を心がけましょう。
あわせてこの用語と記事をチェック