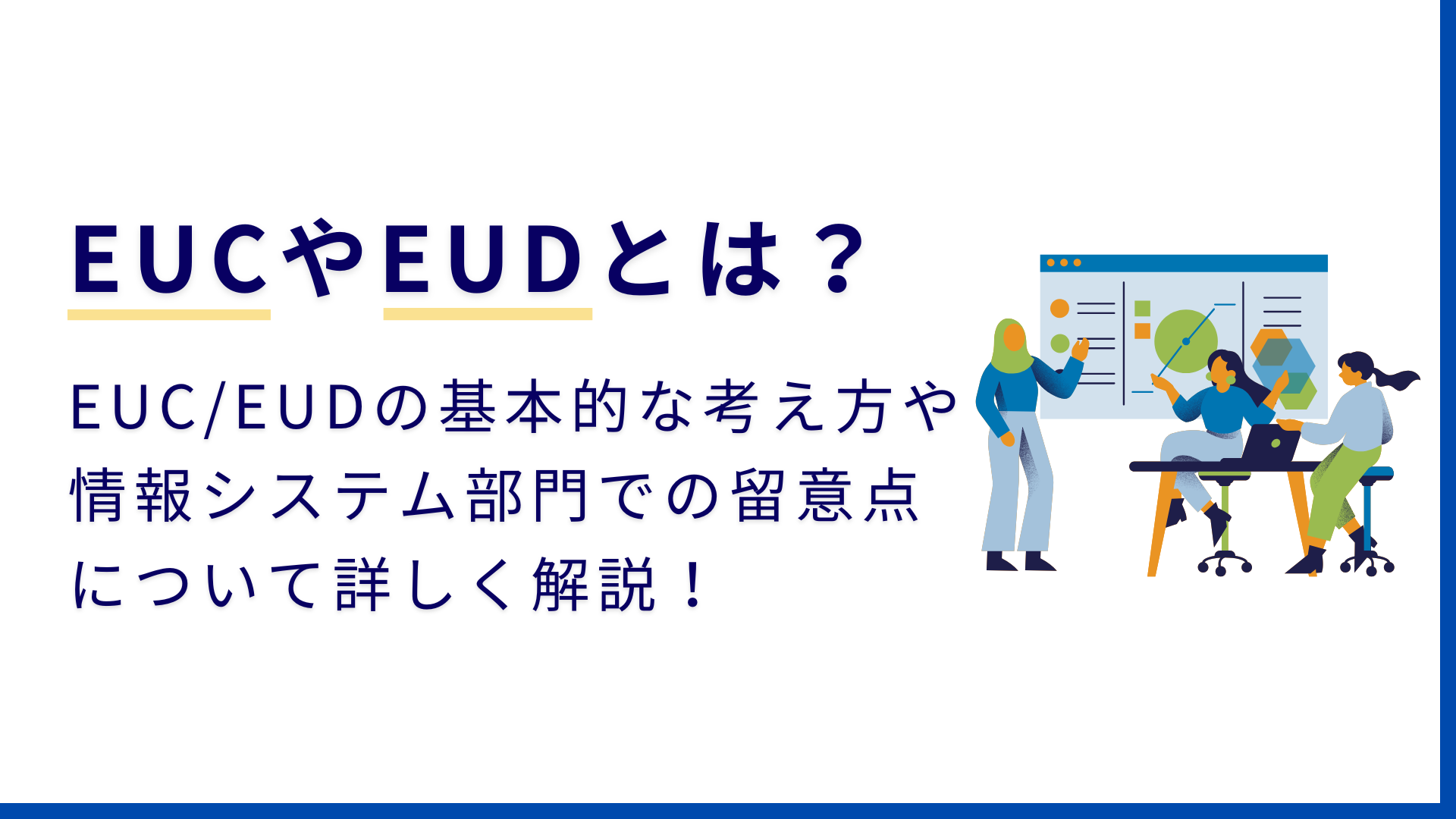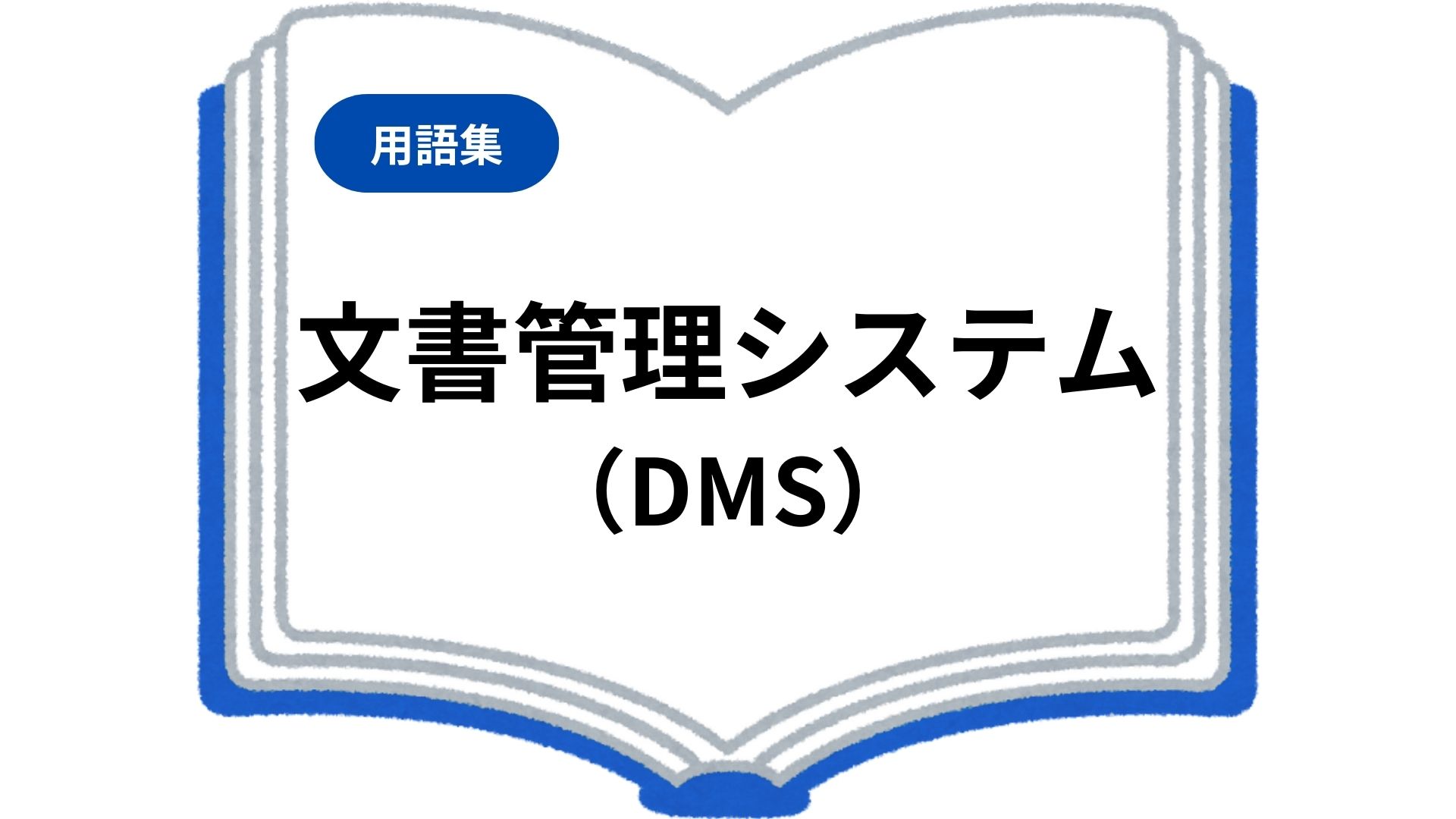
文書管理システム(DMS)とは?機能・メリット・他システムとの違いについて解説
文書管理システム(DMS)とは、企業内の文書やファイルを電子的に一元管理するためのシステムです。
DMSを活用することで、電子ファイルの保存・検索・共有を効率的に行うことができます。
また、スキャナー機能を備えた専用ソフトウェアやハードウェアと組み合わせることで、紙の文書をデジタル化することも可能になります。
DMSには、文書の保存、検索、バージョン管理、アクセス権限の設定といった機能に加え、ワークフロー機能が搭載されているものもあり、承認プロセスの自動化や業務の進捗管理が可能です。
例えば、請求書や契約書といった重要書類を安全に保管し、必要な時に迅速に検索・取得することができます。
また、複数の従業員が同じ文書を共同編集する際には、更新履歴を記録して変更内容を追跡することが可能です。
さらに、文書へのアクセス制限を設けることで、機密情報の漏洩を防ぐことができるのも特徴です。
近年、企業のDX推進の加速や電子帳簿保存法(電帳法)の改正に伴う事業環境の変化により、文書の電子化とその適切な管理は不可避の課題となっています。
その解決策として、多くの企業でDMSの導入が進んでいます。
DMSを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
①キーワード検索で瞬時に文書を特定
文書の検索時間が大幅に短縮され、業務効率が向上します。
従来のファイリングキャビネットでの管理と比べ、必要な文書をキーワード検索で即座に見つけることが可能です。
②災害対策とBCP対応を強化
災害時のリスク管理の観点からも重要です。
紙の文書は火災や水害で失われる可能性がありますが、DMSで電子化して保管することで、確実なバックアップが可能となります。
③AI・OCRで入力作業を自動化
近年のDMSにはAIを活用したOCR(光学文字認識)や文書の自動分類機能を備えたものもあり、手作業によるデータ入力の負担軽減や業務のさらなる効率化が期待できます。
DMSと他のシステムの違いを理解しておくことも重要です。
- ERP(統合基幹システム)
ERPは経理や人事など基幹業務全般を統合管理するシステムであり、一部の文書管理機能を含む場合もありますが、DMSは文書の保存・管理・共有に特化しています。 - グループウェア
情報共有や社内コミュニケーションが主目的のグループウェアと比べ、DMSは文書の版管理や長期保存機能が充実しています。 - クラウドストレージ
クラウドストレージはファイルの保存・共有を目的としたサービスですが、DMSは文書の体系的な管理や詳細な権限設定、ワークフロー機能などを備えており、より業務プロセスに直結した管理が可能です。
DMSは、企業の文書管理を効率化し、業務プロセスを改善する重要なツールです。
コンプライアンスへの対応や働き方改革の推進においても、その重要性は増す一方です。
導入に際しては、自社の業務フローや必要な機能を十分に検討し、適切なシステムを選択することが成功への鍵となるでしょう。
目次
よくある質問
自治体や企業がDMSを導入する際、特に留意すべきセキュリティ面のポイントは何でしょうか?
DMS導入時には、格納する文書の機密性や公開範囲に応じたアクセス制御と、改ざん・漏洩を防ぐ仕組みを整備することが重要です。
特に自治体や企業では、個人情報や契約書など外部流出が許されない文書を扱うため、セキュリティ要件を明確に設定する必要があります。
主なセキュリティ上の留意点
1. アクセス権限管理
・ユーザーや部署ごとに閲覧・編集・削除権限を細かく設定できる機能が必須です。
・「最小権限の原則」を適用し、必要以上の権限を付与しないことが望まれます。
2. 認証・多要素認証の導入
・ID/パスワードのみでなく、ワンタイムパスワードや認証アプリなど多要素認証を利用することで、不正アクセスを防止します。
3. 通信・保存データの暗号化
・インターネット経由で利用する場合は通信経路の暗号化(TLS)を徹底する必要があります。
・サーバー内に保存されるデータについても暗号化対応が望ましいです。
4. 操作ログ・監査証跡の記録
・文書の閲覧・更新・削除といった操作履歴を自動的に記録し、監査や不正調査に活用できる仕組みを備えることが求められます。
5. バックアップと可用性確保
・データ消失や災害時に備え、冗長化・定期バックアップ・復旧手順を整備する必要があります。
・特に自治体ではBCP(事業継続計画)との整合性を考慮することが重要です。
6. クラウド利用時の留意点
・データ保管場所(国内外のデータセンター)や契約上のセキュリティ水準を確認することが必要です。
・自治体の場合、「ガバメントクラウド」など標準的なクラウド環境との適合性も考慮されます。
DMSのセキュリティ対策は、「誰がどの文書にどうアクセスできるか」を明確に制御し、さらに不正や障害時に備えた仕組みを組み込むことがポイントです。
発注者はベンダー任せにせず、組織の情報セキュリティポリシーや法令に基づいて要件を設定することが求められます。
DMS導入にあたり、発注者が検討すべき非機能要件(性能・拡張性・可用性など)は何でしょうか?
DMSは日常的に大量の文書を扱う基盤システムであるため、機能要件だけでなく、長期運用を見据えた非機能要件を定義することが不可欠です。
特に性能・拡張性・可用性・セキュリティといった観点をバランスよく検討することが求められます。
主な非機能要件の検討ポイント
1. 性能(レスポンス・処理能力)
・大量文書の検索や表示が遅延なく行えること。
・同時アクセス数が増えても処理が安定するかを検討する必要があります。
2. 拡張性(スケーラビリティ)
・将来的な文書数や利用部門の増加を見据え、ストレージや機能拡張が容易な構成であること。
・クラウド型の場合はスケールアウトの柔軟性も確認が必要です。
3. 可用性・信頼性
・システム障害時の復旧時間や許容ダウンタイムを定義し、冗長構成やバックアップ方式を検討します。
・災害時のBCP(事業継続計画)に対応できる設計が望まれます。
4. セキュリティ
・アクセス権限管理や暗号化、監査ログといったセキュリティ要件は非機能要件として明確化が必要です。
・個人情報や機密文書を扱う場合は法令やガイドラインへの準拠を必須とします。
5. 運用性・保守性
・バージョン管理、監査対応、利用ログの出力など運用時に必要な仕組みがあるか。
・ユーザーサポートや管理者機能が整備されているかを確認する必要があります。
DMSの非機能要件は、「長期に安定して使えるか」「将来の変化に対応できるか」を中心に検討することがポイントです。
発注者はベンダーに任せきりにせず、性能・拡張性・可用性・セキュリティといった要素を調達仕様書に明示することが望まれます。
DMSの運用定着を図るために、発注者側でどのようなルールや体制整備が求められるでしょうか?
DMSは導入するだけでは定着せず、発注者が主体的にルールを整備し、組織全体での利用を浸透させることが不可欠です。
特に「文書管理ルールの明確化」と「運用を支える体制づくり」が求められます。
主な整備ポイント
1. 文書の分類・保存ルール
・文書種別ごとの保存場所・フォルダ構成・命名規則を統一します。
・保存期間や廃棄ルールを定め、情報が散逸しないようにします。
2. アクセス権限と承認フロー
・部署・役職ごとにアクセス権限を整理し、機密文書の閲覧範囲を適切に制御します。
・文書の登録・改訂・公開には承認プロセスを設け、責任の所在を明確にします。
3. 利用ルールの周知・教育
・操作マニュアルやFAQを整備し、利用者研修を実施します。
・利用ルールを継続的に周知し、従業員が迷わず利用できる環境を整えます。
4. 運用責任者・管理部門の設置
・システム管理者や文書管理責任者を定め、運用上の問い合わせ対応や改善活動を担わせます。
・定期的にルール遵守状況を点検し、必要に応じて改善します。
5. 監査・モニタリングの仕組み
・操作ログを活用して不正利用やルール違反を検知します。
・内部監査や情報セキュリティ委員会などの場で運用状況を定期的に確認する体制を構築します。
DMSの定着には、「文書管理ルールの策定」「運用体制の明確化」「教育・監査による継続改善」が不可欠です。
発注者が主体的にルールを整え、組織全体に根付かせることで、システムは単なる文書保存庫ではなく、組織的な情報資産管理の基盤として機能します。