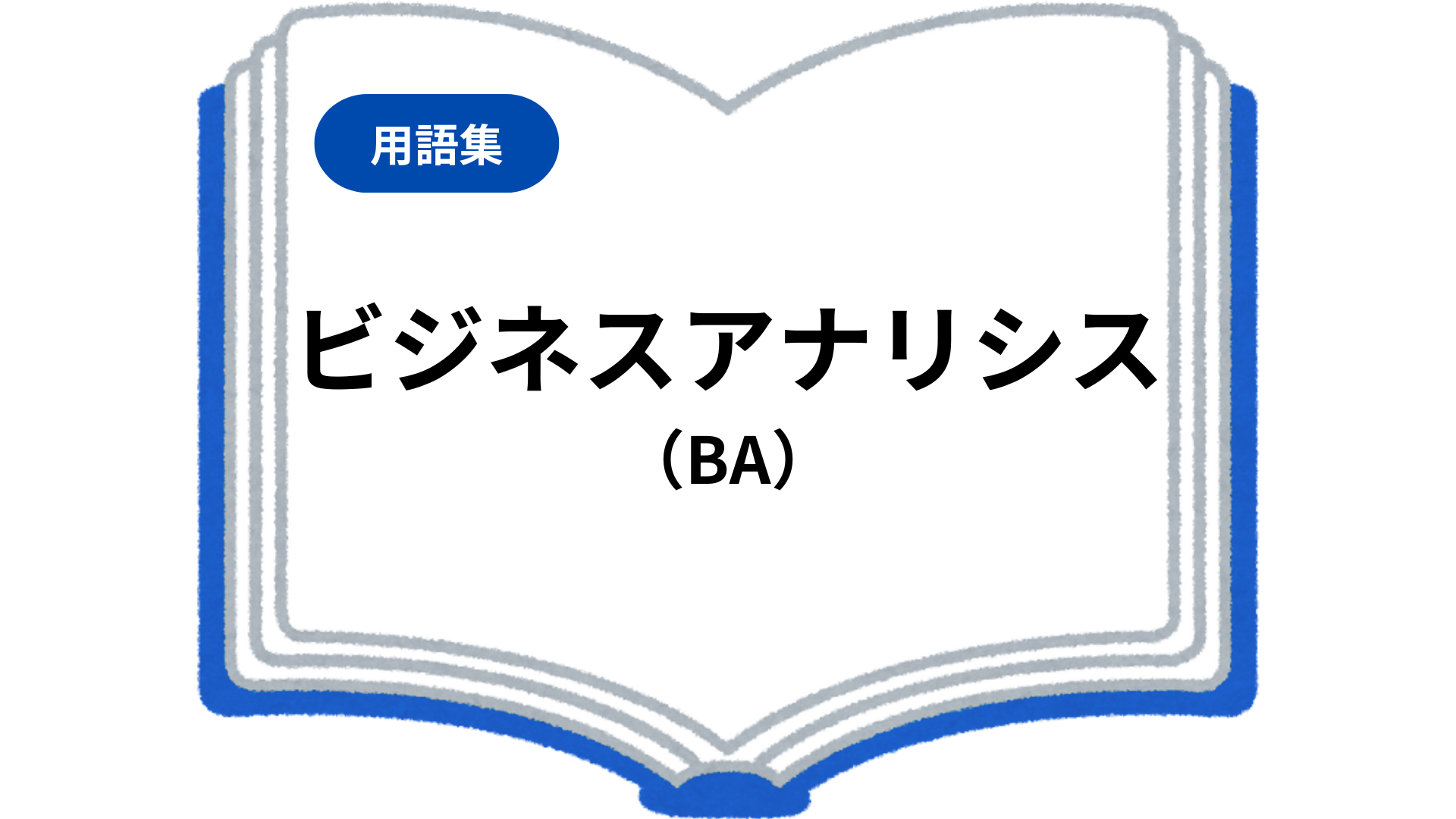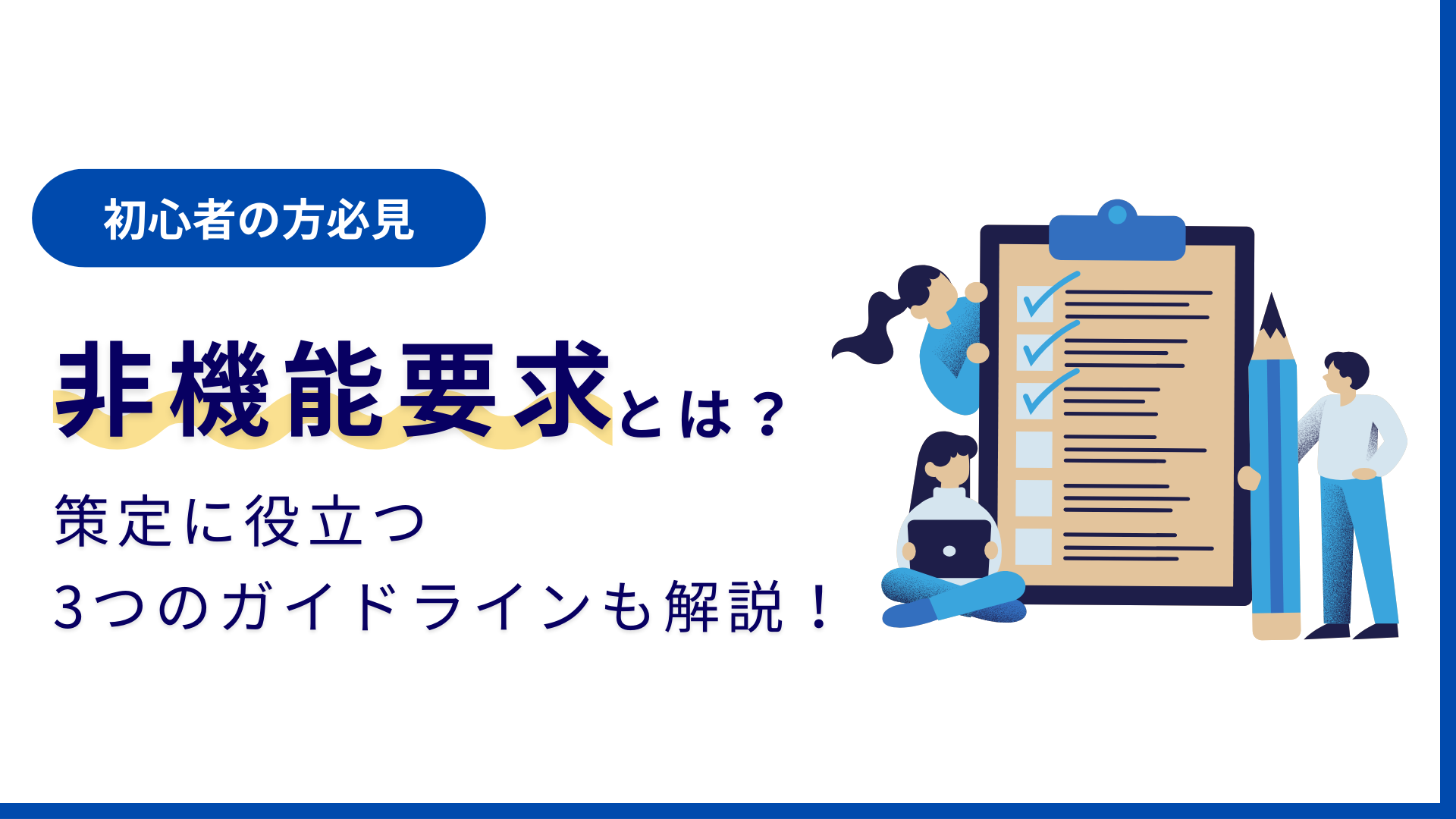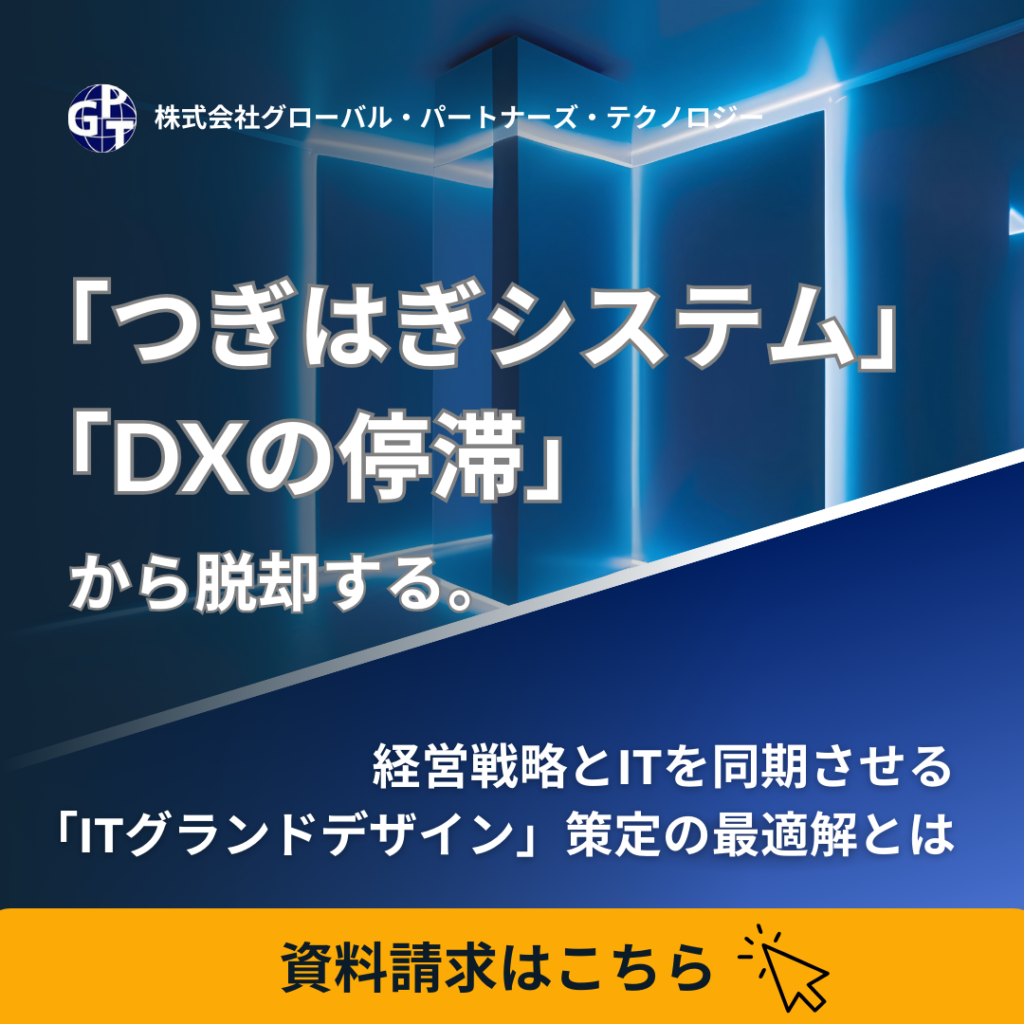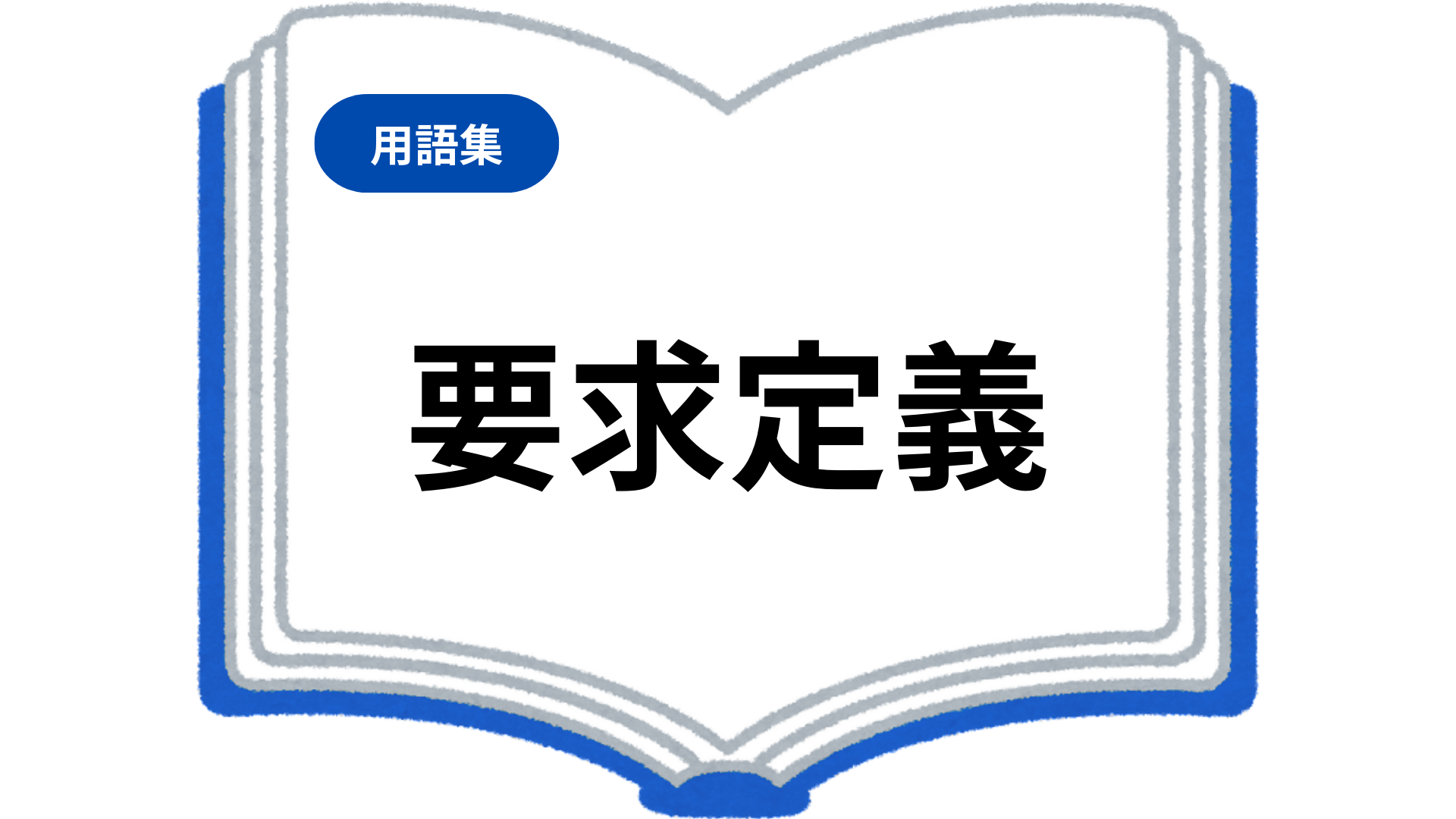
要求定義とは?ユーザ側が主体となって取り組むべき工程について解説
要求定義とは、新システムの導入や既存システムの刷新を検討している企業が、システム開発会社へ発注する前に「どんなシステムを作りたいか(実現したいこと)」を明確化するプロセスです。
この段階では、具体的な技術的仕様ではなく、業務課題をどう解決したいか、どのような成果を得たいかといったビジネス視点での要望を中心に整理します。
要求定義を実施する主な目的は、「自分たちが求めている新システム像」を発注先の候補となるシステム開発会社に齟齬なく伝えることです。
システムを発注するプロセスにおいては、下記のように複数の段階に分けて要求定義を実施します。
- 業務課題の洗い出し
現行業務、現行システムの課題やユーザーの不満などを洗い出して整理します。 - 要求概要の検討
1.の工程で洗い出した課題を基に、次期システムに求める機能の大まかな方向性を定義します。 - 情報収集・ベンダーとの対話
要求概要をもとに、複数の開発ベンダーから情報を収集し、技術的な可能性や実現手段を検討します。 - 要求仕様の策定
実現可能な範囲を見極めながら、必要な機能や対応範囲を具体的な要求仕様として文書化します。そして、それらをシステム導入/刷新計画書に反映させていきます。
株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジーでは、現行調査からシステム導入/刷新計画書に反映までの工程について、説明した記事を公開しております。
詳細について知りたい方は、下記の記事もご参照ください。
システム導入/刷新に向けた現状分析の進め方と計画の立て方とは?
なお、要件定義は発注側の企業で検討した要求仕様をもとに、発注し契約をしたシステム開発会社と一緒にシステムで実現する要件を決めるプロセスのことです。
要求定義が不十分なまま発注を行ってしまうと、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 要件定義や設計の段階で追加工数・追加費用が発生する
- ベンダーとの認識の齟齬により仕様の抜け漏れ・誤解が起きる
- 開発後のシステムが期待と異なるリスクに繋がる
このような事態を避けるためにも、要求定義は発注前に時間をかけて丁寧に実施することが不可欠です。
目次
よくある質問
業務課題の洗い出しを発注者が主体的に行うことは、なぜ求められるのでしょうか?
業務課題の洗い出しは、システム導入の方向性を定める出発点であり、発注者が主体的に取り組むことが求められます。
発注者自身が課題を整理せずにベンダー任せにすると、導入後に期待と実態の乖離が生じ、投資効果が十分に得られない可能性があります。
1. 業務実態の正確な把握が可能
発注者は自らの業務フローや運用上の課題を最も理解しています。
現場の実態を発注者が自ら整理することで、システム化すべき課題とそうでない課題を明確に切り分けられます。
ベンダーに任せた場合、外部からは見えにくい運用上の問題や将来的な改善ニーズが漏れてしまう恐れがあります。
2. システム要件の的確な設定につながる
課題の洗い出しが不十分だと、表面的な要望だけが要件化され、導入後に「業務に合わない」「想定外の機能不足がある」といった問題が発生しやすくなります。
発注者が主体的に課題を定義することで、システム化の目的と機能要件を一貫性をもって整理できます。
3. 投資効果と優先度の明確化
業務課題を具体的に洗い出すことで、解決すべき優先順位や期待できる効果を定量的に評価しやすくなります。
これにより、システム投資が単なるコストではなく、経営的成果に結び付けやすくなります。
4. 組織全体の合意形成を促す
課題の抽出は利用部門や経営層を巻き込みながら行う必要があります。
発注者が主体となって関係者の意見を集約することで、導入後に「現場が使いにくい」「経営目標と整合していない」といった不満を防ぎ、システム活用の定着につながります。
以上の理由から、業務課題の洗い出しを発注者が主体的に行うことは、システム化の目的を明確化し、導入効果を最大化するために不可欠といえます。
要求仕様の策定にあたり、発注者が特に注意すべきポイントは何でしょうか?
要求仕様の策定は、プロジェクトの成否を左右する重要な工程であり、発注者が主体的に関与して具体性と一貫性を確保することが求められます。
要求仕様が曖昧なままでは、ベンダーごとの解釈の違いから追加費用や納期遅延につながるリスクが高まります。
1. 曖昧さの排除と具体性の確保
「高速」「使いやすい」などの抽象的な表現は避け、処理速度や画面遷移数など定量的な指標を明記することが望まれます。
具体性を持たせることで、発注者とベンダーの認識を一致させやすくなります。
2. 業務課題との対応付け
仕様を単なる機能要望として記述するのではなく、解決すべき業務課題と結びつけることが重要です。
課題と対応関係を明示することで、優先度の整理や将来的な拡張判断も容易になります。
3. 範囲と前提条件の明確化
システムで対応する範囲、外部システムとの連携、運用体制の前提条件を明確にしないと、「想定外」として追加コストや再調整が発生しやすくなります。
契約条項や見積条件に直結するため、特に注意が求められます。
4. 関係者の合意形成
利用部門・情報システム部門・経営層といった多様な立場の関係者が関与するため、策定段階での合意を確保することが不可欠です。
発注者が調整役を担うことで、導入後の利用定着や満足度を高められます。
要求仕様の策定は「具体性」「業務との結びつき」「範囲・前提の明確化」「合意形成」という4点を意識することが求められます。
これにより、発注者自身がプロジェクトを主導し、契約や進行管理を安定させる基盤を築くことができます。
要求定義を軽視した場合、予算や納期にどのようなリスクが波及するでしょうか?
要求定義を軽視すると、システム化の目的や範囲が曖昧なまま進むため、結果として予算超過や納期遅延といった重大なリスクが発生しやすくなります。
発注者が初期段階で十分な整理を行わない場合、調達全体の不確実性が高まり、契約や進行管理に直接的な影響を及ぼします。
1. 追加開発によるコスト増加
要求が曖昧なまま契約すると、開発途中で仕様変更が頻発しやすくなります。
そのたびに追加費用が発生し、最終的に当初想定を大きく上回るコストがかかる恐れがあります。
2. 納期遅延の連鎖
要求が固まらないまま進行すると、ベンダー側で手戻りが増え、開発工程が停滞します。
結果として検証や導入のスケジュールも後ろ倒しになり、全体の納期遅延につながります。
3. 契約トラブルの発生
契約時に範囲や要件が不明確だと、「これは契約対象外」といった認識の齟齬が生じやすくなります。
こうした解釈の違いは、追加請求や調整コストを招き、結果的に予算や納期を圧迫します。
4. 進行管理の困難化
要求が不明確なままでは進捗や成果物の評価基準も曖昧になり、問題を早期に把握できません。
その結果、軌道修正が遅れ、コストと納期の双方に悪影響が波及します。
要求定義を軽視すると「追加費用」「納期遅延」「契約トラブル」のリスクが高まり、発注者自身が不利益を被る可能性が大きくなります。
そのため、初期段階から要求を丁寧に整理し、契約や進行管理に反映させることが強く求められます。
要求定義と要件定義を混同すると、プロジェクト全体にどのような影響が及ぶ可能性があるでしょうか?
要求定義と要件定義は工程の目的と役割が異なります。
これを混同すると、プロジェクトの方向性や契約条件にずれが生じ、最終的に予算・納期・品質のいずれにも悪影響が波及する可能性があります。
1. システム化の目的が不明確になる
本来、要求定義は「どのような課題を解決したいか」を発注者が整理する工程です。
これを要件定義と混同すると、ベンダー主導で技術的仕様ばかりが先行し、業務課題が解決されないままシステムが構築される恐れがあります。
2. 契約や範囲設定の不一致
要求定義が曖昧なまま要件定義に移行すると、契約で定める範囲や成果物に抜け漏れが生じやすくなります。
結果として「契約対象外」といった解釈の違いが発生し、追加費用や調整コストにつながります。
3. 進行管理の混乱
要求と要件の切り分けができていないと、進行管理の評価基準が曖昧になります。
業務的な成果と技術的な成果の双方を正しく測れず、問題の早期発見が難しくなるため、遅延や品質低下のリスクが高まります。
4. 発注者の主体性低下
本来は発注者が担うべき「業務ニーズの定義」をベンダーに委ねてしまうことで、導入後に「現場に合わない」「期待と異なる」といった不満が残りやすくなります。
これによりシステム活用の定着も阻害されます。
このように、要求定義と要件定義を混同すると「目的の不明確化」「契約範囲の齟齬」「進行管理の困難化」「利用定着の阻害」といった形でプロジェクト全体に影響が及ぶため、両者の違いを理解して進めることが望まれます。