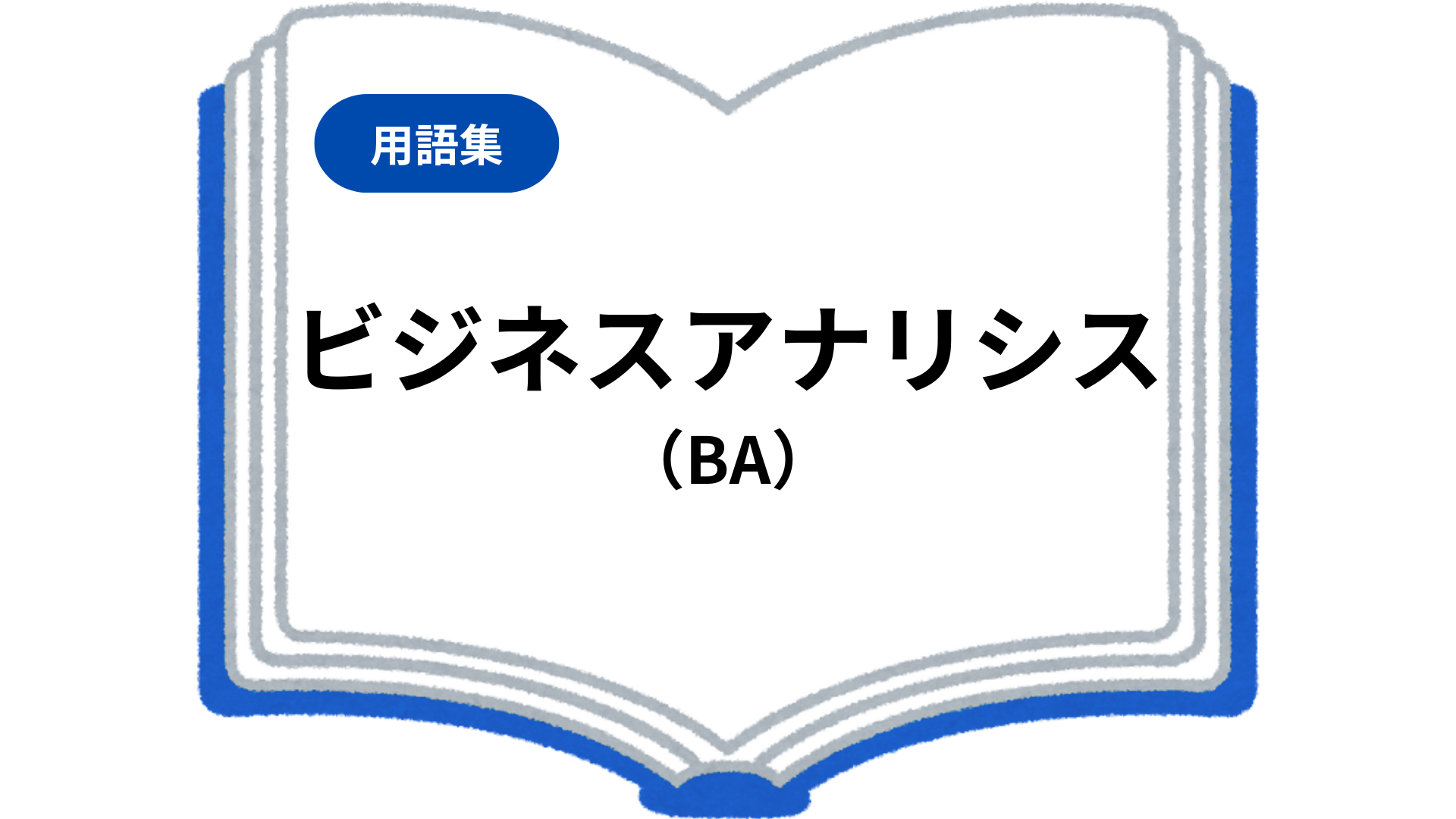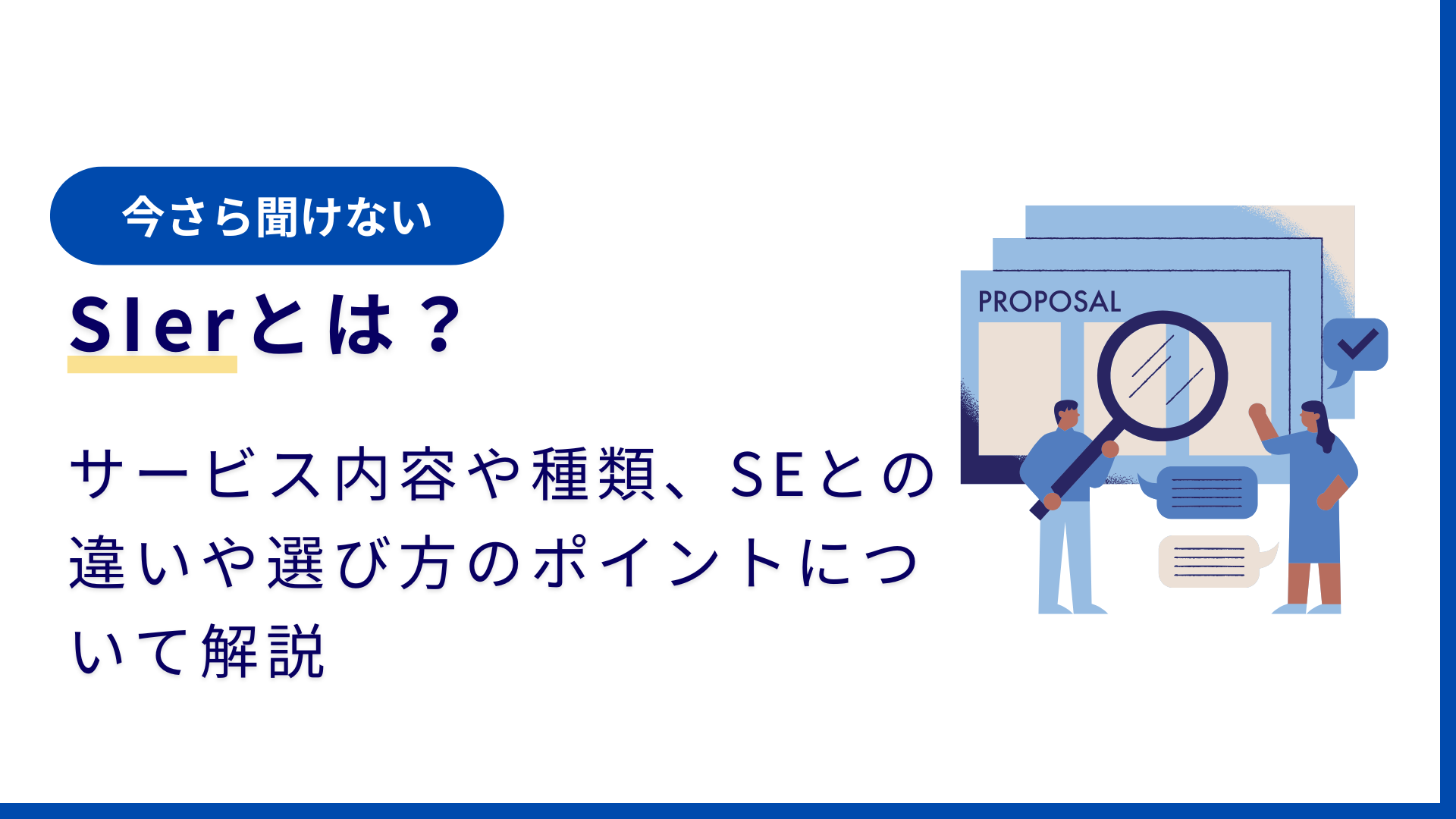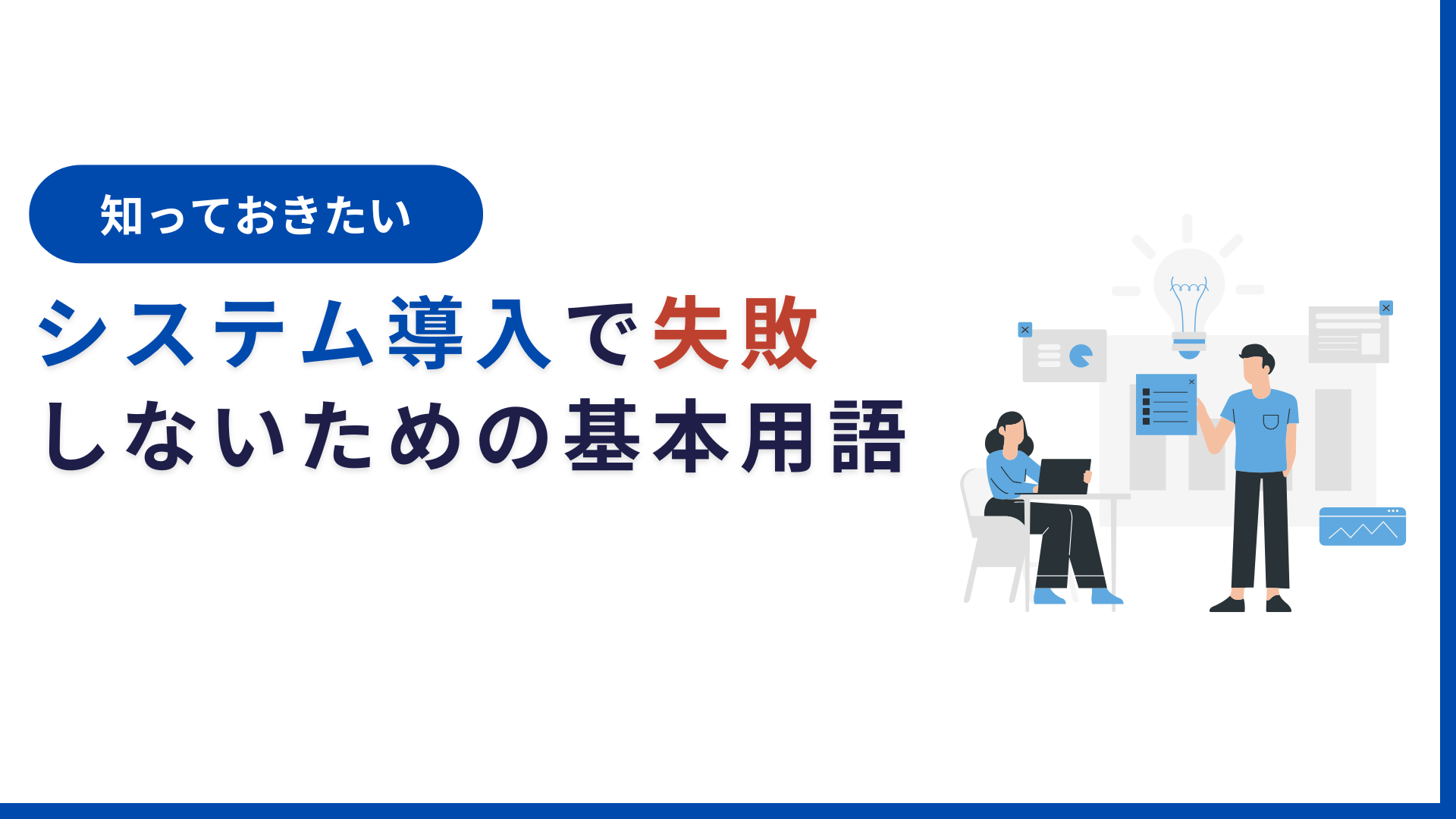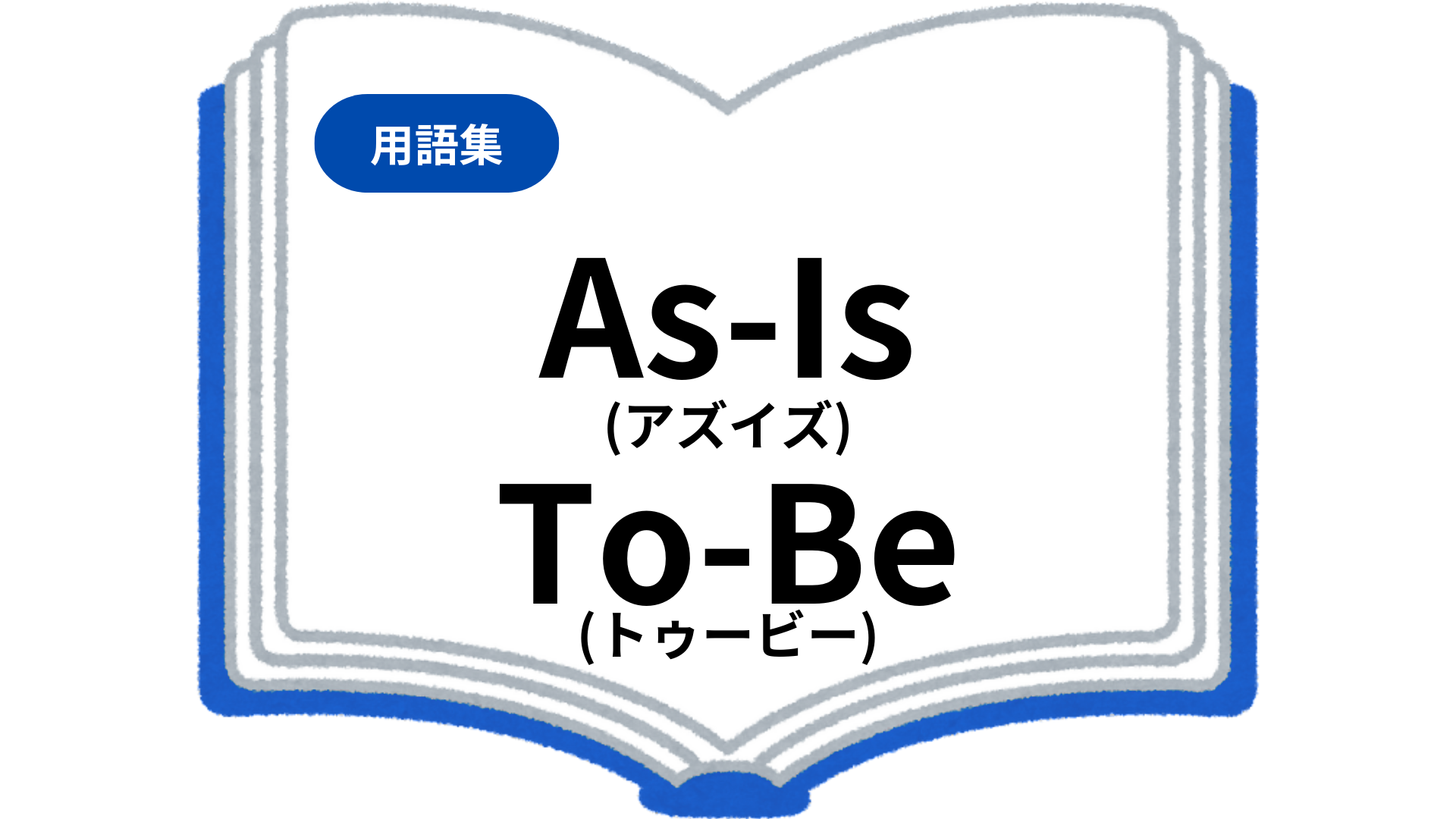
As-Is・To-Beとは?IT調達における頻出用語の意味と使い方について解説
近年、デジタル化の加速やDX進に伴い、多くの企業が業務改善や情報システムの見直しを進めています。
このような取り組みを成功させるうえで重要な概念が「As-Is(アズイズ)」と「To-Be(トゥービー)」です。
「As-Is(アズイズ)」とは「現状」という意味を持つ英熟語です。
使い方としては、下記のような使い方です。
- As-Is業務:現状の業務を指す用語です。
- As-Isシステム:現状のシステムを指す用語です。
一方、「To-Be(トゥービー)」は、「将来あるべき姿」「理想の姿」を意味する英熟語です。
現状分析をした後、課題分析やプロジェクト目標の具体化・最終化を実施します。
次に、企業が目指すべき理想の業務プロセスやシステムを明確にします。
その際に使われるのがTo-Beという用語です。
使い方としては、下記のような使い方です。
- To-Be業務:システム導入後の理想の業務を指す用語です
- To-Beシステム:システム導入後の理想のシステムを指す用語です
両者を比較することで、何が足りないのか、どのように業務を効率化すべきかが明確になり、結果として費用対効果の高いIT投資を実現することができます。
ヒアリングや業務フロー作成のポイントについて知りたい方は下記の記事をご参照ください。
現状分析から業務のあるべき姿を検討するフェーズについて解説した記事もあります。
情報システムの刷新を担当することになり課題分析をすることになった担当者の方は、下記の記事もご参照ください。
よくある質問
なぜ業務改善やシステム導入にAsIs/ToBeの整理が必要なのですか?
As-Is/To-Beの整理は、業務改善やシステム導入において非常に重要です。正しい整理を行うことで、次のようなメリットを得ることができるでしょう。
1.課題の可視化と認識の統一
現状を正確に把握し、理想像を描くことで、チームや関係者間で「どこが問題でどこを目指すか」を共通理解できます。これにより、議論を深めることができ、具体的な改善方向へ進めることができます。
2.表面的な改善行為の防止
漠然とした改善では「形だけの改革」に終わるリスクがあります。
As-Is/To-Beの整理を行うことで、現状と理想のギャップを明確にし、意味のある改善に繋げることができます。
3.解決策が整理できる
現状と理想の差分を明らかにすることで、どのステップを改善し、どの施策(システム導入、業務フロー変更など)を優先すべきかが見えてきます。
問題解決への具体的な方針が立てやすくなります。
As‑Is/To‑Beの整理は、業務改革・システム導入に取り組む際の基礎中の基礎です。
現状と理想を比較・共有し、真の課題を特定したうえで改善策へ落とし込むことで、無駄のないプロセスと確かな成果を得ることができるでしょう。
AsIs/ToBeはどの部門で実施すべき?
As‑Is/To‑Beの整理は、業務部門とIT部門の「協働」で進めることが重要です。具体的には以下のような役割分担が効果的です。
・業務部門(業務担当者)
As‑Is(現状)分析の主役は業務部門です。
日常業務を最もよく理解している業務担当者が、そのプロセス、手順、課題やボトルネックを整理します。
現場の声や視点を反映しないと、業務の実態と乖離してしまう可能性が上がってしまいます。
・IT部門(情シス、情報システム部門)
To‑Be(理想)設計では、業務部門から上がった課題を踏まえ、システム化や技術面からの改善策を検討したり、ワークショップやディスカッションをファシリテートする役割を担います。
IT部門は議論を整理し、方向性を補助する立場として非常に重要です 。
AsIs/ToBeの整理でよくある失敗や注意点は?
AsIs/ToBeの整理は業務改善やシステム導入における重要なステップですが、進め方を誤ると本来の効果が得られないことがあります。
よくある失敗の一つは、現場のヒアリングやデータ収集が不十分なままAsIs(現状)をまとめてしまい、表面的な課題しか見えなくなることです。
これでは、的確な改善策を立てるための出発点が曖昧になります。また、ToBe(理想像)についても、「業務を効率化する」「時間を短縮する」といった抽象的な表現にとどまってしまうと、チームの共通認識が得られず、実行に移しにくくなります。
さらに、AsIs/ToBeの整理そのものが目的化してしまい、分析に時間をかけすぎて改善施策が進まないというケースも少なくありません。
こうした失敗を防ぐためには、現場の実態を丁寧に把握しつつ、理想像には具体的な数値や期限を含めて描き、分析の結果を必ず次のアクションに結びつける視点が求められます。
特に最初は、「問い合わせ対応の時間短縮」や「属人化の解消」など、テーマを絞って小さく始めることで、現実的かつ実行可能な改善へつなげやすくなります。