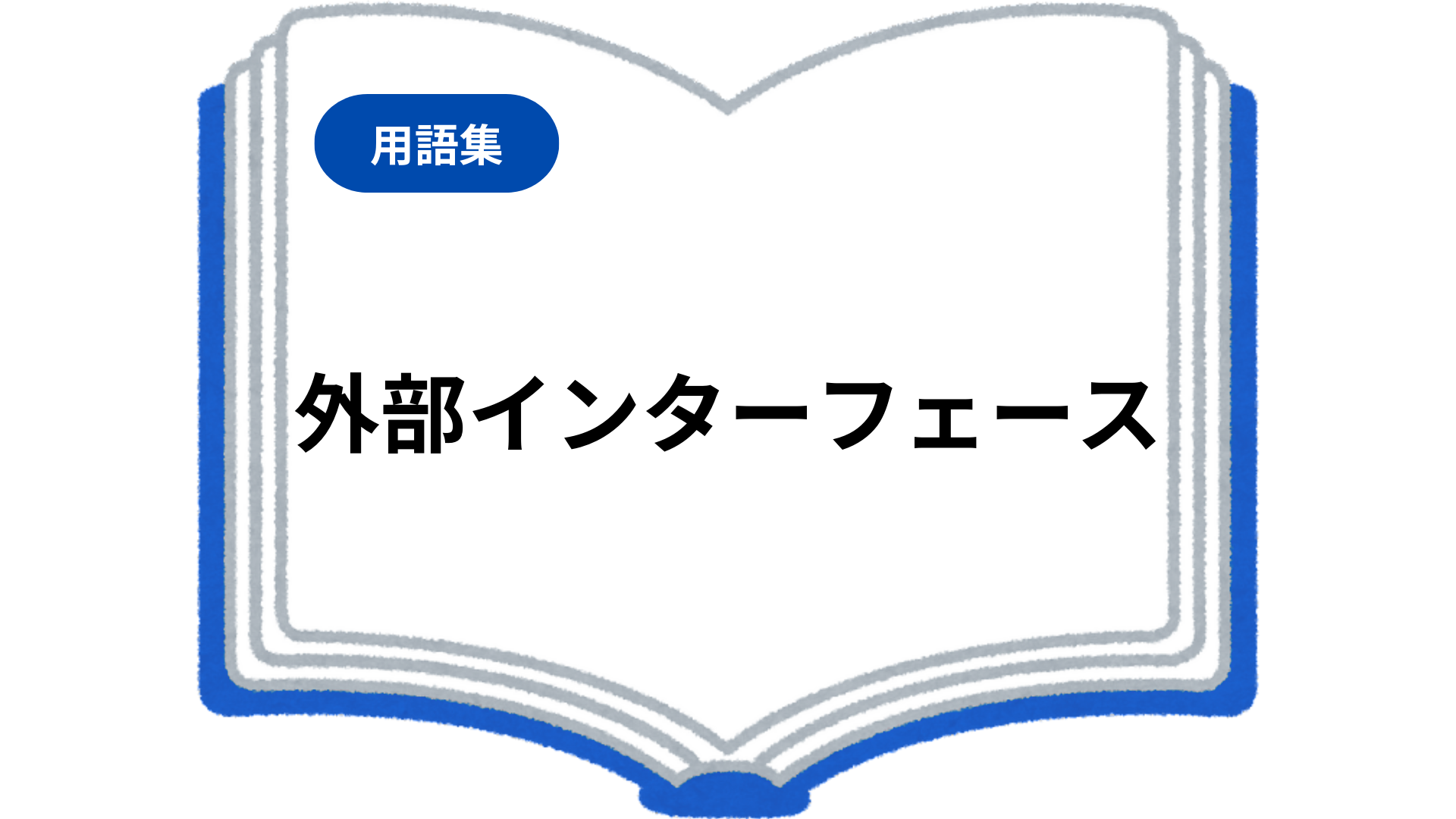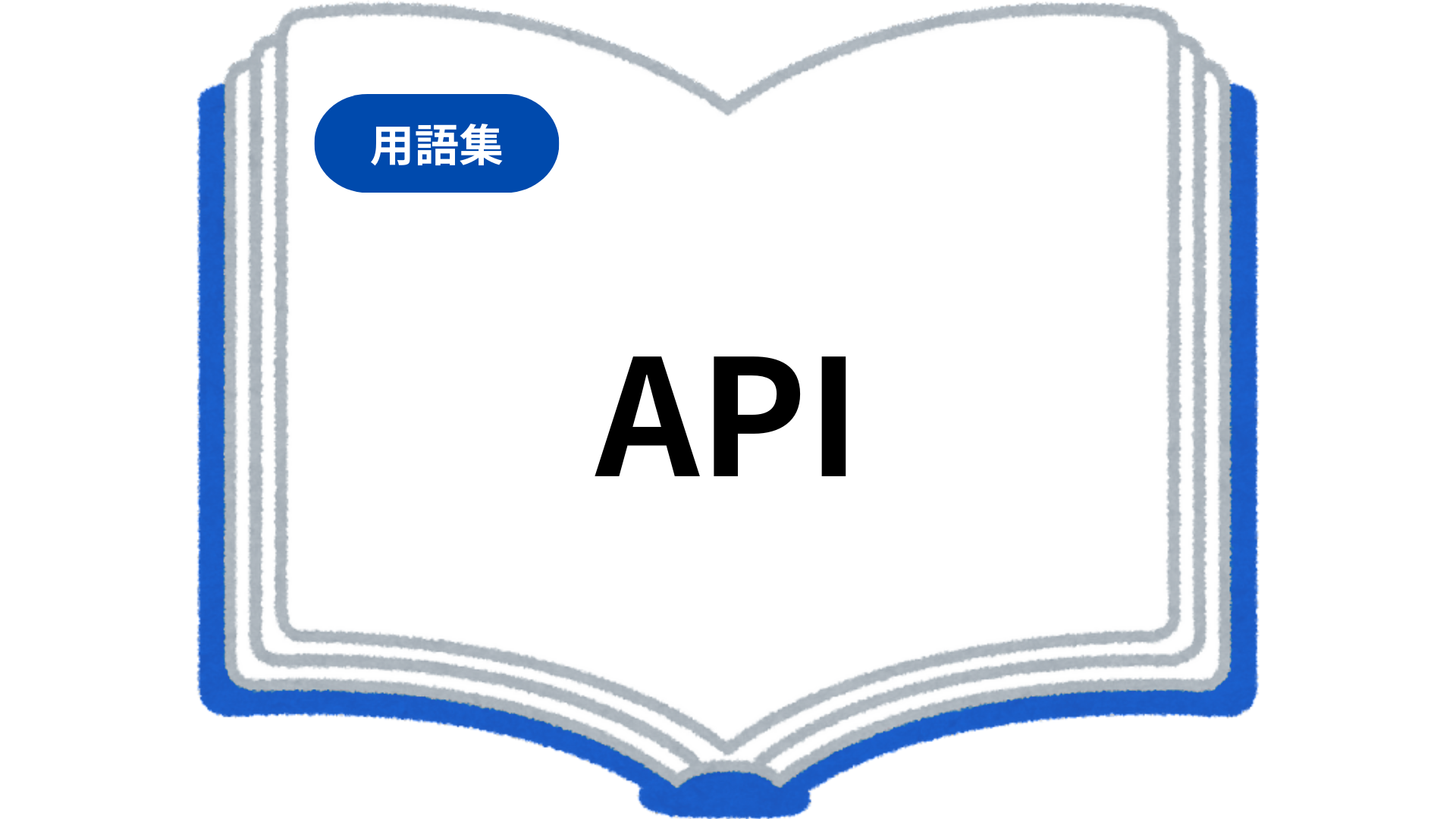
APIとは?初心者にも分かるようにAPIの仕組み・メリット・活用例を解説
API(Application Programming Interface)とは、ソフトウェアやプログラム同士が機能やデータをやり取りするための「接点」を定めた仕様のことです。
「インターフェース」とは、そもそも何かと何かをつなぐ接点や接続ルールのことで、APIは異なるアプリケーションやサービスを繋ぐ役割を果たします。
たとえば、飲食店のWebサイトにGoogle Mapが表示されているのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
このとき、WebサイトはGoogle Mapアプリを開かずとも地図を表示・操作できるようになっています。
この「Google Mapの機能を外部から利用できるようにする仕組み」こそがAPIです。
開発に際してAPIを利用する目的として、「システム間データ連携の開発負荷を削減するため」があげられますが、すべてのケースにおいて開発負荷を削減できるわけではありません。
APIで接続する際、APIで「接続する側」と「接続される側」がありますが、APIはアプリケーション間・業界間で標準化されているわけではないため、双方に開発が必要です。
またAPIが特に効果を発揮するのは、「1対N」の連携が必要な場合です。
例えば、”Googleが1つのAPIを公開しておけば、複数のWebサイトやアプリがそのAPIを使って地図機能を利用できる”等が該当します。
このように、「1(提供者)」がAPIを公開することで、「N(利用者)」との連携コストを抑えることができます。
逆に、「1対1」の限定的な連携では、API開発のコストメリットは小さくなる傾向があります。
APIは、アプリケーションやシステム同士が連携し、機能や情報を共有できるようにするための共通言語のようなものです。
使い方や実装の仕方によっては、開発効率の向上、業務プロセスの自動化、サービスの拡張など、さまざまなメリットをもたらします。
ただし、導入前には「連携の規模」や「実装コスト」をよく検討することが重要です。
目次
よくある質問
API 利用に伴うセキュリティリスクとして、発注者が注意すべき点は何でしょうか?
API はシステム間連携を効率化する一方で、外部との通信口を新たに開くことになるため、セキュリティリスクへの配慮が不可欠です。
発注者が十分に確認・管理しないと、情報漏えいや不正利用に直結する恐れがあります。
1. 認証・認可の不備
不適切な認証方式や権限管理の甘さは、不正アクセスを許す原因となります。
API キーやトークンの管理方法、アクセス制御の仕組みを契約時点で明確にすることが求められます。
2. 通信経路の脆弱性
暗号化されていない API 通信は、盗聴や改ざんのリスクがあります。
HTTPS の利用や、データ送受信時の暗号化要件を仕様に含めることが重要です。
3. 過剰公開や利用制御不足
必要以上に広範な API を公開すると、攻撃対象領域が拡大します。
利用範囲や公開範囲を限定し、リクエスト数の制御(レートリミット)を設定することが望まれます。
4. ログ・監査体制の不備
アクセスログや利用状況を適切に監視していないと、不正利用や異常なアクセスを早期に検知できません。
運用段階での監査体制を設計段階から盛り込むことが必要です。
API 利用におけるセキュリティ対策は、ベンダー任せにせず発注者自身が要件として明確にすることが求められます。
これにより、安全性と利便性を両立させたシステム連携が実現できます。
API の導入コストと開発負荷は、どのように評価・判断すべきでしょうか?
API の導入は利便性や拡張性を高める一方で、開発・運用に伴うコストや負荷も発生します。
発注者は短期的な費用だけでなく、中長期的な効果や運用体制まで含めて評価することが求められます。
1. 初期開発コストの把握
API を自社で新規に開発する場合、設計・実装・テストに相応の工数が必要です。
既存 API を活用できるか、ベンダーが提供する標準 API を利用できるかを確認することで、初期負荷を抑制できます。
2. 運用・保守コストの見積もり
API は導入後もバージョン管理やセキュリティ更新が不可欠です。
運用を継続するための体制や費用を契約時に見込んでおかないと、長期的に想定外のコストが発生する恐れがあります。
3. 拡張性と再利用性の評価
一度構築した API が他システムや将来の拡張に再利用できれば、投資効果は高まります。
逆に個別対応に終始すると、システムが複雑化し保守負荷が増大するため、設計段階での評価が重要です。
4. 外部サービス利用との比較
自社開発よりも外部の API サービスを利用した方が安価・迅速な場合もあります。
導入目的に応じて「自社開発か外部利用か」を比較検討し、費用対効果を判断することが望まれます。
API の導入コストと開発負荷は、単に開発費用だけでなく「初期コスト・運用コスト・拡張性・外部利用の選択肢」を含めて総合的に判断することが重要です。
API 利用のメリットが大きい場面と、小さい場面は、それぞれどのように見極めることが望ましいでしょうか?
API 利用は利便性や拡張性を高めますが、すべてのケースで有効とは限りません。
導入効果を最大化するには、利用の目的や規模、将来的な拡張性を踏まえて判断することが求められます。
1. メリットが大きい場面
・複数システムやサービス間でデータを自動連携させる必要がある場合
・外部サービス(決済、地図情報、認証など)を効率的に利用する場合
・将来の拡張や他システムとの接続を前提とした設計を行う場合
これらでは API の標準化された仕組みを活用することで、開発効率や運用の柔軟性が大きく向上します。
2. メリットが小さい場面
・利用範囲が単一システム内に限定され、外部連携の必要がない場合
・データ量や処理頻度が少なく、手作業や簡易ツールで十分対応できる場合
・ 一度きりの利用で継続的な運用を前提としない場合
こうしたケースでは、API を開発・運用するコストに対して効果が小さく、過剰投資となる可能性があります。
3. 判断のポイント
API のメリットを見極める際は「連携の必要性」「利用頻度とデータ量」「将来の拡張可能性」の3点を基準に検討することが望まれます。
これらを満たす場合はメリットが大きく、逆に限定的な利用であれば他の手段を検討する方が効率的です。
このように、API 利用の是非は場面ごとのニーズや将来性を踏まえた総合判断が必要であり、発注者が投資効果を意識して見極めることが重要です。
あわせてこの用語と記事をチェック