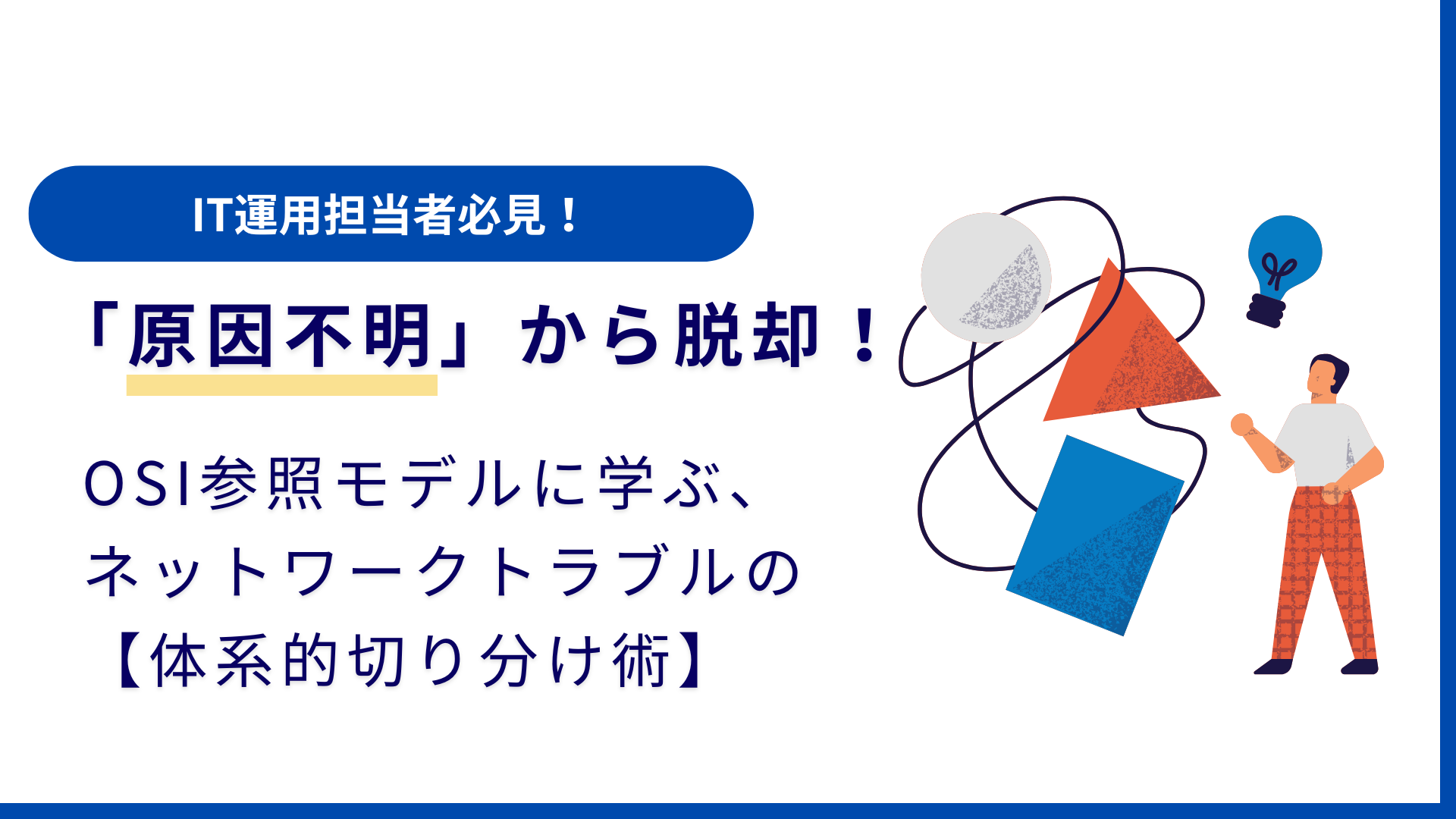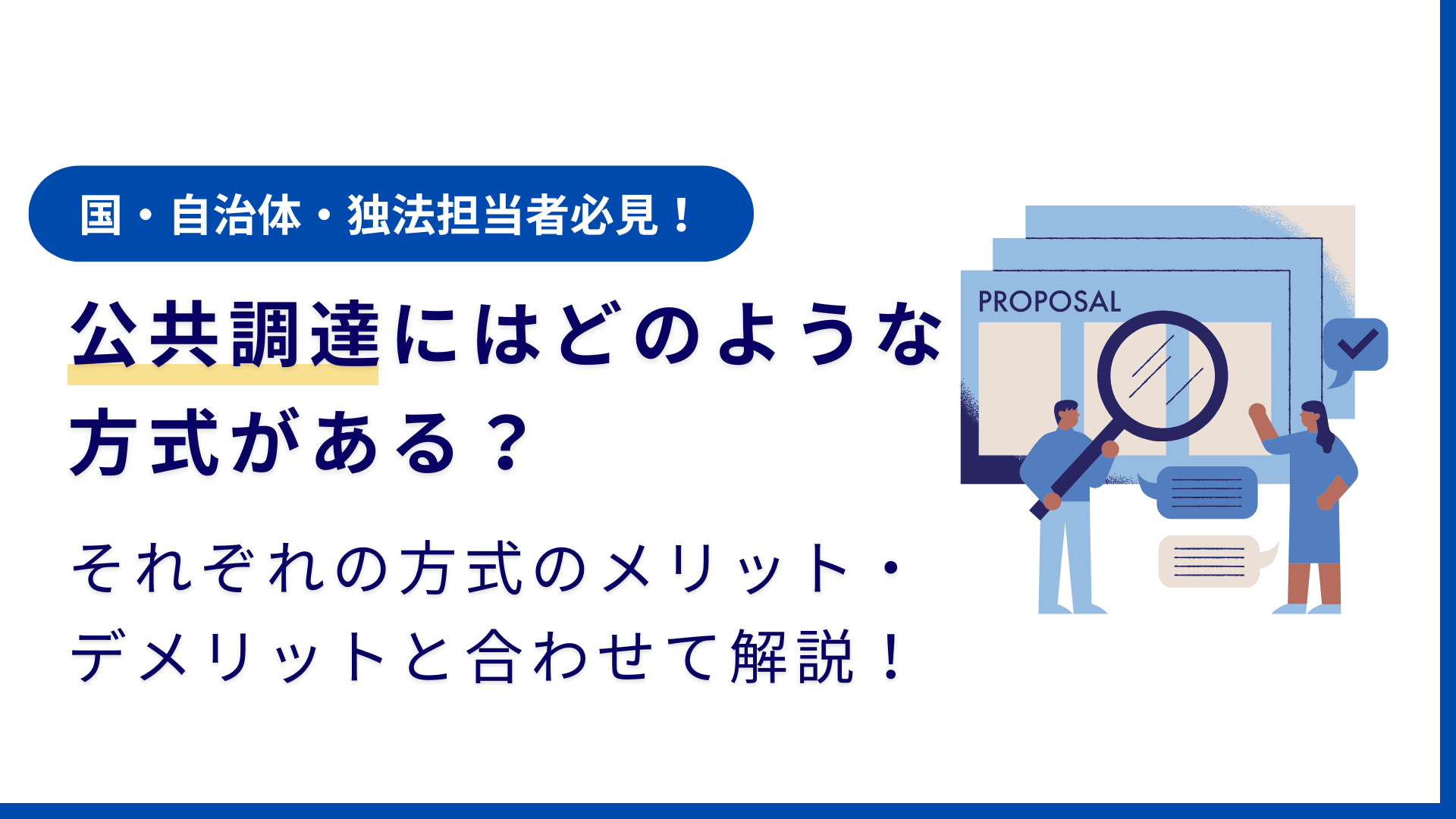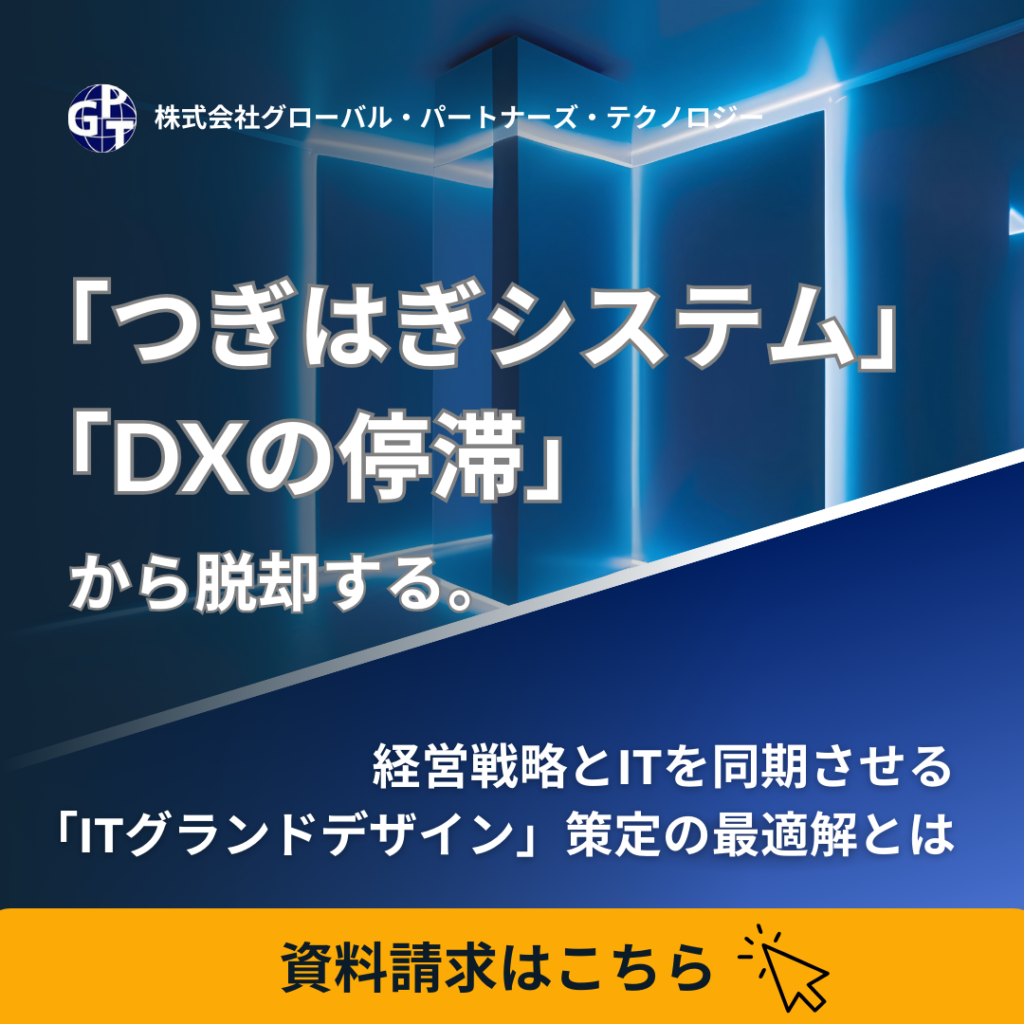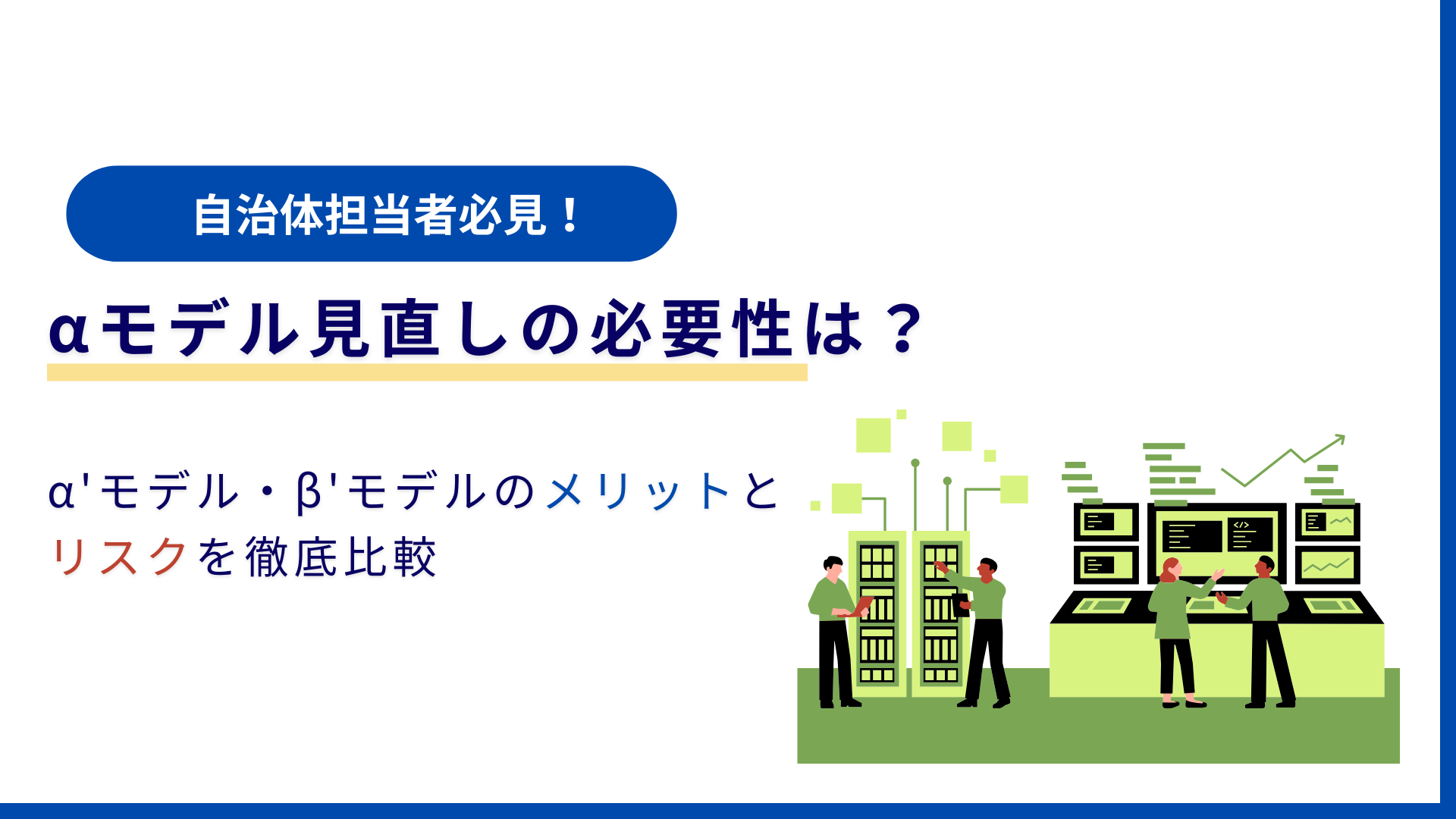
【三層分離】αモデルの見直しの必要性は?α’モデル・β’モデルのメリットとリスクを徹底比較
「外部からLGWANへファイルを取り込む際に、毎回ファイル無害化処理や上長への承認が求められ、手間が多い・・・」
「ファイル無害化の過程で必要なマクロやスクリプトが無効化され、思うように業務を進められない・・・」
「環境ごとに端末やアカウントを切り替える必要があり、パスワード管理や運用の負担が大きい・・・」
セキュリティ対策の制約により業務の本質ではない部分に時間を割かざるを得ない状況が続いており、負担を感じている自治体職員の方も多いのではないでしょうか。
こうした日々の負担は、αモデルでネットワークを構成している場合にどうしても生じてしまう課題です。
これらの課題を抜本的に解消するためには、ネットワーク構成そのものの見直しが必要です。
見直し後のネットワーク構成の選択肢としては、既存の構成を大きく変更せず必要なクラウドサービスだけを安全に使えるようにするα’モデル、さらにインターネット利用に主軸を置いたβ’モデルがあります。
本記事は、現行のαモデルから、各モデルへ移行する際のメリットと、移行に伴う考慮すべきリスクをわかりやすく解説しています。
α’モデル、β’モデルに移行するにあたってどのようなメリットやリスクがあるのかを確かめたい方は、ぜひご一読ください!
目次
三層分離とは?
三層分離は、自治体において庁内の情報系をマイナンバー系、LGWAN接続系、インターネット接続系の3つに分け、それぞれのネットワークセグメントを分離し、セグメント間の通信を必要最小限に制御することによりリスクを局所化し、セキュリティを向上させるための考え方です。
三層分離の背景や構成、各モデルの基本概念を詳しく確認したい方は、こちらの解説記事をご覧ください。
αモデルからβ’モデルに移行するメリット
クラウドサービスの選択肢拡大と調達の自由度
β’モデルでは業務の運用環境がインターネット前提になるため、利用可能なSaaSなどのクラウドサービスの選択肢が大きく広がります。
その結果、機能・価格・サポート・連携方式を比較した上で、自組織の要件に合致した最適な製品を選びやすくなります。
LGWAN環境下やオンプレ環境下の制約に左右されにくくなることで、段階導入や乗り換えの判断が柔軟になり、調達・運用の自由度も高まります。
物理機器の保守工数削減とBCP(事業継続計画)の実効性向上
クラウド側がメインの環境となるため、物理機器(サーバ/ストレージ/仮想基盤)の保守・更改に関わる負担が軽減できます。
また、災害や設備障害、故障時の部品交換や夜間対応といった運用上のコストも相対的に下げられるという副次的なメリットが得られます。
その結果、災害発生時等においても主要業務を継続できる可能性が高まり、BCPの実効性が向上します。
仮想化技術による端末構成の最適化とリモートワーク対応
すでに仮想化技術を用いて業務端末を統合運用している場合は、β’モデルへ移行しても端末のコストメリットという点では大きな変化は生じにくいと考えられます。
一方、業務ごとに複数端末を持ち替えている構成では、β’モデル採用に伴う全体見直しの中で仮想化技術の採用などによる端末構成の最適化を同時に行うことで、運用コスト削減につながる可能性があります。
また、β’モデルではαモデルと比較して、リモートワークに必要な環境を整備しやすくなります。
リモートワーク環境の整備を行った場合、在宅や出先でも扱える業務の幅が広がることにより、非常時の業務継続(BCP)にも寄与します。
αモデルからβ’モデルへ移行する際のリスク
インターネット接続への比重移行によるセキュリティリスク
庁内の閉域ネットワークから、インターネット側に業務の比重が移ることで、フィッシングやパスワードリスト攻撃などによる不正アクセスのリスクが高まります。
とくに利用者教育が不十分な場合、誤操作や情報入力の誘導が起点となって被害が拡大しやすくなります。
セキュリティ運用・監視体制に伴うコスト増加の可能性
業務の比重がインターネット側に移ると、外部接続を前提に日々の運用を継続的に整える必要が生じ、その分、運用コストが増える可能性があります。
また、外部からの攻撃にさらされる接点が増えるため、想定される脅威に継続して対処する体制の維持が必要となり、高水準のセキュリティ運用に要する費用も増加が見込まれます。
利便性は高まる一方で、αモデル時と比べて運用・保守コストが増加する可能性がある点は、あらかじめ考慮しておく必要があります。
αモデルからα’モデルに移行するメリット
既存の構成を維持したままクラウドサービスが利用可能
既存の構成を維持したまま移行できる最大の利点は、移行作業の負担を抑え、庁内の合意形成と周知・教育を迅速に進められることです。
既存の構成から大幅に変更しないため、規程・ルールの再整備は最小限にとどまり、既存資産(機器・契約・手順)を活かせます。
さらに、移行に伴う影響範囲が局所的であるため、移行時に問題が発生した場合に巻き戻しもしやすく、切り替え時のリスクを最小限に抑えられます。
また、この構成により必要なクラウドサービスに絞って庁内利用を開始することができます。
自組織に必要なクラウドサービスをあらかじめ特定し、利用者・利用条件・通信先を定めたうえで限定的に許可することで、従来のαモデルと同等程度のセキュリティレベルを担保しつつ、必要なサービスを利用することができます。
αモデルからα’モデルへ移行する際のリスク
例外通信の管理不備によるセキュリティ整合性の欠如
α’モデルは必要なクラウドサービスに絞って利用を許可する前提であるため、例外通信の管理が不十分だと、全体の整合が崩れるおそれがあります。
許可対象・利用者・通信先などが整理されていないと、障害やインシデント発生時に影響範囲の把握と遮断が遅れます。
その結果、復旧判断や原因特定が長引くといったリスクが発生します。
β’モデルとα’モデル、どちらを目指すべき?
どちらが優れているかではなく、自組織の目指す姿と現在の置かれている状況を比較しながら移行を検討することが重要です。
まずは、どちらのモデルに移行する場合であっても、日々の運用を支える人的リソース・金銭的リソースがどの程度そろっているかを整理し、自組織の現況を把握したうえで、より適合度の高い方を検討するとよいでしょう。
目指す姿として「庁外でも庁内と同様の環境で働けるようにしたい」「クラウド連携を前提に業務を組み替えたい」という目的が明確であれば、β’モデルの採用が適しています。
一方で、「既存の三層分離を保ちながら必要なクラウドに限定して使いたい」「まずは優先度の高い業務だけで効果を出したい」という方針を優先するのであれば、α’モデルの採用が適しています。
いずれの場合も、現時点の体制と目的を踏まえ、自組織の目指す姿から逆算して移行計画を立てることが、最終的に良い結果につながるでしょう。
最後に、それぞれのモデルの違いについて、主なポイントを比較表にまとめましたので、自組織の状況と照らし合わせてご確認ください。
| 比較項目 | α’モデル | β’モデル |
|---|---|---|
| 基本コンセプト |
既存維持
既存構成を維持しつつ、特定クラウドのみ許可
|
クラウド前提
インターネット接続を基本とし、業務を一体化
|
| 移行の難易度 |
低
既存構成を流用するため、変更・影響が少ない
|
高
ネットワーク構成と運用ルールを抜本的に見直す
|
| クラウドの自由度 |
限定的
許可された特定のサービスのみ利用可能
|
高い
様々なSaaS・クラウドサービスを柔軟に選択可能
|
| コストの傾向 |
現状維持+α
既存資産を活かせるが、物理機器の保守は残る
|
運用費シフト
物理保守は減るが、セキュリティ監視等の運用費増
|
| セキュリティ |
境界防御
通信の出入り口を絞って守る
|
ゼロトラスト
端末やID管理を含め、網羅的に守る
|
| 働き方・BCP |
庁内メイン
非常時の柔軟性はβ’に劣る
|
場所を問わない
テレワークや災害時の業務継続がしやすい
|
| 向いている組織 |
・まずは特定業務だけクラウド化したい
・今の環境を大きく変えるリソースがない
|
・庁外でも庁内と同じように働きたい
・将来を見据えてネットワーク構成全体を刷新したい
|
まとめ
β’モデルとα’モデルへ移行する際のメリットとリスクを解説しました。
お話しした通り業務効率を向上させるためにはネットワーク構成の見直しを実施することが望ましいですが、日々の業務に追われており、現況の整理や移行計画の立案までは手が回らないという自治体職員の方々も少なからずいらっしゃると思います。
そのような場合は、専門的知見を持った外部リソースの力を使うことも有効な選択肢の一つです。
IT調達ナビの運営会社であるGPTech(グローバル・パートナーズ・テクノロジー)においても、専門的な知見を持ったコンサルタントによる自治体のネットワーク構成の見直しに関する支援が可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
ここまでお読みいただき、ありがとうございました!