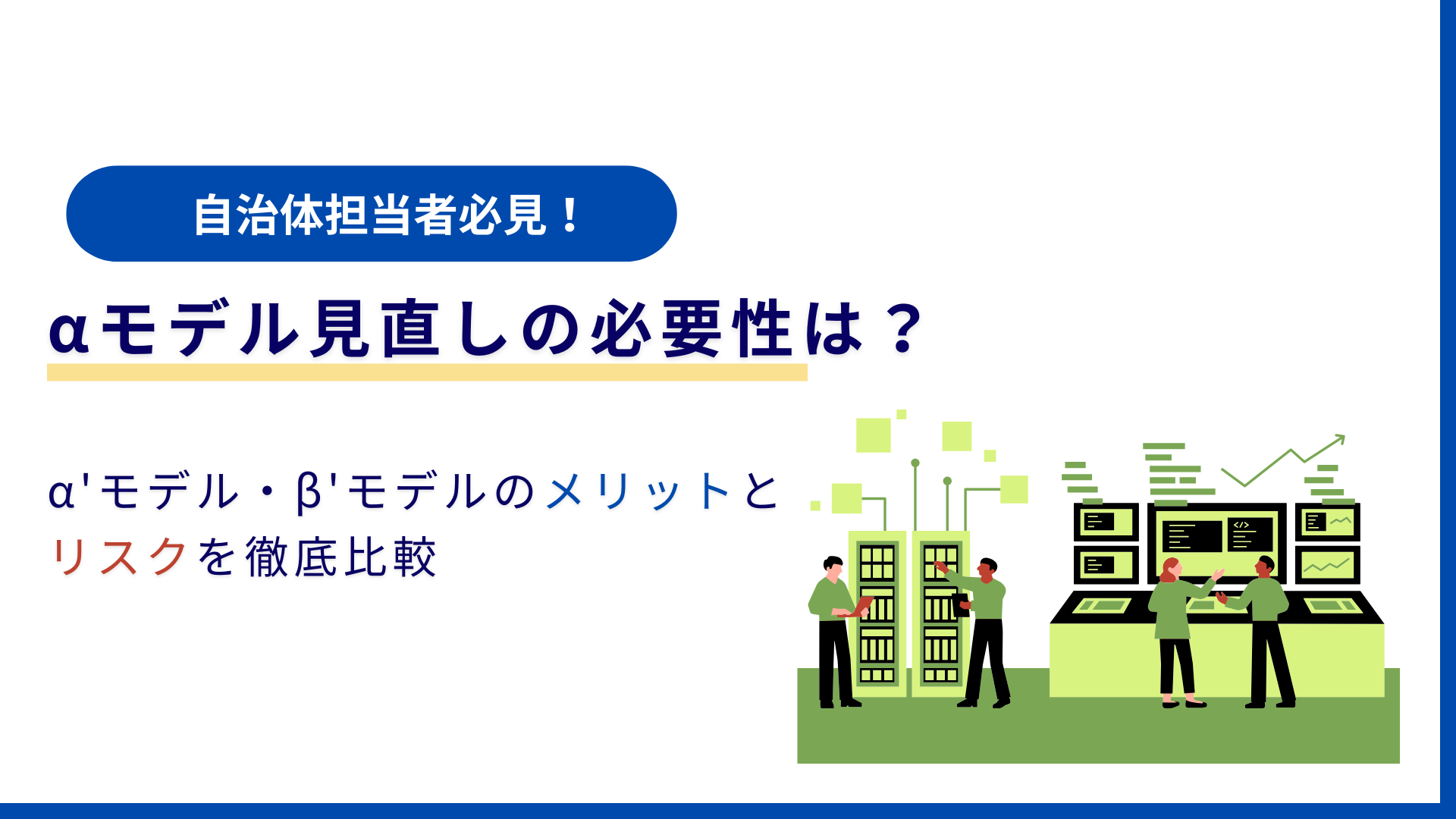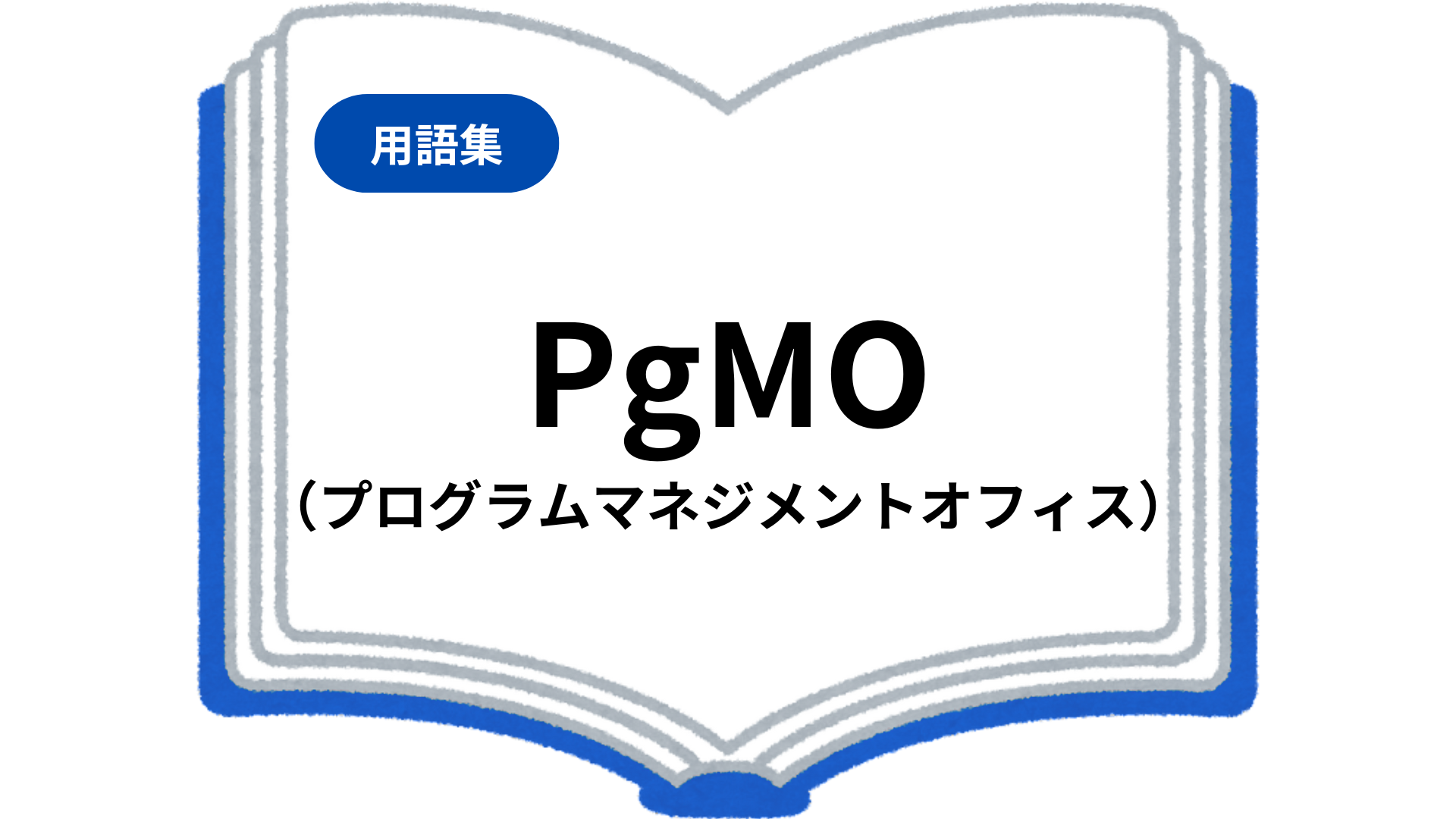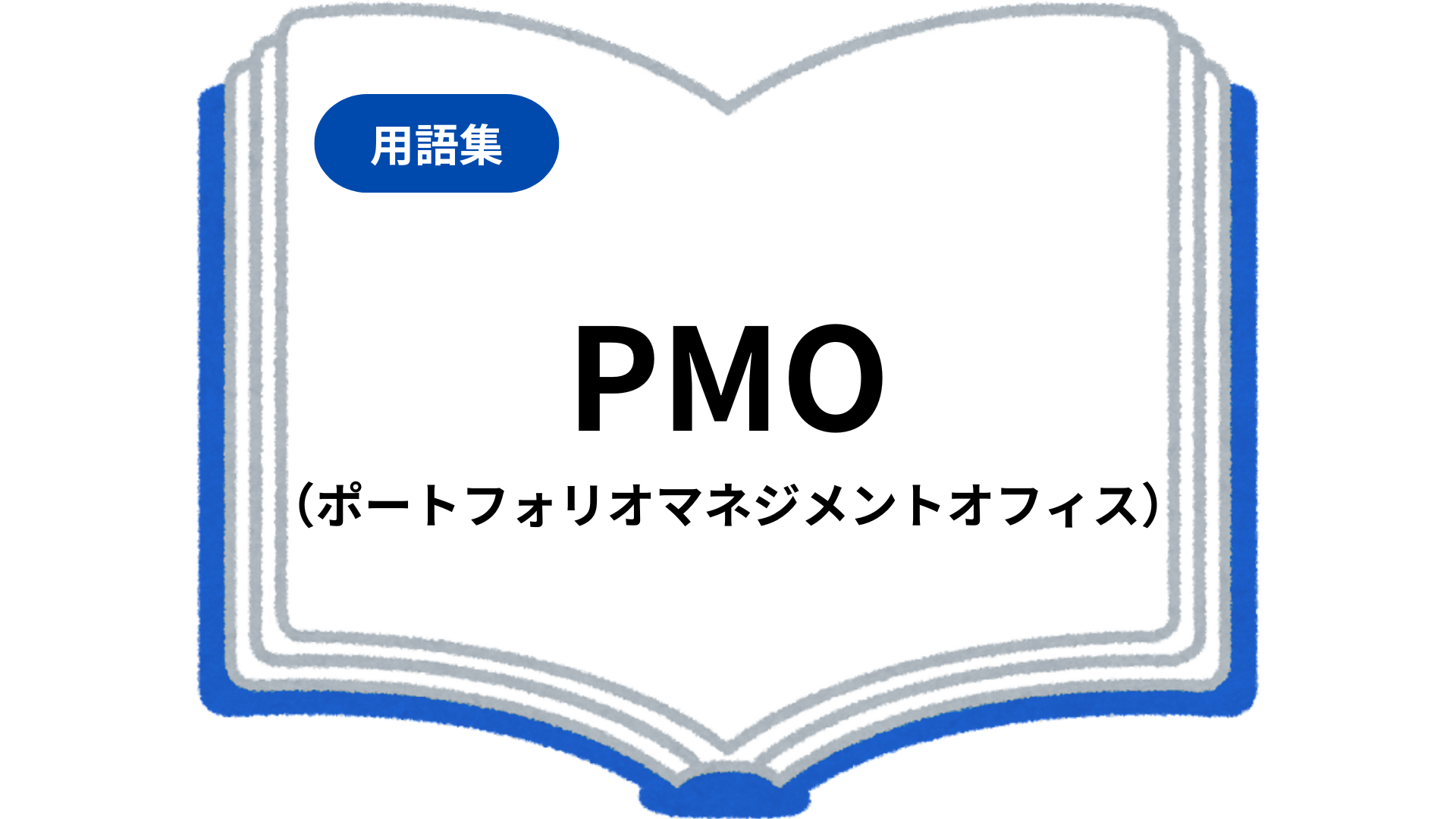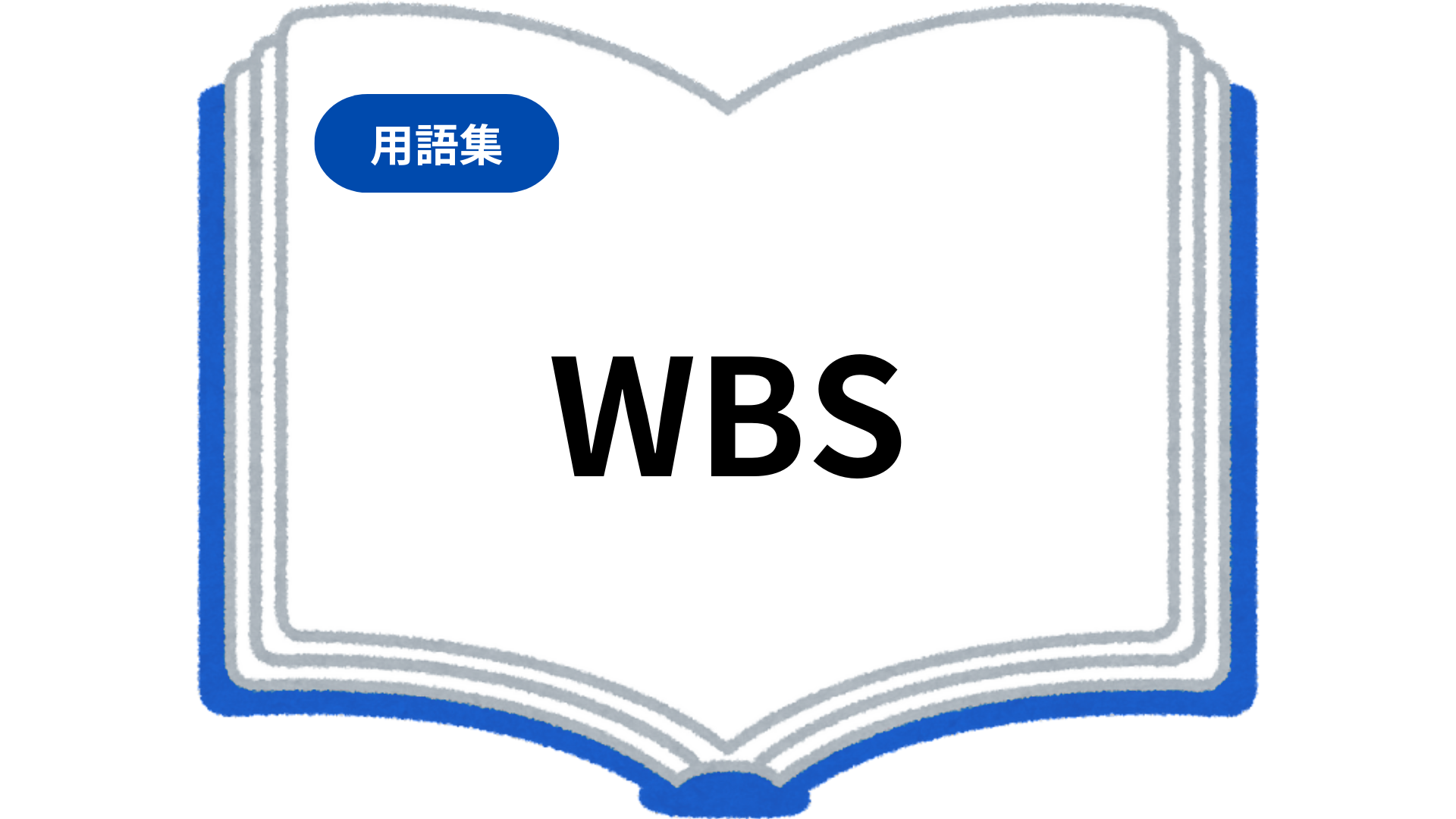
WBS
WBSはWork Breakdown Structureの略でプロジェクト管理のための重要なツールのひとつです。日本語に訳すと「作業分解構造表」ですが、イメージしやすく言うと「タスク一覧表」とになります。
この記事では、WBSについて、その構造やポイント、作成する意義を解説します。
WBSの第1版(ドラフト)は、プロジェクトの目標や成果物の定義、体制などを記述した「プロジェクト実行計画書」や、プロジェクトとして実施する内容、実施しない内容を大きく定めた「スコープ定義書」等をもとに作成します。
その際、最終的な成果として達成すべきモノやコト*を大分類とする方法や、プロジェクトの流れ(プロジェクトの立ち上げ→計画→実行→終結、および全体管理)を大分類にする方法、経営の4資源(ヒト、モノ、カネ、情報)で分類する方法などがあります。
新しい情報システムを導入する場合のWBSは最終的な成果としてのモノやコトを大分類にする方法をお勧めします。
(*新しい情報システム導入の場合、最終的な成果は「システム」だけではなく、「新業務プロセス」「利用者教育」「運用準備」「保守準備」「稼働承認」等も含まれます。)
大分類が決まれば、そこから中分類、小分類と分解(Breakdown)していきます。そして、分解の最小単位は「タスク」(ワークパッケージとも言われる)と呼び、具体的な作業の実行・完了が判断できるレベルです。
WBSでは「MECE(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)」が求められます。つまり、漏れなくダブりなくプロジェクトのタスクを抽出するという意味です。
では、どうすればMECEなWBSができるのでしょうか。
3つのポイントがあります。
①一般的にWBSの第1版はプロジェクトリーダーが作成します。しかし、網羅性を確保するために、第1版ができあがったら、プロジェクトのメンバーと過不足のないようにチェック会を開催して、WBSを充実させましょう。また、第1版作成時からメンバーを集め、ブレインストーミング法で作成する方法もありますし、過去の類似プロジェクトのWBSを参考にするのもよい方法です。
②前述のように大分類法にはいくつかの考え方があります。どれかひとつの大分類法でタスクを抽出した後は、それを別の分類法に組み替えてみてください。そうすれば、足りない項目や重複した項目が見えてきます。
③WBSについては「段階的詳細化」という考え方があります。一度で全てのタスクを網羅することは難しく、大分類、中分類レベルで抽出が停止した後、見えていなかったタスクが明らかになったり、新たなタスクが発生したりした時はWBSを修正して網羅性を高めるという意味です。
WBSのないプロジェクトは考えらず、それほど重要なツールだと言えます。
WBSを作成する意義は以下の通りです。
・プロジェクト組織の内部、外部に対し「プロジェクト全体を見える化する」ことができる
・ガントチャートと併用してプロジェクトの進捗状況を把握することができる
・プロジェクト内部でのコミュニケーションツールとして利用し、問題発生時には対応策検討の資料になる
WBSは日常業務にも応用できるツールですので、是非作成してみてください。
目次
よくある質問
システム発注におけるWBSの目的と効果は何か?
システム発注におけるWBSの目的は、プロジェクト全体を明確に分解し、抜け漏れのない計画と進捗管理を可能にすることです。
これにより、プロジェクトの進捗状況やリスクの把握が容易になり、発注者にとっても透明性と統制が強化される効果があります。
主な目的
1. 作業の明確化と抜け漏れ防止
・システム開発の工程を階層的に分解し、必要なタスクを網羅的に把握する。
・要件定義からテスト、移行、運用までの全体像を可視化することで、発注者自身も必要なタスクの見落としを防げる。
2. 責任範囲の明確化
・各タスクの担当者(発注者・ベンダー双方)を明示することで、責任の所在を曖昧にしない。
・外部委託範囲と発注者側作業(レビュー・承認など)を明確に分けることができる。
3. 契約や予算との整合性確保
・WBSをもとに見積りや契約範囲を明確化でき、追加費用やスコープ逸脱のリスクを抑制する。
4. 進捗管理・品質管理の基盤
・タスクごとに進捗状況を管理できるため、遅延や問題の早期把握につながる。
・各工程の完了条件を明確化することで、品質担保の基準を設定できる。
発注者にとっての効果
・プロジェクト全体像の可視化により、経営層や関係部署への説明が容易になる。
・進捗やコストの透明性が高まり、ベンダーへの依存リスクを低減できる。
・契約管理や成果物確認の基準として活用でき、発注者のコントロール力が強化される。
WBSは、発注者が主体的にプロジェクトを管理するための重要な基盤です。
作業の明確化、責任範囲の整理、契約・進捗管理の指標として活用することで、プロジェクト全体のリスク低減と成功率向上につながります。
WBSを作成・確認する際、発注者が留意すべき事項は何か?
WBSにおいて発注者が留意すべき事項は、作業範囲の網羅性、契約範囲との整合性、責任分担の明確化、成果物と完了基準の妥当性、進捗管理の実効性、リスク対応の適切性です。
これらを確認することで、後工程の認識齟齬や追加コスト発生を防ぐことができます。
主な留意点
1. 作業範囲の網羅性と契約範囲との整合性
・要件定義からテスト・移行・運用開始まで必要な工程が抜けなく分解されているか。
・ベンダーが作成したWBSが契約書やRFPに記載された範囲と齟齬がないか。
・契約外作業が紛れ込んでいないかを確認する。
2. 発注者作業と責任分担の明示
・レビュー・承認・検収といった発注者側の作業がWBSに含まれているか。
・「発注者」「ベンダー」の役割分担が明確で、混在していないか。
3. 成果物と完了基準の妥当性
・各タスクの成果物(設計書、テスト報告書など)が具体的に定義されているか。
・完了条件(承認基準)が曖昧ではなく、検収に耐えうる内容か。
4. 進捗管理の実効性
・タスクの粒度が適切で、進捗を定量的に把握できる単位になっているか。
・契約に定める納期や成果物とWBSの内容が一致しているか。
5. リスクや変更対応の考慮
・作業の依存関係が整理され、遅延リスクを把握できるか。
・変更発生時に修正・再計画しやすい構成になっているか。
WBSはベンダー任せにするのではなく、契約・品質・進捗管理の基盤として発注者が主体的に確認することが不可欠です。
形式的な受け取りではなく、計画の妥当性を検証することで、後工程でのトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
WBSを活用して進捗管理を行う際の発注者のポイントは?
WBSを活用した進捗管理において発注者が重視すべきポイントは、進捗の定量的な把握、成果物に基づく確認、遅延時の早期是正対応です。これにより、単なる進捗報告の受け取りにとどまらず、契約や品質に直結する管理を行うことが可能となります。
発注者の確認ポイント
1. 進捗の定量的な把握
・タスクごとに計画工数や完了率が明示されているかを確認する。
・「何%完了」といった曖昧な報告ではなく、WBS上の成果物や完了基準に基づく数値を重視する。
2. 成果物ベースでの進捗確認
・単なる作業着手状況ではなく、設計書やテスト報告書などの成果物が納品・承認されているかを基準とする。
・成果物が発注者にレビューされて初めて完了と認めることが望ましい。
3. 遅延やリスクの早期把握
・クリティカルパス(遅延が全体に影響するタスク)の進捗を重点的に確認する。
・WBSと実績を比較し、遅延傾向を早期に把握する体制を整える。
4. 是正対応の合意形成
・遅延や未達が発生した場合、ベンダーと是正計画(追加要員投入、優先順位調整など)を協議し、文書化して合意しておく。
・発注者側の承認やレビュー遅延が原因とならないよう、内部の対応計画も明確にする。
発注者は、WBSを単なる進捗表として受け取るのではなく、「成果物を基準にした定量的な進捗管理」と「リスクを前提とした早期是正対応」の観点から主体的に活用することが重要です。これにより、契約・品質・納期を守る確度が高まります。
WBSに作業漏れや曖昧なタスクがある場合のリスクは?
WBSに作業漏れや曖昧なタスクが含まれる場合、スケジュール遅延、追加コスト発生、責任分担の不明確化といったリスクが生じやすくなります。これらは発注者にとって契約や品質に直結する問題となるため、事前に明確化と検証が重要です。
主なリスク
1. スケジュール遅延
・抜け落ちたタスクが後工程で判明すると、追加作業が必要となり、全体スケジュールに影響する可能性がある。
・特にテストや移行工程での見落としは、稼働開始に直接影響を及ぼす。
2. 追加コストの発生
・契約範囲外として扱われる場合、発注者が追加費用を負担せざるを得ないケースがある。
・曖昧なタスクが原因で作業範囲の解釈に差異が生じ、後から見積増額につながるリスクがある。
3. 責任分担の不明確化
・発注者とベンダーのどちらが作業責任を負うかが不明瞭となり、トラブルや責任転嫁が発生しやすい。
・成果物の定義が曖昧だと、検収基準が揺らぎ、品質保証が難しくなる。
4. 品質低下
・不十分なタスク分解により、レビューやテスト工程が軽視され、システム全体の品質確保が困難になる。
WBSにおける作業漏れや曖昧さは、納期・コスト・品質の三要素に直接的な悪影響を及ぼすリスクがあります。発注者は、成果物や責任分担を明確にしたWBSをレビューし、契約や進捗管理の基盤としての精度を担保することが重要です。
________________________________________
あわせてこの用語と記事をチェック
・ガントチャートとは
・情報システム部門担当者が身につけたいプロジェクトマネジメントを丁寧に解説