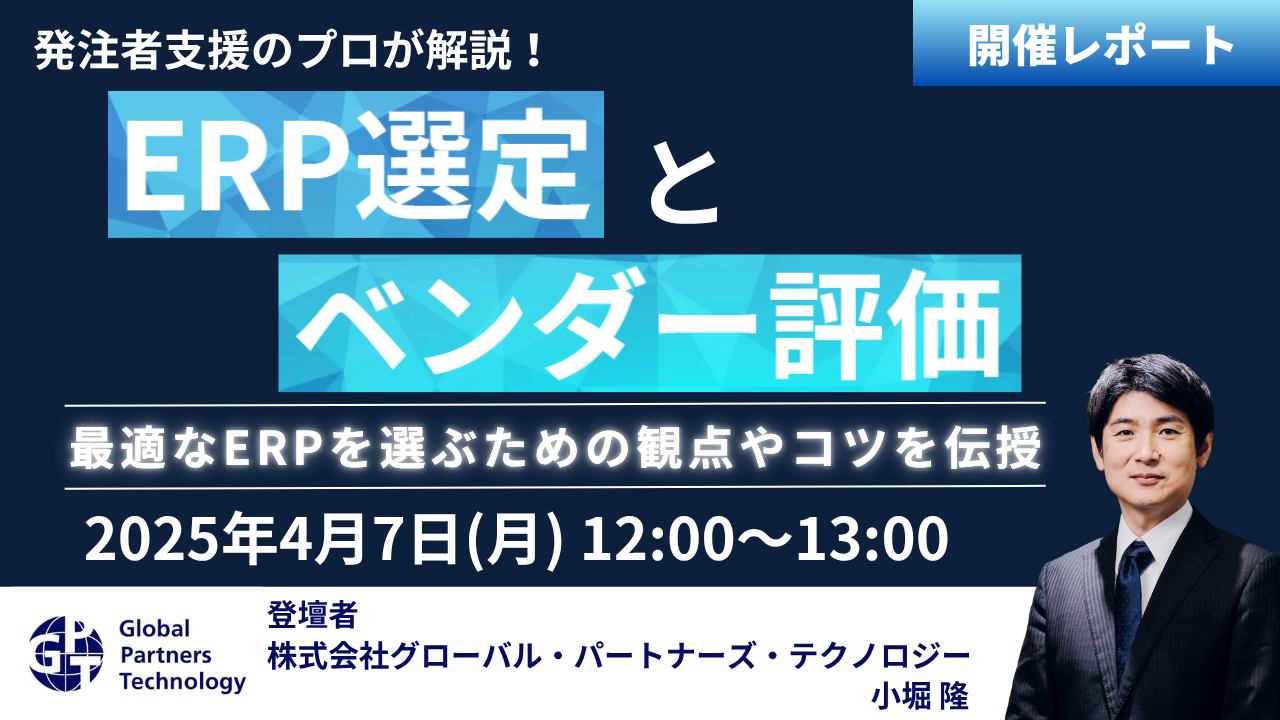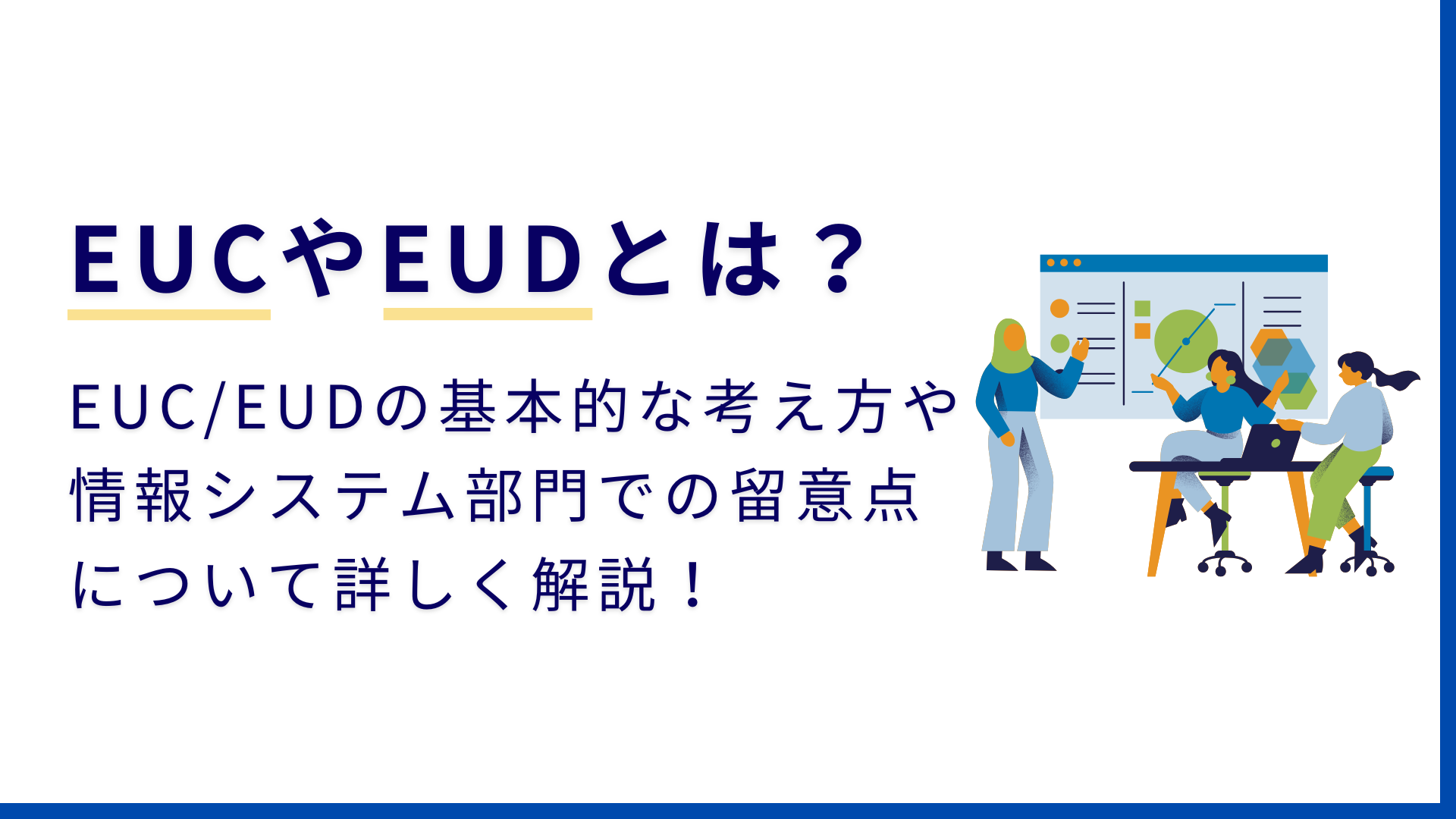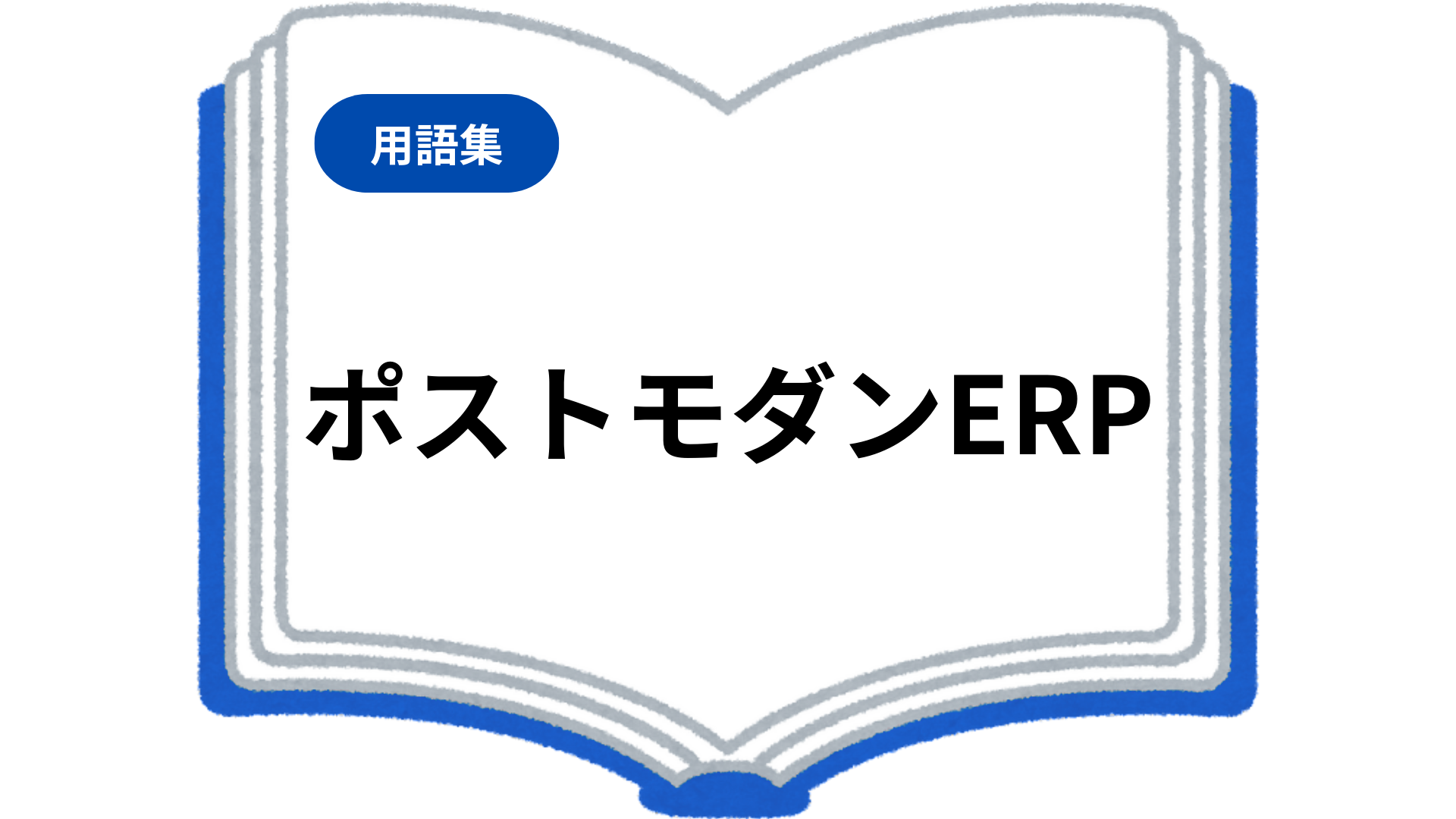
ポストモダンERP
ポストモダンERPとは「次世代型のERP」のことで、具体的には、ERPで実現する機能は主要な業務に絞り、不足する機能はSaaSなどのクラウドサービスを活用して、複数のアプリケーションを連携させて実現する方式のことです。
ERPは「エンタープライズ・リソース・プランニング (enterprise resource planning)」の略称です。企業における各部門の人的資源や情報等のリソースを統合的に管理することによって、企業の経営や業務全般の最適化・効率化を図る考え方、またはそれを実現するシステムのことです。
ERPを導入することで、販売、顧客、在庫、生産、人事・給与、経費等の企業活動におけるデータを一元管理し、経営に活かすことができます。
現在日本に普及している多くのERPのシステムは、すべての業務やデータを管理する統合型のERP(モノリシック型ERP)と呼ばれるものですが、最近はポストモダンERPの考え方が提唱されており、製品も多く出てきています。
従来のモノリシック型ERPでは、企業活動におけるすべての業務に対応する機能が備わっており、一つのデータベースで連携しているため、大規模化しシステム業者依存が加速します。また、保守性が低く、改修のためのコスト・期間が増大しがちであるため、事業活動の足かせになることもあります。
一方で、ポストモダンERPは、個別の領域に特化したシステムを組み合わせ、APIやデータ連携基盤によって連携させることで、上述のモノリシック型ERPの課題は解消され、企業活動におけるデータを一元管理して経営に活かす環境を作ることができます。
参考サイト: https://biz.moneyforward.com/erp/basic/383/
目次
よくある質問
ポストモダンERP導入時に懸念されるリスク(データ分断・ベンダーロックインなど)には何があり、発注者はどう対処すべきでしょうか?
ポストモダンERPは複数のクラウドサービスやアプリケーションを組み合わせて利用するため、柔軟性が高い一方で、データの分断やベンダー依存といったリスクが生じやすいといえます。
発注者は、事前に全体像を整理し、標準化・契約・運用体制の面から対策を講じることが求められます。
主なリスクと対応策
1. データ分断による業務不整合
・リスク:システム間でデータ定義が揃わず、二重入力や齟齬が発生する。
・対応策:マスターデータ管理(MDM)の徹底やAPI連携基盤の標準化を行う。
2. ベンダーロックイン
・リスク:特定ベンダーの仕様や契約に依存し、サービス切替が困難になる。
・対応策:契約段階でデータ移行条件やAPI公開方針を確認し、マルチベンダー戦略を検討する。
3. 運用負荷の増大
・リスク:複数サービスを跨ぐ障害対応や変更管理が複雑化する。
・対応策:発注者側に全体統制を担う体制(PMO等)を設け、共通ルールを策定する。
4. セキュリティリスク
・リスク:クラウドごとにセキュリティ水準が異なり、セキュリティレベルが低いクラウドから全体に影響が及ぶ可能性がある。
・対応策:非機能要件としてセキュリティ条件を明記し、監査・ログ管理を徹底する。
ポストモダンERPは柔軟性の高さが魅力ですが、「分散による複雑性」と「依存による制約」が導入リスクになります。
発注者はデータ・契約・運用・セキュリティの観点で事前に対策を講じることが望まれます。
ポストモダンERPの導入効果を最大化するために、発注者が社内体制面で準備すべきことは何でしょうか?
ポストモダンERPは複数のサービスやモジュールを組み合わせるため、発注者が主体的に統制し、利用部門を巻き込む体制を整えることが不可欠です。
特に「全体統制の仕組み」「業務部門との連携」「人材・スキルの確保」が重要な準備要素となります。
主な準備ポイント
1. 全体統制を担う組織の設置
・PMOや情報システム部門を中心に、複数ベンダーやサービスを統括する役割を明確化する。
・契約管理・進捗管理・リスク管理を一元的に行う体制が求められる。
2. 利用部門との連携強化
・財務・人事・営業など利用部門を早期に巻き込み、要件定義やFit&Gap分析に参加させる。
・「業務をシステムに合わせる」観点を共有し、カスタマイズ依存を避ける。
3. データ管理責任の明確化
・マスターデータ管理(MDM)を担う部署・担当を定め、全社的にデータ品質を維持する。
・部門ごとのデータ入力ルールを統一することも必要です。
4. 人材・スキルの確保
・クラウドサービス、データ連携、セキュリティに関する知見を持つ人材を育成または外部から補強する。
・ベンダーに依存しすぎないために、発注者側にもシステムに関する広範な知見を持った人材が必要不可欠です。
5. 運用・改善の継続体制
・導入後も定期的に利用状況をモニタリングし、改善提案を反映できる仕組みを持つ。
・単発導入ではなく、持続的に最適化する意識が重要です。
ポストモダンERPの成功はシステムそのものよりも、発注者の社内体制整備と統制力に左右されます。
導入前から全体統制組織・利用部門連携・データ管理・人材確保を準備しておくことが、効果を最大化する鍵となります。
既存の基幹システムとの共存や段階的移行を行う際、発注者が考慮すべきポイントは何でしょうか?
ポストモダンERPを既存の基幹システムと共存させながら段階的に移行する場合、システム間の連携や移行計画の整合性が重要です。
発注者は「移行計画の明確化」「データ連携と品質確保」「業務影響の最小化」を軸に検討する必要があります。
主な考慮ポイント
1. 移行計画の明確化
・一括移行か段階的移行かを判断し、ロードマップを策定する。
・段階的移行の場合、並行稼働期間に発生する追加コストや管理負荷を織り込む。
2. データ連携と品質確保
・既存システムと新システム間でのマスターデータの整合性を担保する。
・データ移行時にはクレンジングを行い、不整合や重複を防止する。
3. 業務影響の最小化
・並行稼働中に利用部門で二重入力や業務の混乱が発生しないよう、明確な運用ルールを設ける。
・業務プロセス変更を伴う場合は、利用者教育や説明を徹底する。
4. リスクと切替タイミングの管理
・システム切替時の障害やダウンタイムを想定し、代替手順や復旧計画を準備する。
・年度末や決算期など業務繁忙期を避けたタイミングで移行を行う。
5. 継続的な評価と改善
・段階移行の進捗に応じて評価を行い、問題があれば計画を修正する。
・完全移行後も、基幹システムの役割を再定義し、最適化を進める。
既存システムとの共存や段階的移行では、「計画性」「データ整合性」「業務影響の最小化」が成功の鍵となります。
発注者は移行ロードマップを明確にし、並行稼働期間における混乱を最小化する体制を整えることが望まれます。
あわせてこの用語と記事をチェック