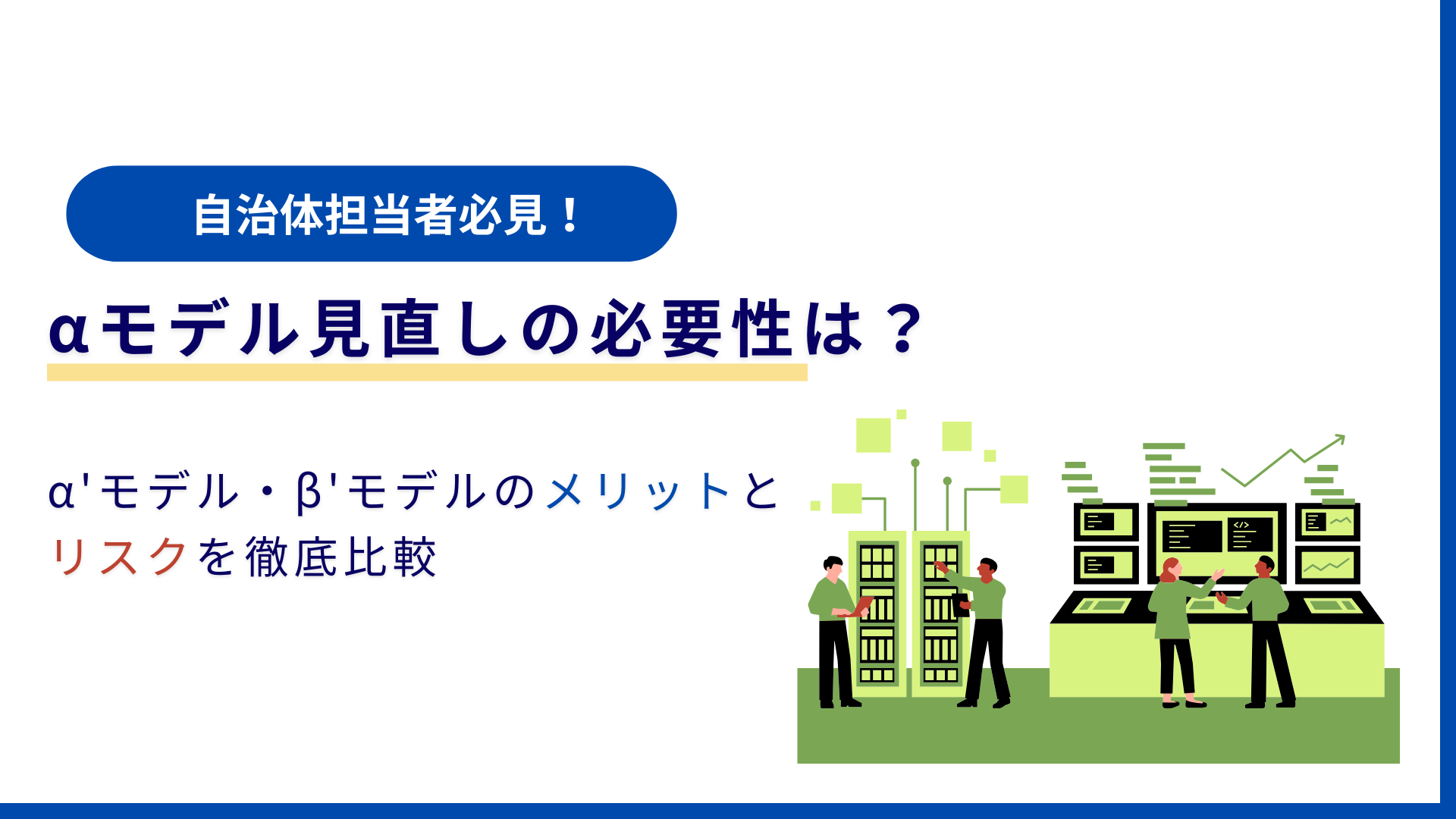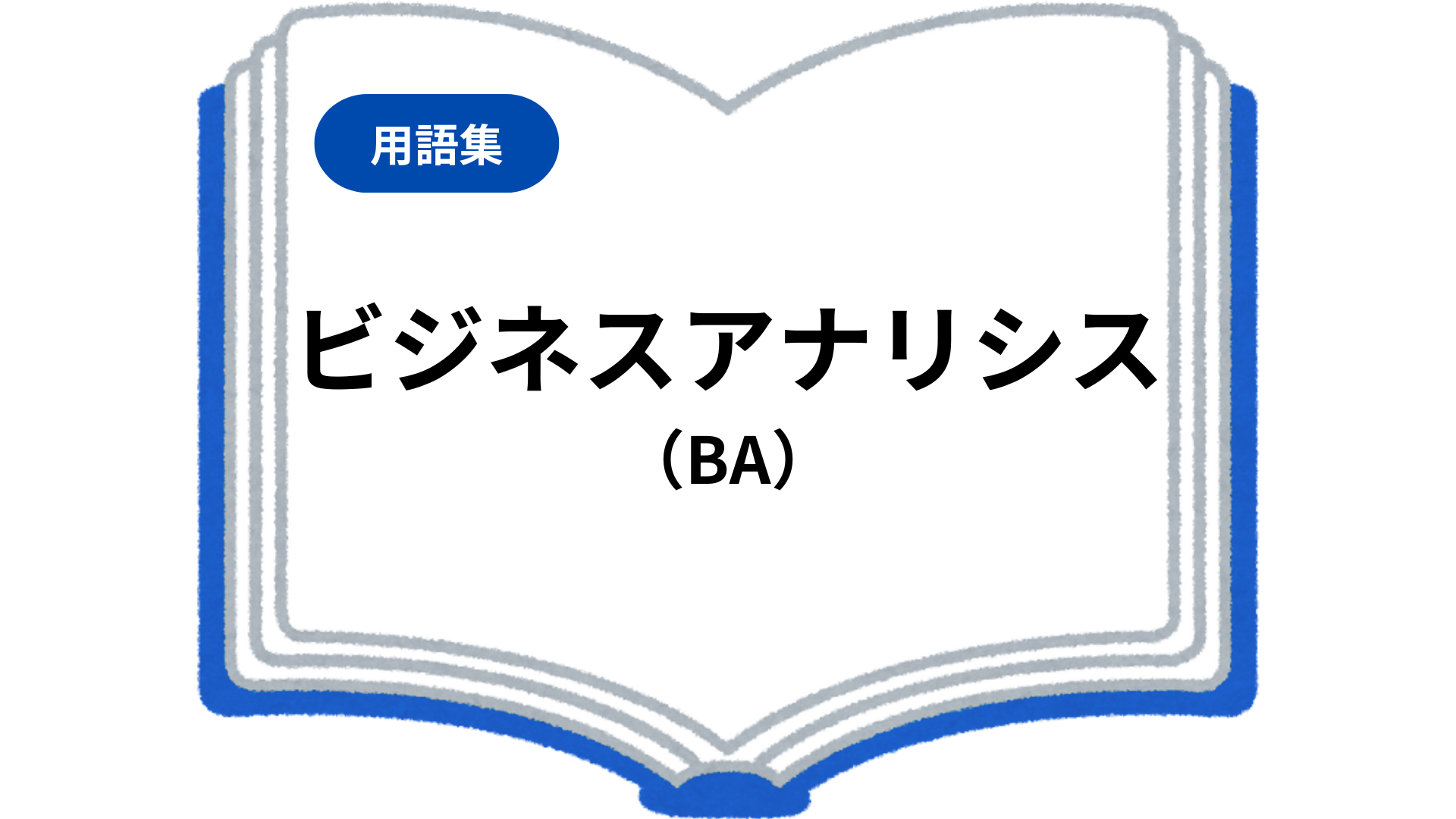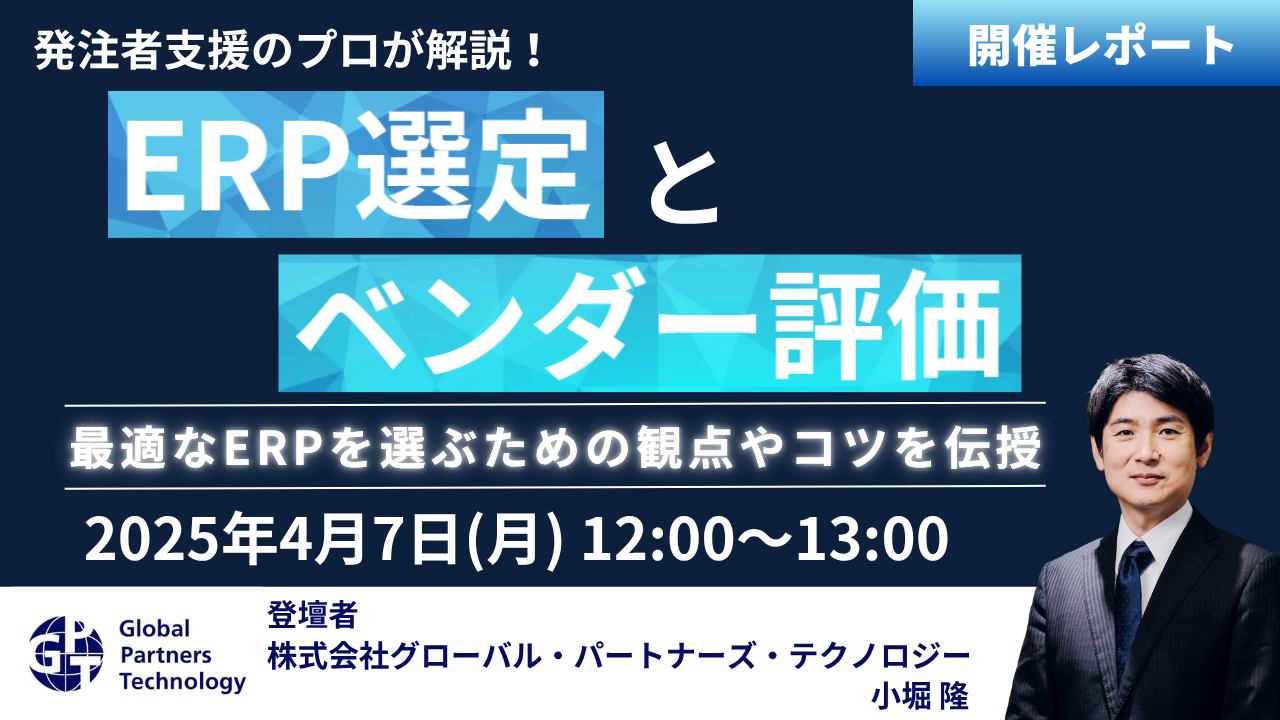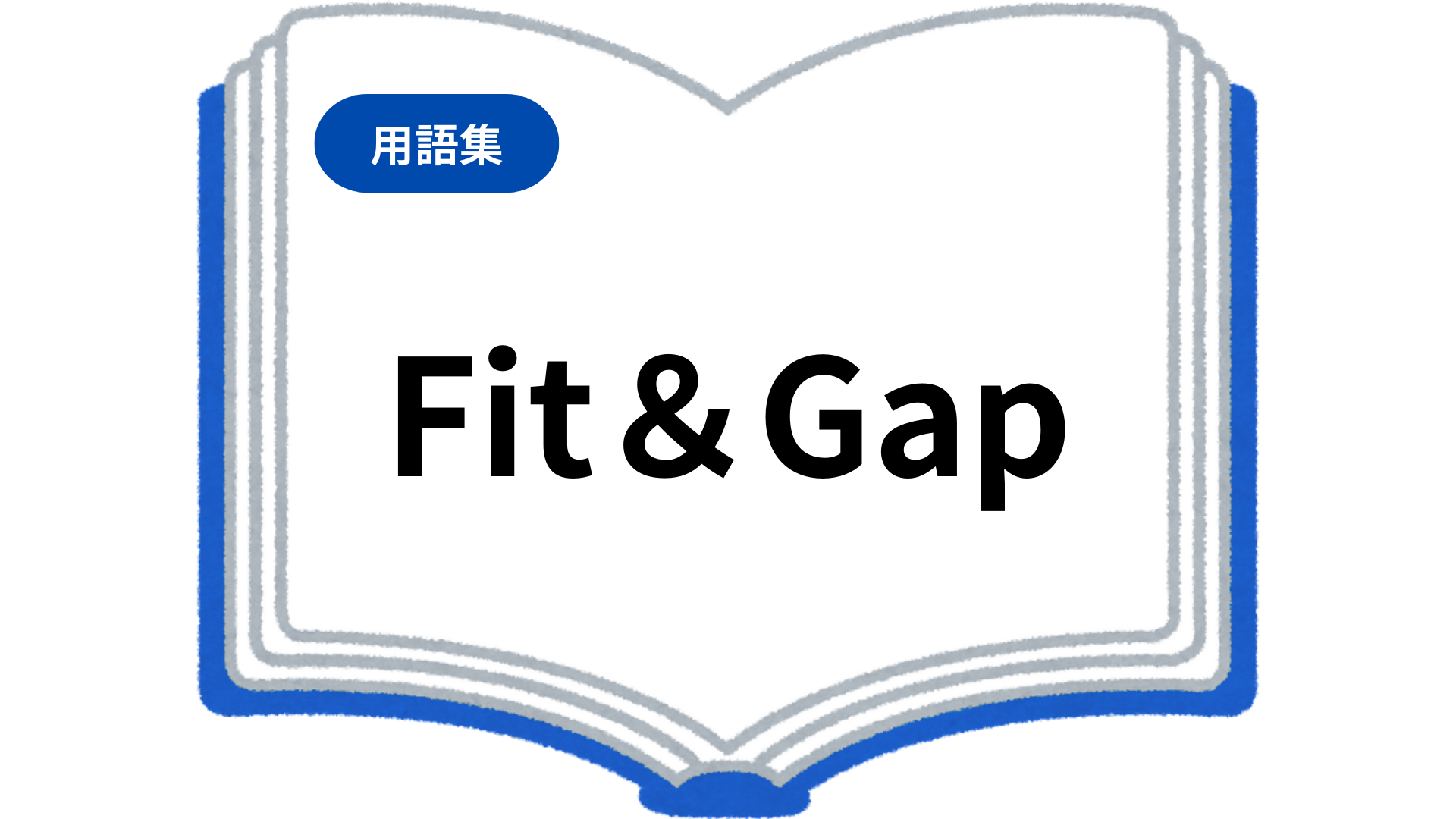
Fit&Gap分析とは?パッケージシステム導入の成功に欠かせない分析手法について解説
Fit&Gap(フィット&ギャップ)とは、パッケージを導入する際に、「パッケージの持つ機能」と「システム利用者の業務プロセスや求めるシステムの機能」を比較して突合し、 どれだけ適合(Fit)し、どれだけズレ(Gap)があるかを明らかする分析手法のことです。
パッケージは、既に完成されたシステムとして製品化されており標準機能は搭載されているため、利用者の業務プロセスや求めるシステム機能とは必ずしも一致しません。
そこで、パッケージとの適合度合いとGapのある部分を確認することで、有力な製品を絞り込むことが可能となります。
Fit&Gapの実施方法としては、「①業務プロセスや新システムに求める機能に対するパッケージの対応有無の確認」→「②対応していない事項(Gap)への対応策検討」という流れになります。
「①業務プロセスや既存システムの機能に対するパッケージシステムの対応有無の確認」では、求める機能を列記した文書上での比較、簡単なデモを実施して求めている機能に合致しているかどうかを確認します。
「②対応していない事項(Gap)への対応策検討」での対応策は、下記の通りです。
- パッケージに追加で開発を行う
- 業務自体をパッケージの機能に合わせて変えていく
- 運用で対処する
なお、候補となり得る全てのパッケージに対し、事細かにFit&Gapを実施することは現実的ではありません。
このことから、株式会社グローバル・パートナーズ・テクノロジーでは、3段階に分けてのFit&Gapの実施を推奨しています。
- 簡易Fit&Gap
簡易Fit&Gapは、深堀検討に値するパッケージをピックアップするために実施されます。実施内容としては、RFIなどによる情報収集を行い、30分~1時間程度の簡単なデモを実施する中で、適合度合いを確認する流れとなります。 - 標準Fit&Gap
標準Fit&Gapは、パッケージを提供する候補会社から精緻な見積もりを取得し、契約条件を固めるために実施されます。候補会社に、パッケージと要求の適合度合いを文書上で整理してもらい、2時間程度のデモの中で確認する流れとなります。 - 詳細Fit&Gap
詳細Fit&Gapは、パッケージを提供する会社と契約後、要件定義フェーズにてパッケージでの実現内容を決定するために実施されます。
このように、複数段階に分けてFit&Gapを進めることで、担当者の負担を減らすことにも繋がります。
Fit&Gapについてより詳細に知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。
パッケージ導入時の要件定義に必要な「Fit&Gap」とは?実施方法やポイントを解説
目次
よくある質問
Fit&Gap分析を効果的に行うために、どのような事前準備や資料が必要でしょうか?
Fit&Gap分析を効果的に行うためには、現行業務を正確に把握し、パッケージシステムの機能と比較できるだけの情報を整えておくことが重要です。
特に「業務要件の明確化」と「標準機能との照合に必要な資料」の準備が不可欠です。
主な準備内容と資料
1. 現行業務の整理
・業務フロー図や業務マニュアルなど、現状の業務手順を可視化した資料。
・業務の入力・処理・出力に関するルールや、部門間の連携方法を明記したもの。
2. 業務要件一覧
・システム化の目的や達成すべき要件を列挙した要件定義書、あるいは要件リスト。
・業務上「必須」と「望ましい」を区別して記載することで、Gap発見時の判断基準になります。
3. 既存システムや関連システムの仕様書
・連携が必要なシステムのI/F仕様、データ項目、処理方式など。
・移行対象となるデータ量や形式の情報も準備しておくと有効です。
4. パッケージ製品の機能一覧
・ベンダー提供の標準機能リストやモジュール仕様書。
・各機能の適用範囲を把握することで、FitとGapの判定がしやすくなります。
5. 評価基準の定義
・「標準機能で代替できるか」「追加開発が必要か」を判断するための評価ルール。
・コスト・運用負荷・将来の保守性などを比較要素として明示しておくことが望ましいです。
Fit&Gap分析の成否は、事前にどれだけ業務要件とシステム機能を整理できるかにかかっています。
業務フロー・要件リスト・既存システム情報・製品機能一覧を揃え、明確な評価基準を持って分析に臨むことで、Gapの発見と対処方針の検討がスムーズに進みます。
Gapが多く発生した場合、発注者はどのような対応策を検討すべきでしょうか?
Gapが多く発生した場合、発注者は「業務をシステムに合わせるのか」「システムを業務に合わせるのか」を冷静に判断する必要があります。
無闇なカスタマイズはリスクを高めるため、まずは業務プロセスの見直しやパッケージ標準機能の活用を優先的に検討することが望ましいです。
主な対応策の選択肢
1. 業務プロセスの見直し(Fit優先)
・業務側をパッケージの標準機能に寄せることで、追加開発や保守コストを抑えられます。
・特に属人的・非効率な業務については、標準化の契機として活用するのが有効です。
2. パッケージのカスタマイズ(Gap解消)
・業務上どうしても外せない要件に限り、追加開発を行う方法です。
・ただし、将来のバージョンアップ対応や保守コストの増大リスクがあるため、必要最小限に留めることが重要です。
3. アドオン・外部ツールの利用
・パッケージ外のアドオン製品や周辺ツールを組み合わせ、Gapを補完する方法です。
・コストや運用負荷を考慮しつつ、柔軟な対応が可能です。
4. 別製品の検討
・Gapが極端に多く、業務やコスト面で調整が困難な場合は、他のパッケージを検討する選択肢もあります。
・Fit率の低さを放置して導入を強行すると、失敗のリスクが高まります。
Gapが多く発生した場合の対応は、「業務を変えるのか、システムを変えるのか」という根本的な判断に直結します。
発注者は安易なカスタマイズに走らず、業務改革・標準機能活用を第一に検討し、それでも満たせない要件にのみ開発や代替策を適用することが成功への近道です。
パッケージの標準機能に合わせるべきか、カスタマイズを検討すべきかはどのように判断すべきでしょうか?
基本的にはパッケージの標準機能に業務を合わせることが望ましいとされます。
カスタマイズは特定の業務要件を満たすための手段ですが、コスト増加や保守負担のリスクが高いため、慎重に判断する必要があります。
判断の主な基準
1. 業務の重要度・固有性
・その要件が業務遂行上不可欠か、法令遵守や基幹業務に直結するかを確認します。
・代替可能な場合は標準機能に寄せる方が望ましいです。
2. コストと効果の比較
・カスタマイズによる追加コスト、将来のバージョンアップ時の対応費用を含めて試算します。
・投資効果が薄い場合は標準機能への合わせ込みを優先すべきです。
3. 運用・保守への影響
・カスタマイズはシステムの複雑性を増し、障害対応や改修時の負担を大きくします。
・長期的な運用を考慮すると、極力標準機能に依拠する方が持続性に優れます。
4. 業務改革の可能性
・現行業務が属人的・非効率な場合、カスタマイズで合わせるのではなく、業務自体を見直す好機とすることが重要です。
・Fit&Gap分析の本来の目的は「Gapを埋める」のではなく「業務とシステムを最適化する」ことにあります。
判断の原則は、「標準機能を優先し、やむを得ない場合のみ最小限のカスタマイズを行う」ことです。
発注者は短期的な利便性よりも、長期的なコスト・保守性・業務効率を見据えて判断することが求められます。