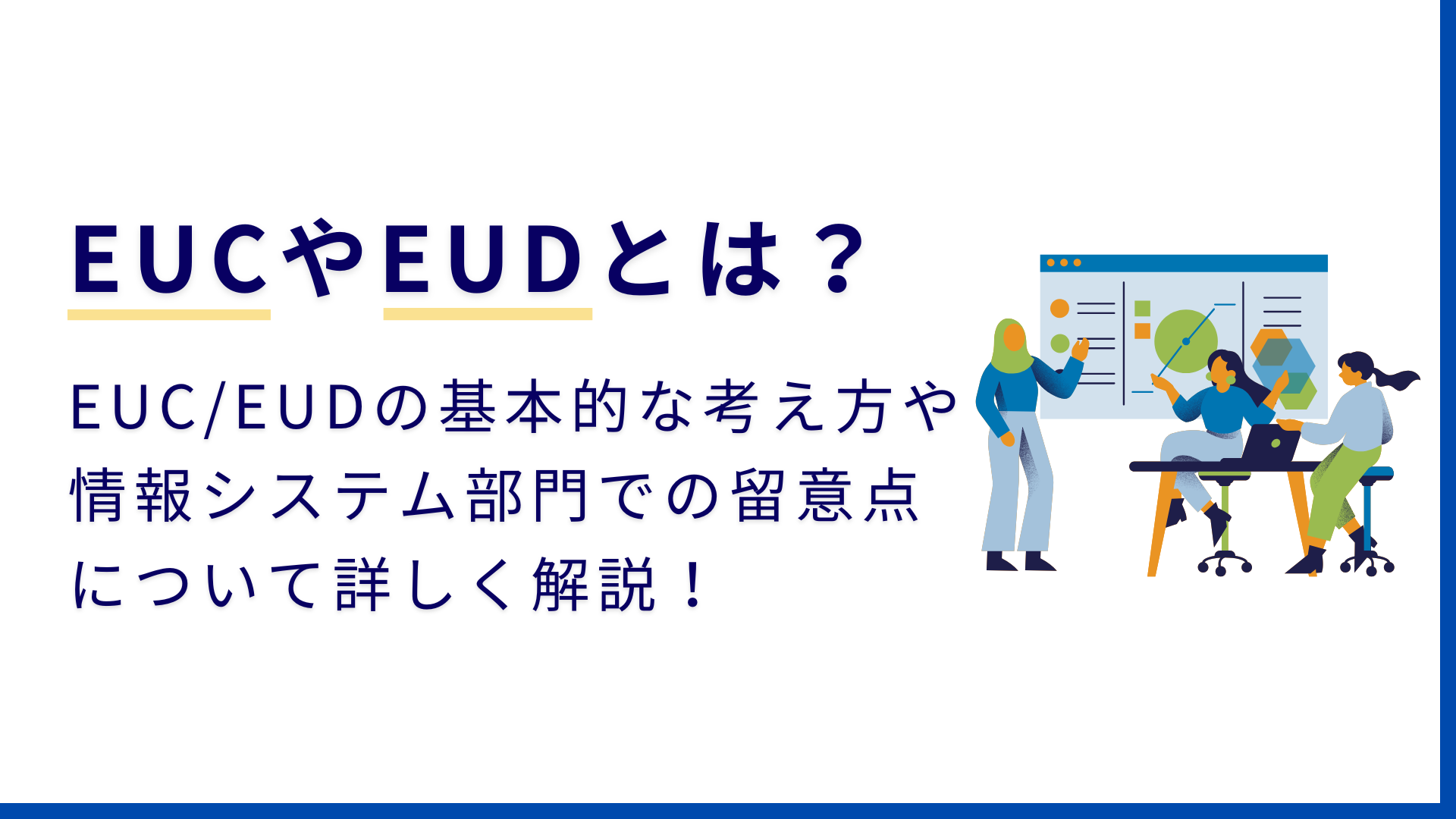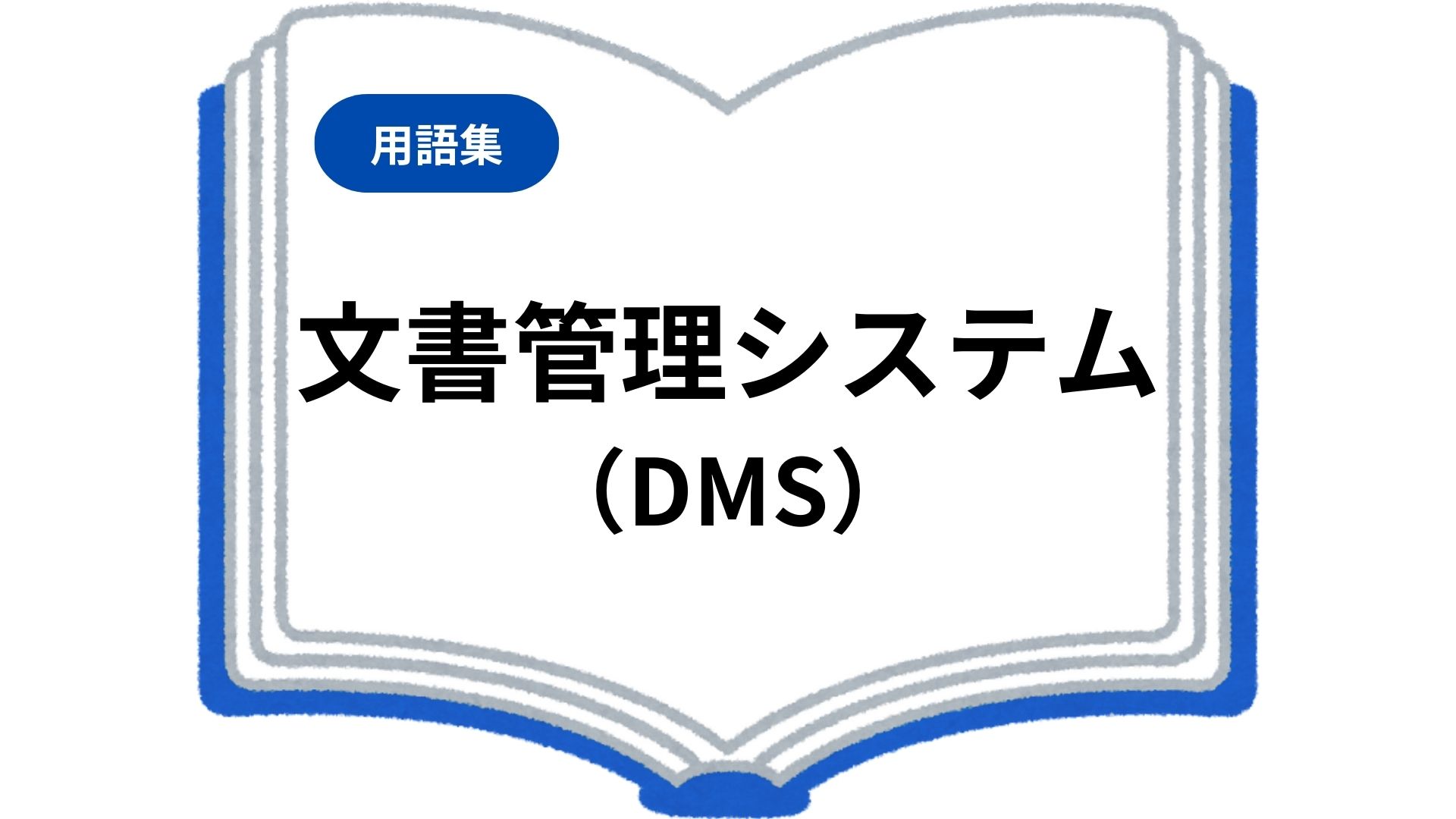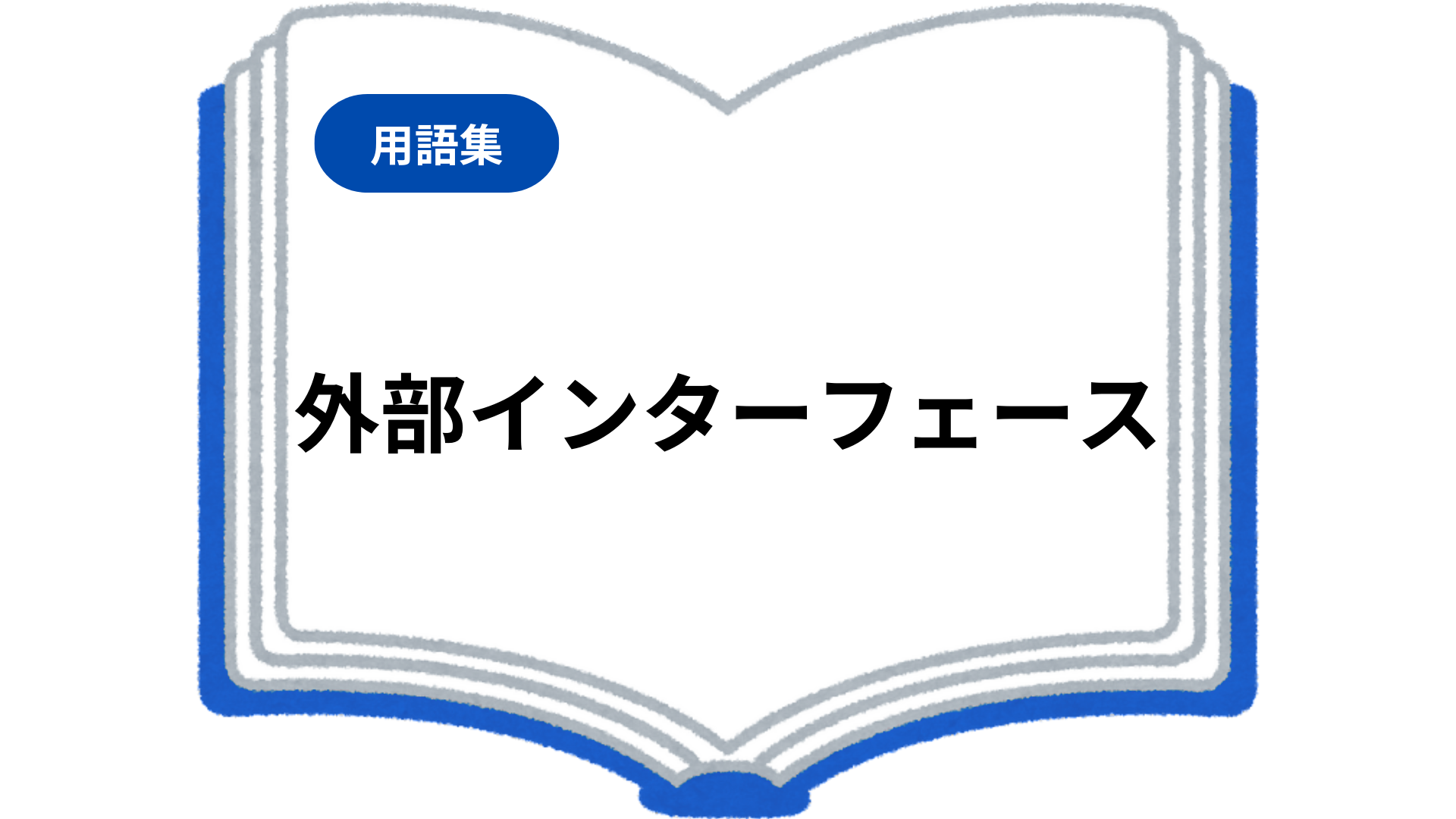
外部インターフェースとは?システム連携に不可欠な基本用語とリスク管理のポイント
外部インターフェースとは、あるシステムやプログラムが他のシステムやプログラムとデータをやり取りするための機能や手段のことを指します。
外部インターフェースが必要な例として、例えば、受注管理システムを新規に開発する場合、外部インターフェースの相手として、販売管理システム、在庫管理システム、顧客管理システムなどが考えられます。
そして、外部インターフェースを通じて、受注情報、在庫情報、顧客情報などがやり取りされるのです。
このように、新規のシステムを開発する際には、必ずと言っていいほど、既存システムとの外部インターフェースが必要になります。
外部インターフェースには、次のようなリスクが内在しています。
・分散型のコンピュータ環境が進めば進むほど接続数が多く、複雑になる
・それぞれのシステムでのデータの定義や表現方法、データ形式が違う
・データの送り側と受け側でデータ処理のタイミングが違う
・一方のシステムの変更時には他方も影響を受け、修正が必要になる
・(社内システムと社外システムを接続する場合)WANやインターネットが介在し複雑性が増す
・外部インターフェース方式がシステムごとに違う*
・障害が発生した際に責任の所在がわかりにくい 等
(*外部インターフェース方式としては、API、FTP、OSレベルでのファイルコピー、データベースリンク、SOA等があります)
これらの原因から発生する障害の防止、障害時の迅速な復旧のために「ドキュメントの整備」は不可欠です。
外部インターフェースとして接続するシステムの担当者同士が話し合い、
全体を一覧化した「外部インターフェース一覧表(外部インターフェース名称、送信側/受信側の接続システム、接続方法、接続サイクル、接続タイミング、データ形式等を記載する)」や、それらを図にした「外部システム関連図」と、外部インターフェースごとに説明した「項目説明書(対象データの項目名、項目説明、長さ、データ形式等を記述する)」や「処理説明書(送受区別、データ量、レコード長や処理内容説明を記述する)」が必要です。
これらのドキュメントによって、新システム開発関係者と既存システムの関係者間、あるいは、システム開発の発注側企業と受注側企業間が外部インターフェースに関する共通理解を持ち、認識の齟齬を防ぐことができます。
目次
よくある質問
外部インターフェースとAPIはどう違うのですか?
外部インターフェースは“外部システムとの接点全般”を指す広い概念であり、APIはその中の一つの手段(技術)です。
用語の位置づけの違い
・外部インターフェース
他システムとのデータ授受や機能連携を行うための接続仕様の総称です。ファイル連携(CSV/XMLなど)やAPI、バッチ処理、EDIなど複数の手段や形式を含む概念で、システム外部との「やり取りの窓口」の定義全体を指します。
・API(Application Programming Interface)
外部システムとプログラム同士がデータや処理をやり取りするための標準化された通信手段(インターフェースの一種)です。RESTやSOAPなどの通信形式で、主にリアルタイム処理や疎結合な連携に活用されます。
「外部インターフェース」は他システムとの接続手段全体を指す上位概念であり、「API」はその中に含まれる具体的な接続方式の一つです。両者は同義ではなく、目的や手段に応じて使い分ける必要があります。
システム調達や仕様書作成時には、外部インターフェースの全体像を整理したうえで、APIの有無や形式を個別に明記することが重要です。
外部インターフェースのトラブルはどのように検知・対応すればよいですか?
ログ監視やアラート通知を活用し、異常発生時には早期に接続元・データ形式・処理ステータスを確認する体制が必要です。
主な検知方法
・ログ監視の自動化
外部インターフェースの実行結果(送信/受信の成否、件数、エラー内容など)を記録するログを定期的に監視することが基本です。異常検知時に自動アラート(メール通知やダッシュボード連携)を行う設定が推奨されます。
・処理ステータスの可視化
インターフェース処理の正常/失敗を可視化する管理画面を設け、エラー内容をリアルタイムに把握できる設計とすることで、担当者による早期の一次対応が可能になります。
対応の基本ステップ
・障害発生の把握
自動アラートや業務担当者からの報告で異常に気づいた段階で、処理ログやエラーメッセージを確認します。
・接続先・通信経路の確認
ネットワーク障害や相手システムの稼働状況、認証エラーなどの外的要因を切り分けます。
・送受信データの妥当性検証
データ形式の不一致(項目追加・桁数違いなど)やファイル破損の有無を確認します。
・リトライまたは一時的な手動対応
原因が限定されており修正可能な場合は、リトライ処理や一時的なファイル手動送付などで業務を継続します。
・恒久対応(設定変更・仕様調整)
再発防止の観点から、仕様変更・異常値チェックの追加・相手先との取り決め見直しなどを実施します。
外部インターフェースは、他システムとの接続に依存するため、異常検知の仕組みと初動対応の体制整備が不可欠です。
ログ監視や可視化により早期発見を行い、障害発生時には、接続・通信・データの3点から要因を切り分けることが、安定運用への第一歩です。
外部インターフェースの整備が遅れると、業務にどのような支障が出ますか?
システム間の連携不全により、データの二重入力や処理遅延、属人化が発生し、業務効率とデータの信頼性が著しく低下します。
主な影響
1. データの二重入力・転記作業が発生する
外部インターフェースが整備されていない場合、他システムとの連携ができず、職員が別システムへ手作業で情報を入力する必要が生じます。これにより、作業負荷の増加と入力ミスのリスクが高まります。
2. 業務処理が遅延・滞留しやすくなる
インターフェース未整備の状態では、日次・週次などの定型処理においてデータ授受のタイミングが合わず、業務フローが停止するケースがあります。特に締め処理や報告業務では大きな支障となります。
3. 属人化・ブラックボックス化が進む
手動連携や暫定対応が常態化すると、一部職員に業務ノウハウが集中し、引継ぎが困難になるなどのリスクが発生します。担当者の退職や休職により業務が停滞する恐れもあります。
4. 組織全体のデータ整合性が損なわれる
連携が不十分な状態では、部門間で異なる情報が存在したり、最新版のデータが共有されないなど、全体最適が損なわれます。これは意思決定やレポート業務において重大な問題となりえます。
外部インターフェースの整備は、業務効率化だけでなく、正確な情報共有や組織的意思決定の前提として不可欠です。
連携基盤が未整備のままでは、現場の業務に負担がかかるだけでなく、全体最適を阻害し、将来的なシステム統合・DXの妨げにもなり得ます。
あわせてこの用語と記事をチェック
・まずは全体像から!システム発注者側の目線でシステム導入時の業務を解説
・パッケージ導入時の実装作業とその中でも発注者側が実施すべきこととは