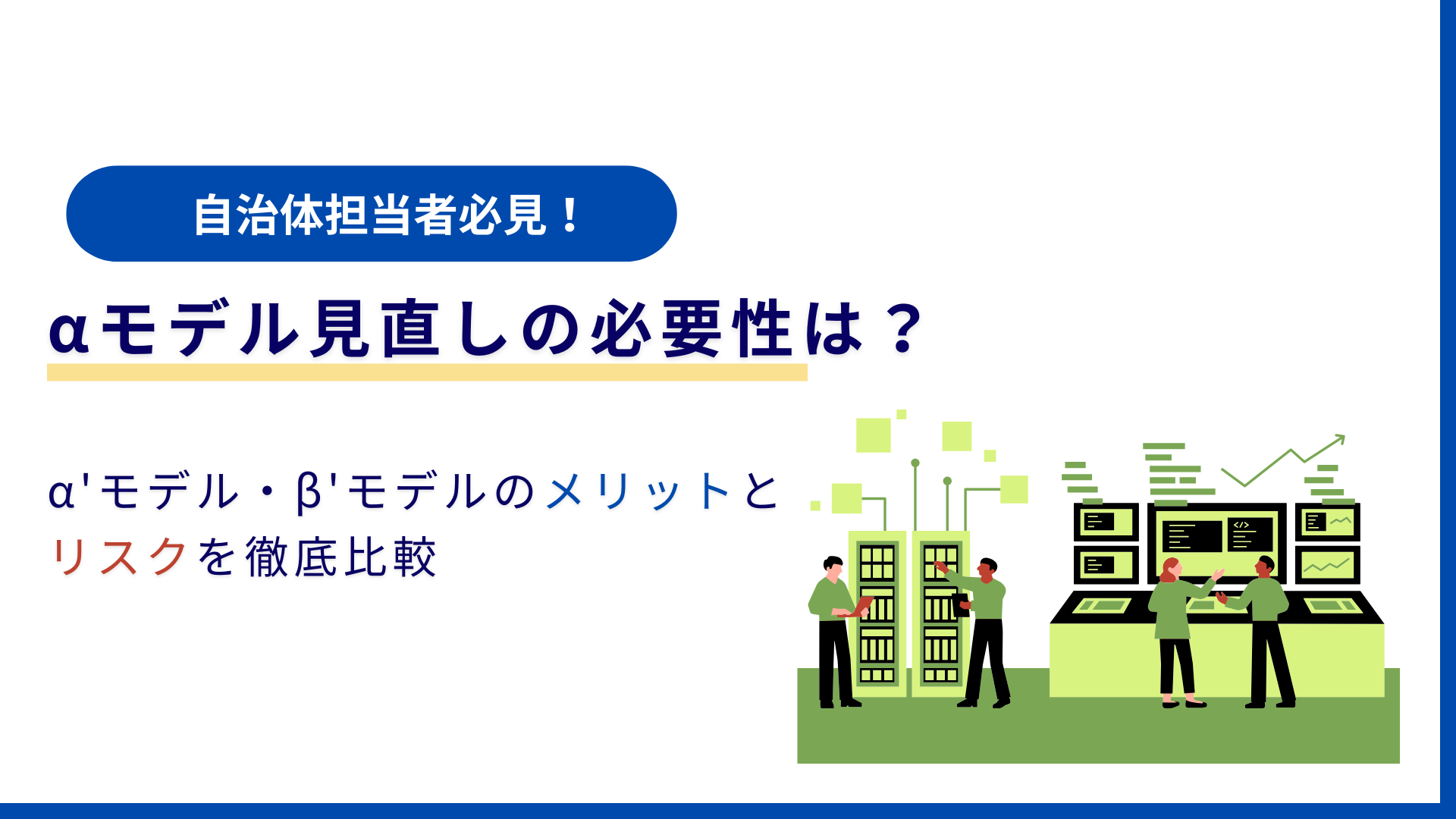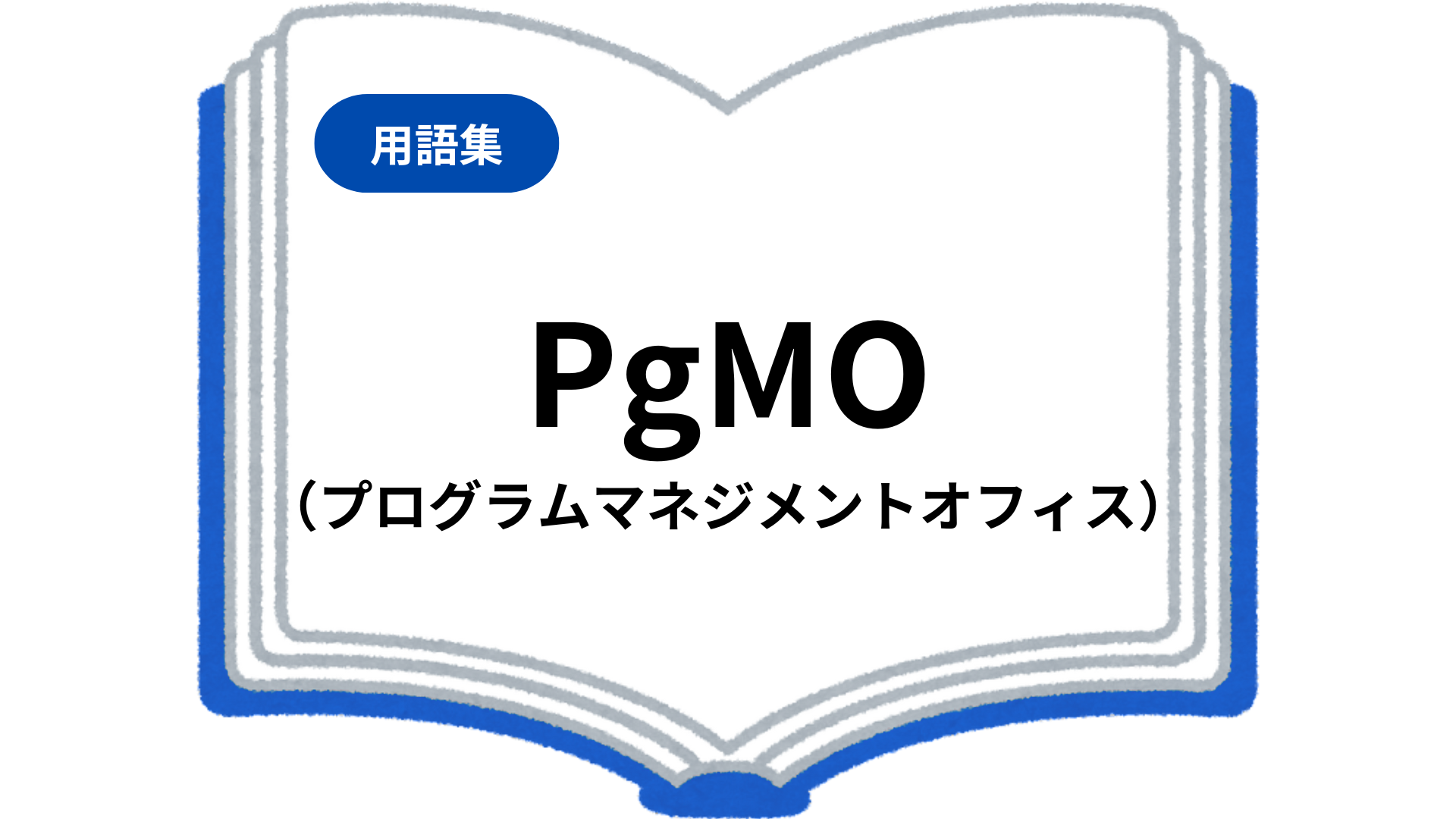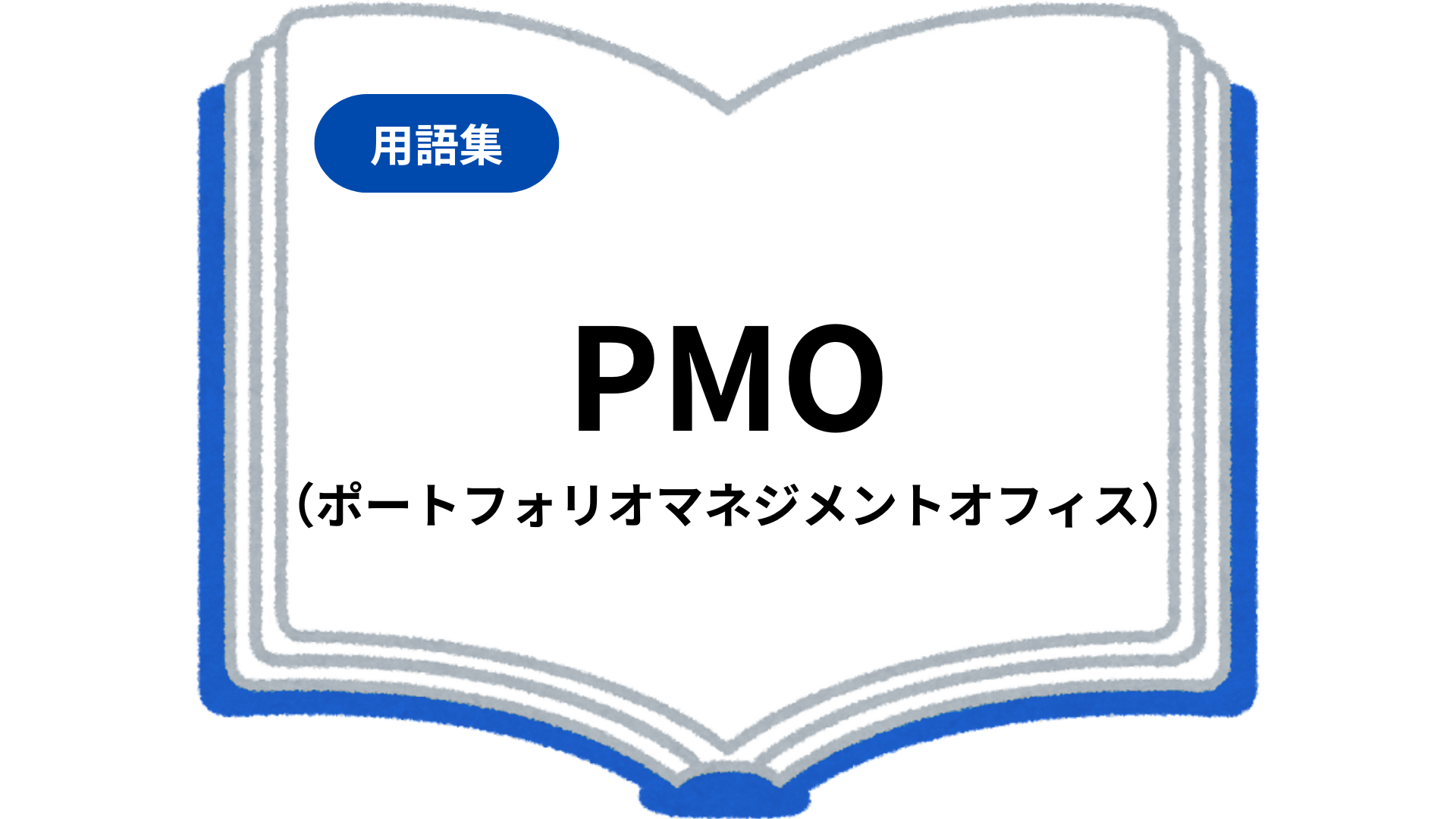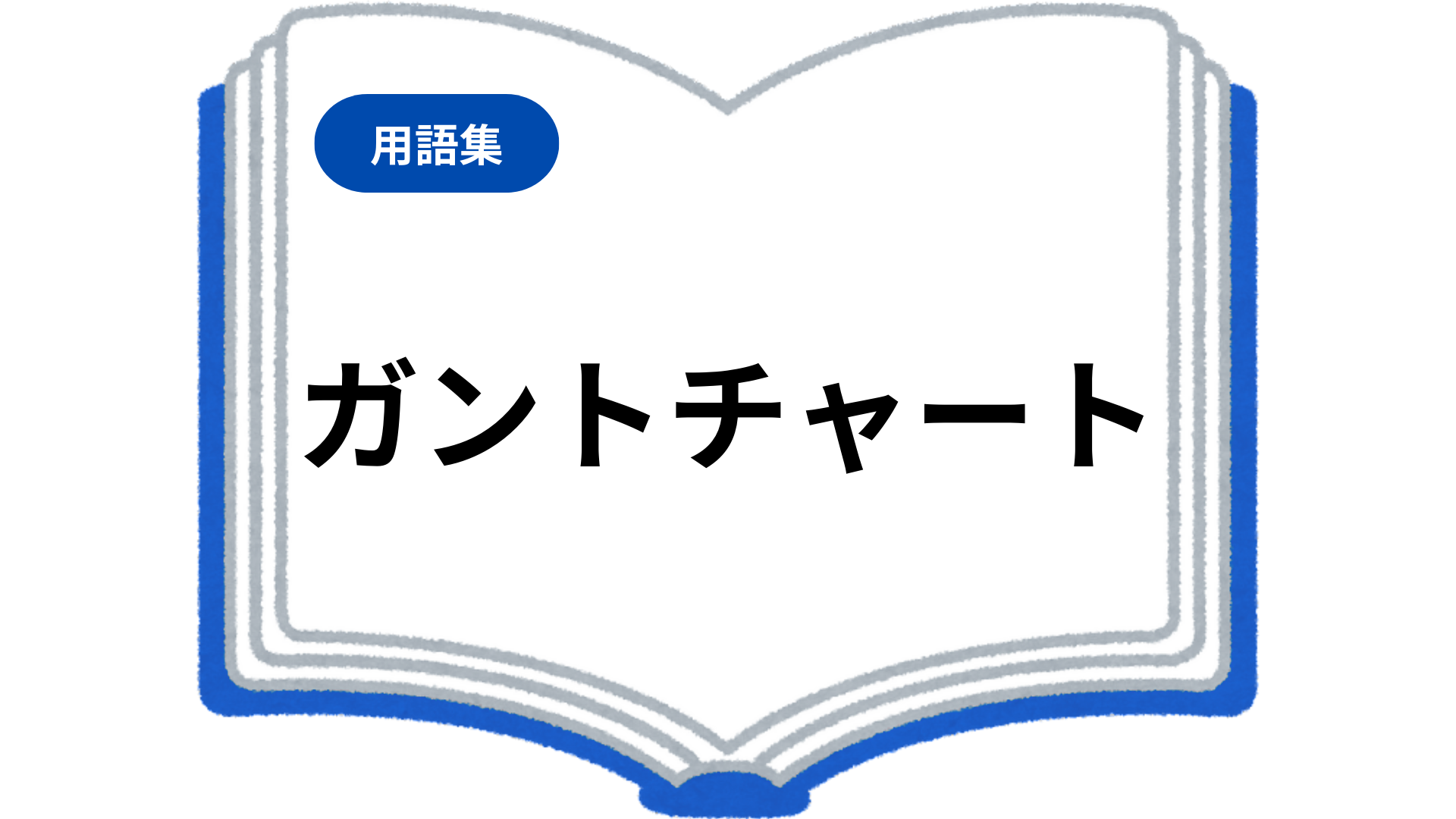
ガントチャートとは?プロジェクトの進捗管理に用いるツールについて解説
ガントチャートは、プロジェクトの進捗を管理するために作成される図表で横棒グラフで表します。
ガントチャートの最も大事な役割は「プロジェクトの進捗状況を見える化する」ことです。
横軸にプロジェクトの開始から終了までのカレンダーを配し、縦軸にプロジェクトで実行すること(WBSのタスク)を記載します。
そして、タスクごとに、開始予定日から終了予定日までを棒グラフで表現するのです。
ガントチャートは主にプロジェクトの進捗管理に使用されますが、同時に、コミュニケーションツールとしても利用します。
コミュニケーションの対象はプロジェクト関係者の場合やプロジェクトの上位組織や経営層の場合もあります。
コミュニケーション時には、当日までに完了していないといけない作業の遅れが一目瞭然に可視化され、対応策の検討に役立ちます。
ガントチャートのもう一つの重要なポイントはそれぞれのタスク依存関係が明示されることです。
タスクには「それのみを単体として進められるもの」と「先行する仕事(複数の仕事の場合もあります)が終わらないと始められないもの」があります。
これをガントチャート上で表示することにより担当者間のコミュニケーションが促進されるとともに、関係者の管理が容易になるというメリットがあります。
さらに、ガントチャート上に「マイルストーン」を記入することにより、作業進捗の目安にすることができます。
「マイルストーン」は作業の区切りとなる重要なイベントのことで、経過承認のためのミーティングや、検収テスト完了、最終承認などもマイルストーンになります。
ガントチャートは単独で作成される場合もありますが、WBSの右横に並べて記載されることが一般的です。
それは、タスクの開始予定日、終了予定日、完了日、担当者など、ガントチャートとWBSで共有する情報が多いことが理由です。
また、ガントチャートがWBSをもとにして作成されるため、WBSに追加変更があると、ガントチャートもそれに応じて変更しなければいけません。
このため、WBSから自動的にガントチャートを生成するツールも多く市販されています。
よくある質問
WBSとガントチャートの違いは何ですか?
WBSはプロジェクトで「何を行うか」を構造的に整理する技法であり、ガントチャートはその作業を「いつ行うか」を時間軸で可視化するスケジュール管理図です。両者を併用することで計画から運用まで一貫したプロジェクト管理が可能になります。
定義と目的の違い
・WBS(Work Breakdown Structure)
プロジェクトに必要な作業を末端タスクまで分解し、階層構造で整理する手法です。作業の抜け漏れ防止、担当者割り当て、工数見積りの確実性向上に有用です。
・ガントチャート
WBSで洗い出したタスクを軸に、開始日・終了日・進捗状況を棒グラフとして時間軸上に配置する工程表です。プロジェクト進行の見える化や調整、依存関係管理に効果的です。
WBSは「やるべきことを整理する骨組み」、ガントチャートは「そのスケジュールを管理するタイムライン」です。
いずれか一方では片手落ちとなるため、両者を連携利用することで、プロジェクト管理の精度と効率が向上します。
計画段階でWBSを策定したうえで、ガントチャートによって定期的に進捗をチェックし、構造と時間軸の両面を管理することが望ましいです。
工程が複雑で変更が多いプロジェクトでは、ガントチャートは不向きですか?
ガントチャートはスケジュール可視化に有効ですが、工程変更が頻繁なプロジェクトでは適切に運用しないと非効率になりやすいため、運用設計とツール選定が重要です。
主な注意点
・変更対応の柔軟性が低くなる
ガントチャートは計画に基づいたバー形式で工程を表示するため、変更が発生するたびに修正作業が必要です。頻繁な修正では、実態との乖離や管理コストの増加が懸念されます。
・依存関係が複雑化しやすい
工程数や依存関係が増えると、ガントチャートの修正範囲が広がり、更新作業が大幅に煩雑になります。
・作成・保守に手間がかかる
特にExcelなど静的なツールの場合、変更のたびにガントチャートを手動で修正する必要があり、運用負荷が重くなる可能性があります。
有効に活用するための工夫
・ローリングウェーブ計画法の併用
全期間を詳細に計画するのではなく、短期フェーズごとに計画を明確化する手法を取り入れることで、変更への柔軟な対応が可能です。
・ガントチャートは「全体の見通し用」に限定
詳細な変更管理や日々のタスク運用は、カンバンやスプリント管理ツールで対応し、ガントチャートは週次や月次レビュー向けの視覚資料として活用すると実務的です。
ガントチャートは計画段階や進捗を可視化するには優れたツールですが、変更頻度が高いプロジェクトには単独での運用は不向きです。
ただし、適切な計画手法や、運用区分の明確化により、変化にも対応できる柔軟な管理が可能です。
プロジェクトの性質と管理体制を踏まえ、目的に沿った設計と運用が重要です。
複数部門が関与する案件で、ガントチャートはどう活用すべきですか?
複数部門が関与するプロジェクトにおいては、ガントチャートを共通の進捗可視化ツールとして活用しつつ、責任体制・更新ルール・共有環境を明確に設計することが重要です。
活用のポイントと注意点
・部門間での共有と認識統一
複数部門が関わる案件では、ガントチャートを共通の最新情報を共有する基盤とし、各自がタスクや進行状況を即時把握できる状態を維持します。これにより、関係部門間のコミュニケーションが円滑になり、調整漏れや重複対応を防止できます。
・依存関係の明示と優先度管理
部門間タスクには依存関係や優先順位が発生するため、ガントチャート上でこれらを明示することで、全体スケジュールの整合性を保ちつつボトルネックの早期把握につなげます。
・責任者と更新頻度の明確化
各タスクには明確な責任者と進捗更新タイミングを設定します。担当者自身が最新情報を変更・反映する責任を持つことで、情報更新の遅延や認識ズレを防げます。
・タスク粒度と可読性の調整
全体像を崩さないためにタスクの粒度を適切に制御します。重要事項のみ粗めに管理し、微細なタスクはまとめたり別管理したりすることで、可読性と運用効率を維持できます。
・複数案件/複数部門の総合管理
複数部門かつ複数プロジェクトが並行すると混乱が生じやすいため、ガントチャートをダッシュボードやリソース管理ツールと連携させることで、情報統合と管理の効率化を図ります。
複数部門が関与するプロジェクトでは、ガントチャートを単なるスケジュール表ではなく、共通進捗管理のための参照基盤として運用することが重要です。
ただし、実効性を担保するためには、責任の明確化・更新ルール・共有環境・適切な粒度設計などの運用ルール整備が不可欠です。
これにより、部門間の調整漏れや情報の不整合を防ぎ、効率的なプロジェクト進行を実現できます。
________________________________________
あわせてこの用語と記事をチェック
・WBSとは
・情報システム部門担当者が身につけたいプロジェクトマネジメントを丁寧に解説