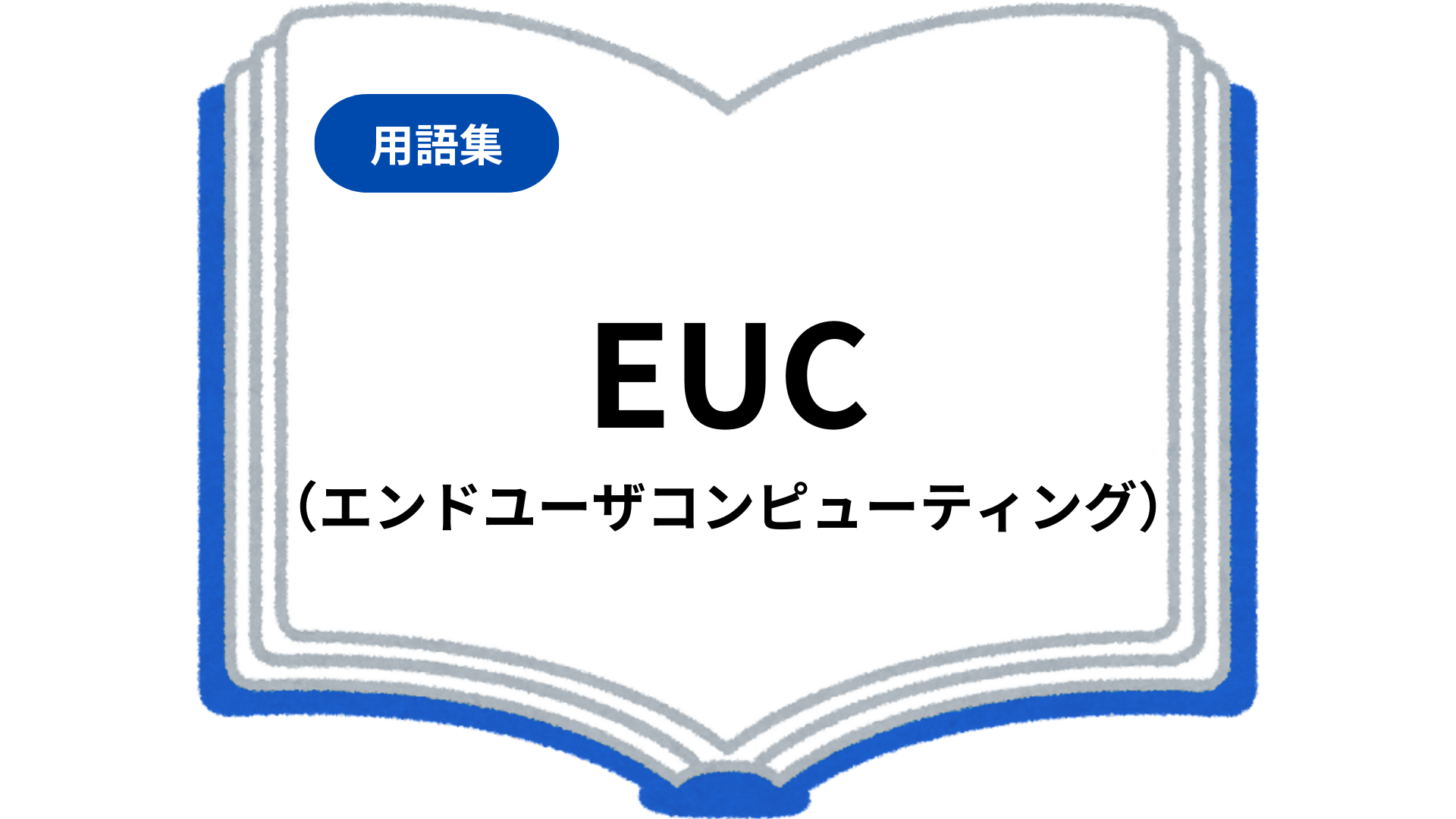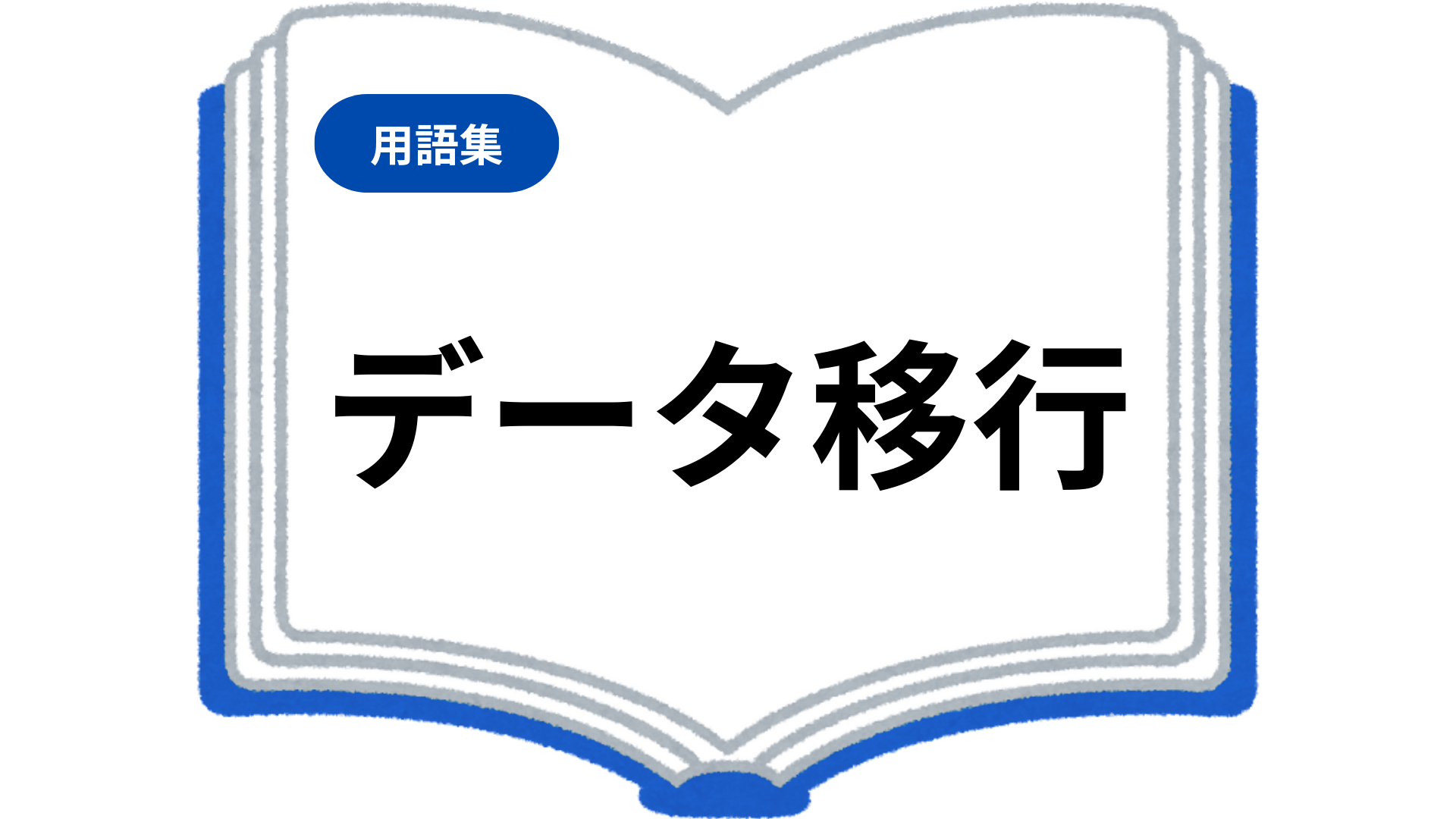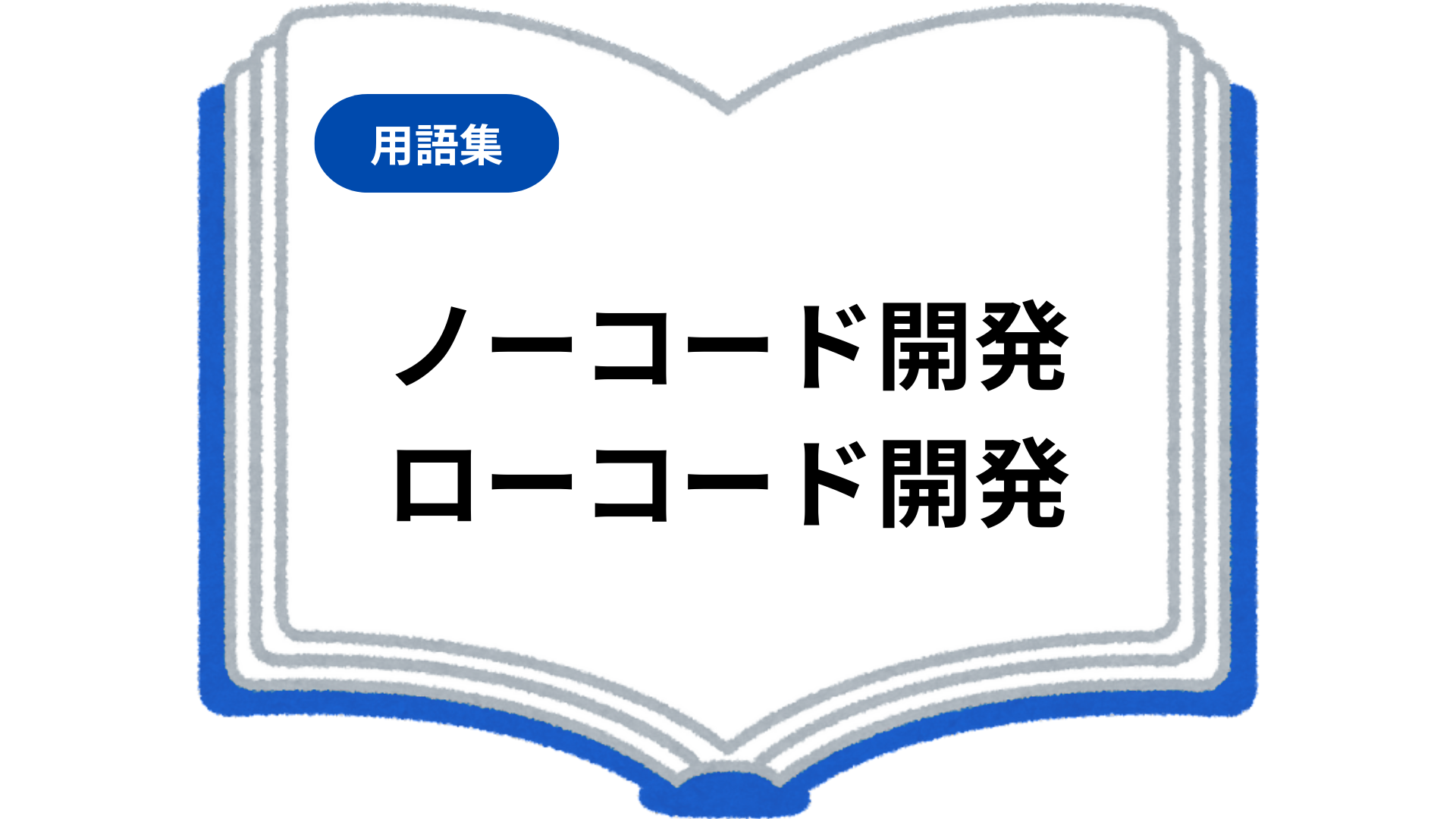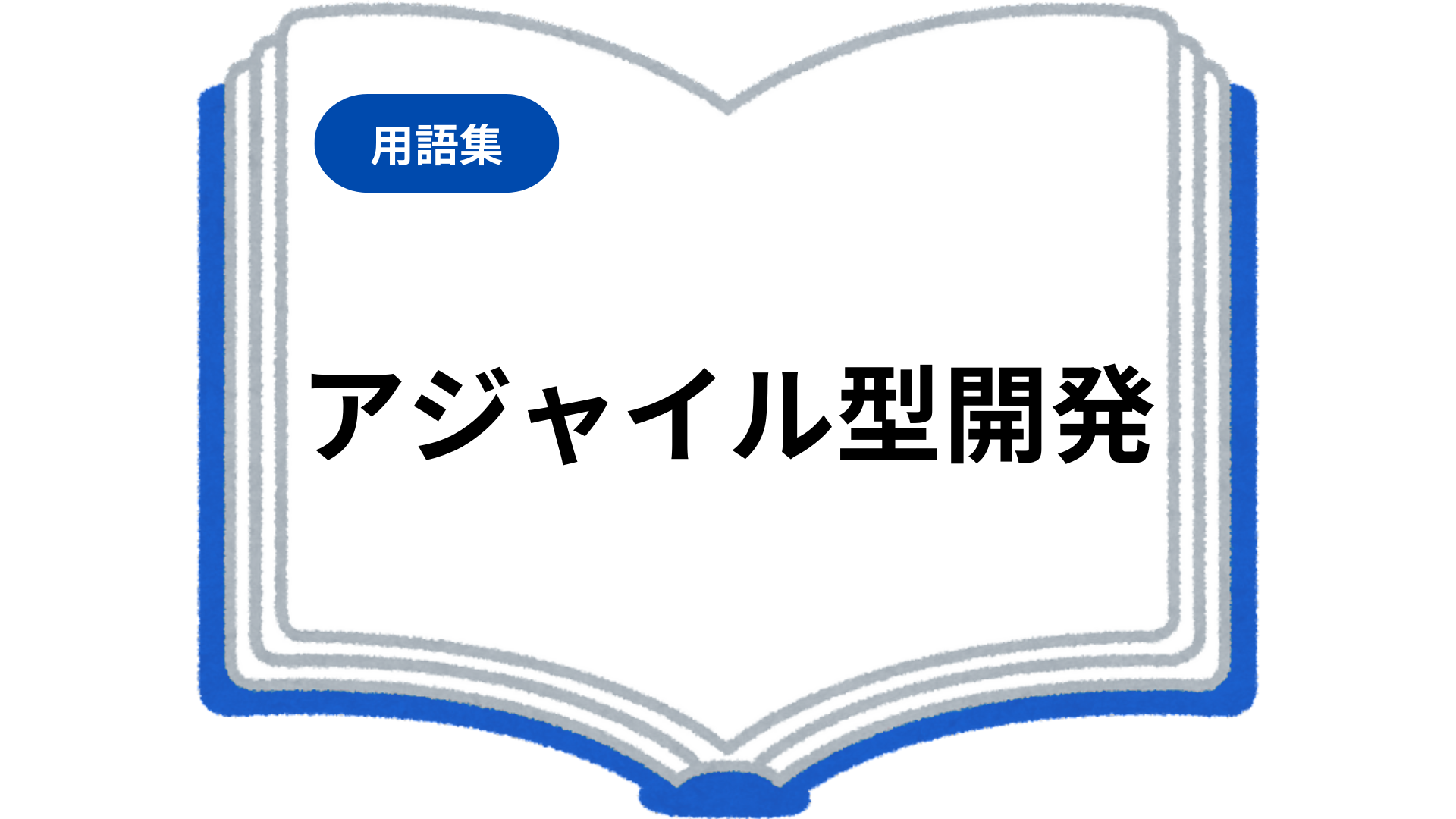
アジャイル型開発とは?変化の激しい時代に注目される開発手法について解説
アジャイル型開発とは、システム開発手法の一つであり、ビジネス環境の変化やユーザーの要望に迅速に対応することを目的とした反復型の開発スタイルです。
短期間の開発サイクル(=イテレーション)を繰り返しながら、段階的に機能を追加・改善していくのが特徴です。
アジャイル型開発の基本的な進め方は、
「設計」、「開発」、「テスト」→リリース→「設計」、「開発」、「テスト」→リリース→「設計」、「開発」、「テスト」となっています。
毎回のサイクルごとに機能単位で小さく開発・検証・リリースするため、ユーザーの声をすぐに反映することができます。
アジャイル型開発のメリットは、下記の2点です。
- ユーザーの要求を踏まえて、順次リリースを行うため仕様の変更に柔軟に対応できること
- 1つのイテレーションごとにリリースされるため、仕様変更があっても大きな手戻りが発生しないこと
一方で、アジャイル型開発のデメリットは、ユーザーの要求を踏まえてシステムの仕様を徐々に固めていくため、システムの全体感が見えにくく、プロジェクトの計画を立てづらくブレやすいことが挙げられます。
近年では、伝統的なウォーターフォール型開発とアジャイル型開発それぞれの手法の長所を柔軟に取り入れることもあります。
例えば、要求定義フェーズではウォーターフォール型で要求を定め、開発フェーズではアジャイル型開発を採用し、ユーザーの要求に柔軟に対応しながら開発を進める場合もあります。
よくある質問
アジャイル開発はどのようなプロジェクトに向いていますか?
アジャイル開発は、プロジェクトの進行中に仕様変更や優先順位の見直しが起こりやすく、全体像がまだ固まっていないような案件に非常に向いています。
例えば、WEBサービスやアプリケーション、ゲーム開発などでは、リリースしながら顧客やユーザーからのフィードバックを受けて改善する必要があるため、アジャイルの小さな反復サイクルが効果を発揮します。
また、仕様が未確定な新規開発や、DX推進・業務改革など、途中で方向転換が想定されるケースでも、まず最小限の要素から作り始め、使いながら仕様を固めていく方式が適しています 。
さらに、短い開発サイクル(イテレーション)を回すことで、リスクを抑えつつ価値を高められます。
一方、機能があらかじめ完全に固まっており、変更や調整がほとんど発生しない大規模な基幹システムやエンタープライズ設計では、ウォーターフォール型の方が管理しやすい場合もあります。
アジャイル開発を導入する際の注意点はありますか?
アジャイル開発は柔軟な対応ができる反面、導入時にはいくつか注意すべきポイントがあります。とくに次の3点は、失敗を防ぐうえで重要です。
1.全体の方向性がぶれやすい
アジャイルでは、短いサイクルで要件や方針の見直しを行います。
そのため、個別の改善に集中するあまり、当初の目的やゴールが曖昧になってしまうことがあります。
全体像を常に意識し、プロダクトオーナーが方向性を整理し続けることが求められます。
2.チーム全体の理解と協力が不可欠
アジャイルは開発チームだけでなく、顧客やマネジメント層を巻き込んだ協働が前提です。
アジャイルの理念や進め方を全員が理解していないと、認識のズレや責任の所在不明がプロジェクトを進める上での障害となります。
導入前に、関係者間でアジャイル開発に対しての共通認識を持つことが成功の鍵です。
3.最低限の計画とドキュメントが必要
「アジャイルは計画なしで進める」と誤解されがちですが、品質や進行の安定を保つには、必要最小限のドキュメントやスケジュール管理が欠かせません。
変化に対応するためにも、柔軟性と計画性のバランスが大切です。
アジャイルを成功させるには、単に開発手法を変えるだけでなく、組織全体で価値観と進め方を共有し、変化を前提とした体制づくりを行うことが重要です。
アジャイル開発で見積もりや納期はどう管理されますか?
アジャイル開発では、従来の「すべての要件を決めてから開発に入る」方式とは異なり、変化に対応しながら開発を進めるという考え方が基本にあります。そのため、見積もりや納期の管理方法も柔軟性を重視したアプローチが取る場合が多いです。
現在も多くの企業では、見積もりを行う際に「作業時間(工数)」や「それに基づく金額」で提示するケースが一般的です。初期段階では、過去の類似プロジェクトの実績や、エンジニアの経験値をもとに概算を行い、大まかな納期と予算を設定します。この時点では、要件がすべて決まっていない場合も多いため、一定の幅を持たせた見積もりが行われることが多いです。
アジャイル開発では、開発を複数の短い期間(スプリント)に分けて進め、定期的に成果物を確認しながら調整していきます。そのため、「毎回のスプリントでどのくらいの作業が完了したか(=進捗)」を確認しながら、納期までに対応できる内容を柔軟に調整するのが特徴です。進捗が遅れている場合は、機能の優先順位を見直したり、一部のスコープを次フェーズに回すなどの対応が可能です。
また、アジャイルに慣れているチームでは、タスクの難易度や規模を「ストーリーポイント」と呼ばれる単位で見積もる方法も活用されています。ただし、これはすべての企業で一般的に使われているわけではなく、従来型の工数見積もりと併用されているケースも多く見られます。
このように、アジャイル開発では初期での厳密な固定ではなく、進捗を見ながら継続的に調整することが基本となります。結果として、変化に対応しやすく、価値の高い成果物を安定的に届けることが可能になります。
________________________________________
あわせてこの用語と記事をチェック
・ウォーターフォール型開発とは