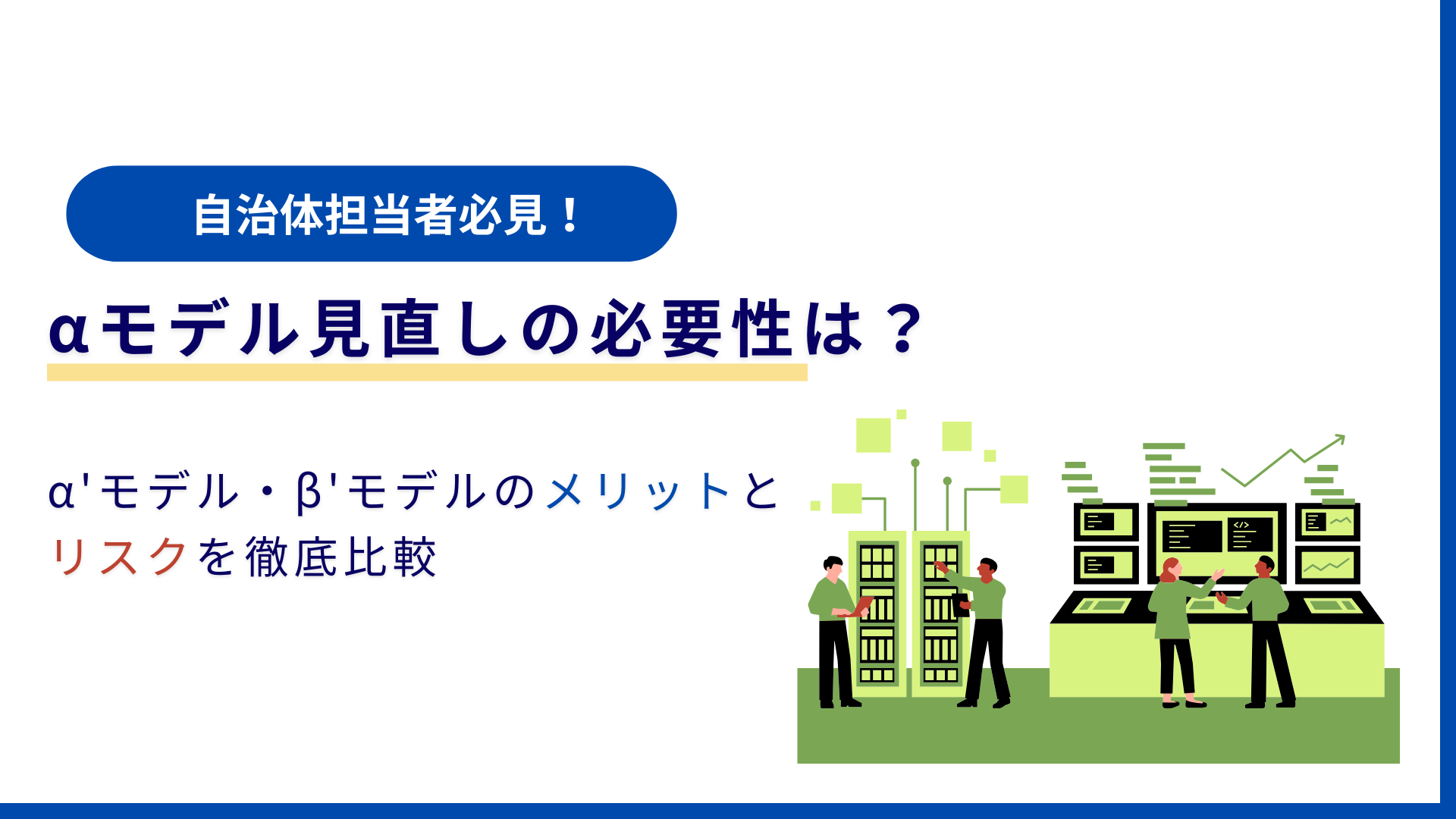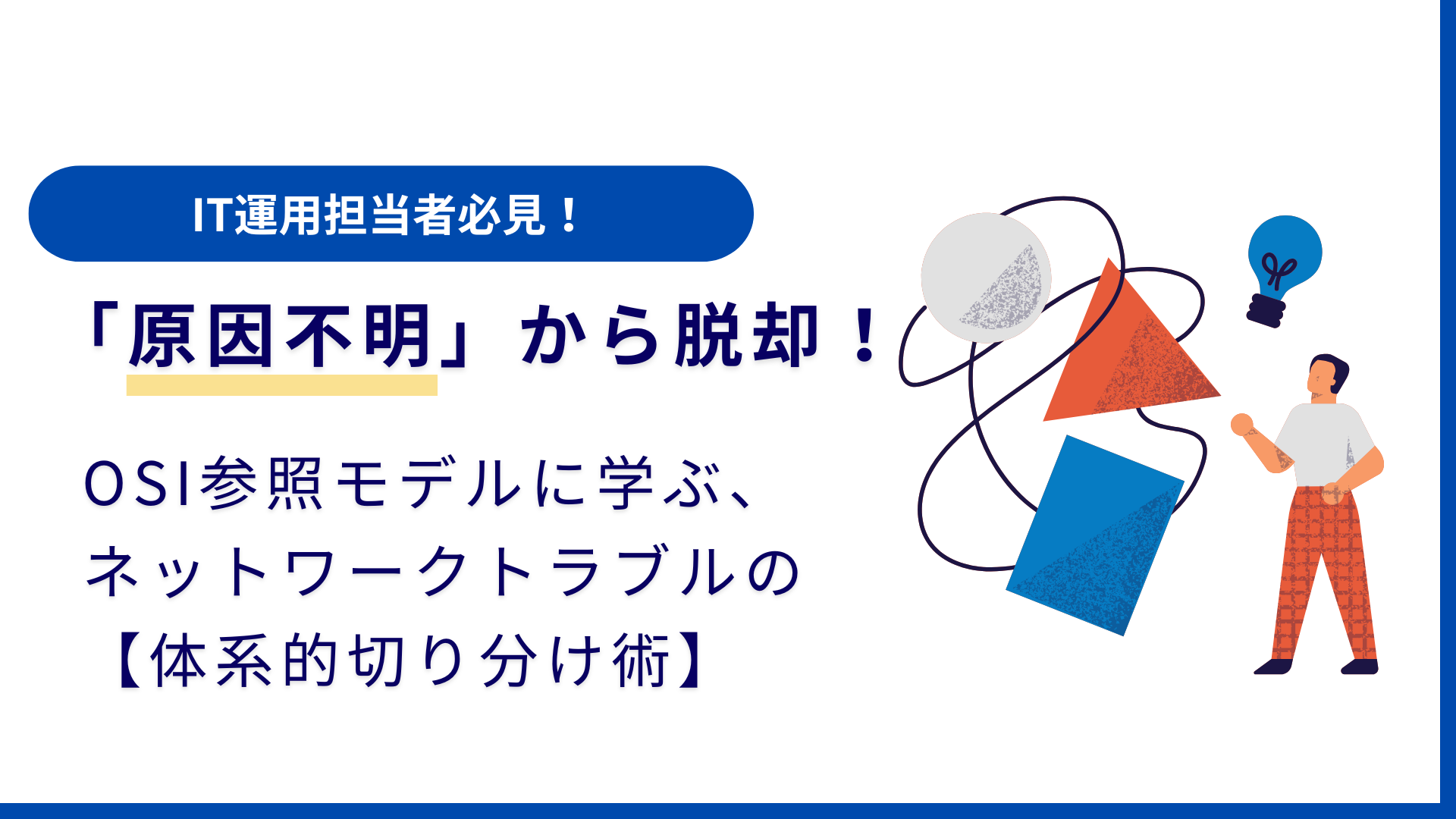GovTechとは?行政×テクノロジーで進化する行政サービスについて解説
GovTechとは、行政機関(Government)と技術(Technology)を組み合わせた造語で「行政機関がテクノロジーを使ってより良いサービスを提供すること」を意味します。
たとえば、オンラインの窓口開設や行政手続き、AIを活用した政策の立案、住民からの意見の収集や、住民への情報提供を効果的に行うデジタルツールなどが該当します。
GovTechの目的は、行政サービスをより便利で効率的にし、住民がその恩恵を受けられる仕組みを作ることにあります。
GovTechを支える技術としては、情報技術やデジタル技術があります。
単にデジタル化するだけでなく、それらを活用して行政サービスや業務プロセスを根本的に見直し、住民にとってより価値あるサービスを提供します。
そのために、自動化やデータ活用で行政職員の作業負担を軽減する「業務効率化」、オープンデータやリアルタイム情報の共有を実現する「透明性と信頼性の向上」、災害時など緊急時の情報提供や支援体制を強化する「迅速な対応」、オンライン手続きの普及促進等による「住民の利便性向上」と同時に窓口対応の負担も軽減するなど、行政の多岐にわたる取り組みがあります。
GovTechを支援する団体も登場してきました。
東京全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のプラットフォームとして2023年に東京都の政策連携団体として一般財団法人GovTech東京の設立や、行政分野のITに携わる企業が集まり一般社団法人GovTech協会設立など、行政機関への支援体制の動きも出てきています。
目次
よくある質問
GovTechとデジタル政府(デジタル・ガバメント)との違いは何ですか?
GovTechは「行政側がデジタル技術を活用して新たな行政サービスや業務変革を実現する取り組み」であり、デジタル・ガバメントは「行政のあり方そのものをデジタル前提で再設計し、サービスを提供する国家戦略」です。
定義と概念の違い
・GovTech(Government Technology)
政府や自治体が、AI、クラウド、ローコードなどの最新技術を使って行政サービスや業務プロセスを革新する取り組みを指します。行政自身が技術開発や運用主体となる場合もあります。
民間企業やスタートアップとの協働による行政DXとして推進されるほか、住民向けサービスだけでなく、行政内部の業務効率化にも焦点が当たります。
・デジタル・ガバメント(Digital Government)
行政サービスについてデジタル技術を徹底活用し、利便性の向上並びに行政運営の効率性及び透明性の向上を実現するための国家的な政策・戦略のことです。
日本では、ワンスオンリー、デジタルファースト、コネクテッド・ワンストップといった三原則に基づく実行計画が策定されています。
GovTechは「テクノロジー×行政」の実践アプローチであり、行政サービスや業務改善に焦点を当てた技術活用の動きです。
一方、デジタル・ガバメントは行政全体の構造や政策を見直し、行政手続きの電子化やサービス設計そのものを変える国家的取り組みです。
GovTechの理念を踏まえた公共システム導入・調達で重視すべきポイントはありますか?
GovTechの取り組みにおいては、「公共性」「実現可能性」「持続性」の3点を軸に、制度や現場の運用に即した視点で技術やサービスを評価することが重要です。
評価・選定時の重要視点
1. 制度適合性と公共性の担保
関連する法令(地方自治法、個人情報保護法等)への適合は公共調達の基本要件であり、GovTechであってもこれを遵守することは必須です。
加えて、自治体の制度運用や地域の実情に即し、他自治体への横展開や複数拠点での利用を視野に入れた設計が評価されます。
また、調達においては、透明性のある公正なプロセスとする必要があります。
2. GovTechスタートアップなど革新的サービスの活用
単に大手ベンダーだけでなく、スタートアップの技術や発想を取り入れることで、柔軟かつ迅速なサービス提供が可能になります。いずれも公共調達ガイドラインに沿った調達を行う必要があります。
3. 共同調達や県・都市単位での実証を活用
自治体間でシステムを共同調達することで、コストの圧縮やノウハウ共有が可能になります。また、実証実験を経て導入することで適合性を事前に確認できるなどのメリットがあるため、導入時のリスクを低減できます。
4. 評価体制と改善のサイクル設計
導入後に改善提案やアップデートを行う体制があるか、利用者や職員のフィードバックを反映できる仕組みの整備状況も重要です。技術や制度の変化に応じて柔軟に対応可能であるかを評価視点に含めます。
GovTechに基づく公共システム導入では、制度面の整合性と技術的革新の活用を両立しつつ、共同調達による効率性・標準化、そして導入後の改善体制までを評価軸として重視すべきです。
自治体自身がこれらの観点を明確にし、判断基準として整理することで、効果的かつ持続可能な調達が実現できます。
GovTechの考え方に基づいた取り組みによって、地域の行政運営や住民サービスにはどのような変化がもたらされますか?
GovTechの考え方に基づいた取り組みを進めることで、行政内部の業務の効率化や住民サービスの利便性向上が期待されます。
既存の制度や運用を尊重しつつ、デジタル技術を段階的に活用することが重要です。
想定される主な変化
1. 手続きの一部オンライン化と処理効率の向上
申請・届出などの手続きがオンラインに対応することで、窓口訪問の負担が軽減され、処理時間が短縮される場合があります。ただし、制度上の制約や利用者のデジタル環境への配慮も必要です。
2. 業務プロセスの標準化と属人化の抑制
業務フローの見直しやシステム活用により、手続きのばらつきや属人対応が抑えられ、組織的な運用体制が構築されやすくなります。
3. データ利活用の素地整備
行政内における業務データや住民情報の整備が進み、政策立案や改善施策の検討に活用できる基盤づくりが可能となります。
4. 住民視点に配慮したサービス設計
利用者の視点に立った設計が進み、UI・操作性が向上するケースもあります。高齢者やデジタルに不慣れな方への対応や、対面支援との併用も併せて検討されます。
GovTechの取り組みは、行政運営と住民サービスの両面で変革を促す可能性を持ちますが、即時的な成果を求めすぎず、中長期的な視点で段階的に進めることが求められます。
関係者間での丁寧な合意形成を通じて、制度や現場に即した実行が重要です。
あわせてこの記事をチェック